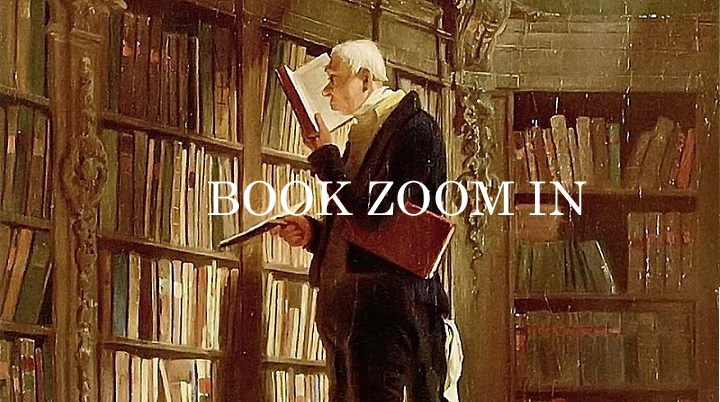後藤里菜『沈黙の中世史――感情史から見るヨーロッパ』、ちくま新書、2024年、1,100円(税込)
文字を読み書きできない人が多く、学問や執筆が男性の聖職者や権力者によりほぼ独占されていた中世。その時代のほとんどの人の声は歴史の闇に消えていきました。ほとんどの人は社会や思想によって沈黙を強いられていたといえるでしょう。ですが、彼ら/彼女らは文字の読み書きを通じて自己表現できない分、たくさん喋り、騒ぎ、叫んだはずです。中世とは喧騒と沈黙が奇妙に入り混じる時代だったのです。今回紹介する『沈黙の中世史』は、そんな中世ヨーロッパの沈黙と喧騒の世界に読者をいざないます。

「感情史から見るヨーロッパ」という副題が示す通り、本書は感情の観点から中世ヨーロッパにおける沈黙と喧騒の歴史を見つめます。古代ギリシア=ローマの古典的教養とキリスト教という知的精神的伝統の上に形作られた中世ヨーロッパについて学ぶ際に、それらの知識は前提として必要ですが、本書では事あるごとにそういった背景を説明してくれるため初学者でも安心です。と同時に、豊富な一次史料の引用と参考文献表があるため、この分野に関心を持っている人も飽きることなく読み進めることができるでしょう。
そんな本書は章ごとに多様な場所、地位、性などを対象としています。第一章では沈黙の最たる場所と考えられる修道院が舞台となります。映画『大いなる沈黙へ』など修道院における沈黙は、多くの人々の知るところとなっています。ですが、沈黙が支配している修道院でも、〈叫び〉(clamor)という喧騒を想起させる儀式が存在しました。静寂の場と考えられている修道院における沈黙と喧騒の霊性について聖ベネディクトゥスの『戒律』などを参照しながら見た後の第二章では、トゥールの聖グレゴリウスの『歴史十章』を主な情報源としながら、君主にとっての沈黙と発声について考察されます。
このように、初めの二章は修道院と君主という地位を主に扱います。続く第三章では服喪という感情が表出するであろう具体的な場、第四章では修道院以外の場における祈りと霊性について書かれます。そして第五章からは、男性により黙すことを強いられていたと考えられる女性の声が対象となります。聖ヒルデガルト・フォン・ビンゲン、マーキエイトのクリスティーナ、マルグリット・ポレート、マージェリー・ケンプ、そしてクリスティーヌ・ド・ピザンといった女性たちが登場し、中世における女性と沈黙、ないしは叫びについて証言してくれます。
政治史や宗教史、思想史といった観点から中世を考究する本は多くあれど、感情の観点から中世という喧騒の時代を見る本は、日本ではまだ多くありません。『沈黙の中世史』というガイドブックを手に、喧騒と沈黙の入り混じる中世ヨーロッパへの旅に出てみてはいかがでしょうか。
石川雄一(教会史家)