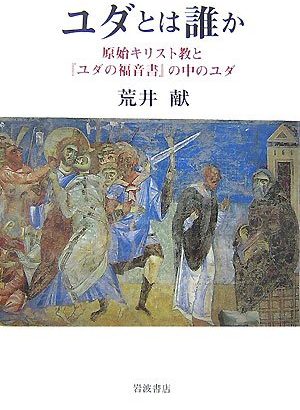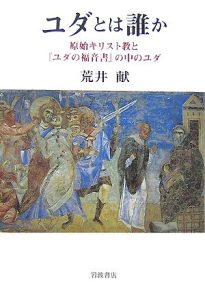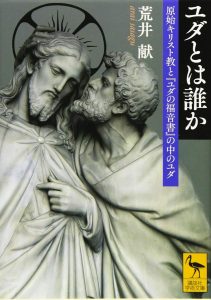AMOR編集部
イスカリオテのユダについて考えたいと思い、日本人著者の文献を探していくと、数年ごとに繰り返しユダに触れる論著が発行されていることに気づく。その事実自体が興味深い。主なものを紹介しよう。
イスカリオテのユダが「旦那さま」のもとに駆け込み、イエスのことを「あの人を生かして置いてはなりません。世の中の仇です」と訴え始める内容という設定で書かれている作品。太宰の口述を妻が筆記したものという。ユダの存在が太宰の文学的想像力をどのように刺激しているのか、一聴である。
聖書や他の歴史資料を参照し、イエスの史実、真実に自ら小説家的想像力をもってアプローチしていく作品。「イエスの生涯を小説家として書いたものであるから聖書におけるその使信についての神学的解釈もない」「イエスの人間的生涯の表面にふれたものにすぎぬ」(あとがき)と断わっているが、そのことによって、読書界においてイエスへの関心を呼び起こしたことは確かだろう。
この中で第8章がイスカリオテのユダにあてられている。題して「ユダ、哀しき男」。ユダへの問いかけを呼び起こすインパクトがあろう。ユダのことを裏切り者、悪魔が入った者としてイメージしていた教会的ユダ像があったとすれば、この表題はショッキングなものだっただろう。
「我々はユダをイエスの単純な反抗者とは思えない。なぜなら多くの弟子たちがイエスを次々と見棄てた後も、ユダは師のあとを従ってきた一握りの者たちの一人だったからである」「彼(=ユダ)は師の運命がもはや変えられぬのを感じていた。そしてまたユダは仲間の弟子たちがその時、イエスを見棄てるだろうことも想像していた。イエスが孤独のままで捕われ、苦しみ、死ぬかも考えたのは彼だけだった」(新潮文庫版 124-25ページ)……あらためて注目したい書になっている。
美学・美術史の専門家である著書が、ユダの図像学として、最後の晩餐の図の考察から入り、ヨーロッパ精神史、文化史に内在するユダ像を探っていく書。「裏切り」の文化史的、心性(メンタリティー)史的探求でもあり、このような主題化として、日本では先駆的な著作なのではないだろうか。
2006年に『ユダの福音書』が話題になった状況へのレスポンスとして、著者のユダ論が集中的に発表されたなかの代表作。第一部は「原始キリスト教とユダ」として、福音書を対象として、その共観的対照を通しての考察となっている。教会、信仰という観点からイスカリオテのユダを考えるためには入り口となる内容である。
際立つのが、マルコ福音書におけるユダ像を確証するプロセスで、最後の晩餐においてもユダが同席していること、ガリラヤにおける復活のイエスとの再会を約束されていること(マルコ16:7)、弟子たちから排除されていないと考えられることが指摘されている。他方、復活したイエスに会うのはマタイ、ルカにおいて「11人」と語られ(マタイ28:16-17;ルカ24:33)、ユダの排除が明白になっていく。また、マタイ、ルカ(使徒言行録)で、ユダの死がそれにまつわるエピソードとともに語られる(マタイ27:3-10;使徒言行録1:16-26)。ヨハネ福音書に関しては、「ユダは、……とりわけヨハネ福音書で最も強く『悪魔』化されていると同時に、このユダによる官憲への『引き渡し』、神の定めに従う、イエスの意思の結果であることが強調されている」(岩波書店版 109ページ)と指摘されている。
第2部では使徒教父文書・新約聖書外典と『ユダの福音書』のユダについての観察、紹介となっていく。
- 岩波書店版(2007年)
- 講談社学術文庫版(2015年)
この編著も2006年に『ユダの福音書』が話題になった状況へのレスポンス作。このブームの様子が「はじめに」に記されていて興味深い。本編は、ユダに関する原典資料集というべきアンソロジー(抜粋集)。正典福音書、新約外典、『ユダの福音書』のそれに該当するグノーシス主義文書、正統主義教父著作、中世の伝説、近現代の文学、神学著作からの抜粋など、上掲の太宰治、遠藤周作の抜粋も含まれている。
荒井氏の上掲書『ユダとは誰か』の続編にあたる書。前著が「比較的には学問的論述になっているのに対して、本書では、それを踏まえた上で、私の想像力の翼を広く拡げ、自由にいわば『文学』風に描写することを目指した」(viiページ)という。自著を踏まえているだけでなく、大貫隆編著の上掲書のアンソロジーも活用した、ユダ観、ユダ像の変遷史ダイジェストといえるもの。各章の表題がそのユダ観の変遷の様相を要約している。
新約聖書にすでにみられる「ユダは救いの内に」から「ユダは救いの外に」へ、そしてグノーシス主義における「ユダは救いの遂行者」像が見られ、中世における「ユダは地獄に」への変化(究極にはダンテの『神曲』)、またヨーロッパの底流にあるユダとユダヤ人の同一視という事象に触れたのち、近代における「ユダの復権」現象が、太宰の作品や『ジーザス・クライスト・スーパースター』(別稿参照)への言及も含んでいるところは興味深い。
著者の立場は、マルコを踏まえてのユダは、意外なことに「はじめに」にあたる文章のタイトル「予断・診断・独断 誰の内にもユダは棲む?」に示されている。ユダはイエスの愛の圏外に置かれてはいない。「イエスが自ら選んだ弟子の一人がユダであっただけではなく、イエスが同時に選んだ他の他の弟子たちにもユダは棲んでいた、とすれば、誰の中にもユダは棲んでいる」(120ページ)。
このような文献案内であまり紹介されることのない『新カトリック大事典』の項目記事を紹介しておく。著者はさいたま教区司祭であった清水宏師(2016年帰天)。『ユダの福音書』、荒井献氏の著作などの動向を踏まえて、ユダに関する確かな基礎知識をコンパクトに提供してくれる。荒井氏によっても論究された、ユダの行為は新約聖書では「パラディドーミ」というギリシア語(「渡す」「引き渡す」)と表現されていることをまず明確にする。これは、無条件に「裏切り」と翻訳も理解もできないこと、ユダの行為も「裏切り」と断定できないことを示している。引き渡すのは大祭司であり、群衆であり、ピラトもしていたことである。
マルコからヨハネへの成立順の概観ではユダに対する描写がたしかに否定的になっていくことは見られるが、とはいえ、「歴史上のユダの姿と役割内容を新約聖書の叙述から判然とさせることは極めて困難である」。芸術史においては、ユダはユダヤ人の特徴をもって描かれるようになり、「『裏切り者』『(金銭に)強欲な者』『神殺し』『懲罰者』など、ユダは反ユダヤ主義のための『原型』とみなされるようになる」ことが指摘される。そして、ユダの全容は、「単に歴史的また聖書解釈上の事柄として扱うだけでは不充分であって、反ユダヤ主義の克服をも視野に入れ、聖書全体に即して神学的な救いの問題として扱うべきだろう」というのがこの項目の結論である。
その例として、邦訳のあるカール・バルトの『イスカリオテのユダ』(吉永正義訳 新教出版社 1997年。別稿参照)、ハンス・ウルス・フォン・バルタザールの『過越の神秘』(九里彰訳 サンパウロ 2000年)が挙げられている。最近では、バルトに触発されて研究と思索を始めたという牧師の著書もある。小野寺泉著『キリストとユダ 四つの福音書が語ること』(一麦出版社 2018年)である。
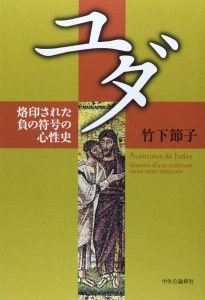 今年3月に休刊となった『カトリック生活』での連載「カトリック・サプリ」で知られる文化史家・竹下節子氏の書き下ろし作品。裏切りのキャラクターとして突出しているユダが「キリスト教の神学の中でどのように解釈されてきたか、ヨーロッパ世界でユダ伝説がどのように必要とされてどのように形成されてきたのかを概観する」(「はじめに」より)なかで、カトリック的なもの、プロテスタント的なもの、またロシアにおける正教的なものにまで視野を広げている。「反ユダヤ主義とユダ」は、本書の最も大きな貢献であるかもしれない。ヨーロッパ文化の深層で「裏切り者」の記号となってユダに注目して、照らし出される諸関係はしばしば陰鬱である。
今年3月に休刊となった『カトリック生活』での連載「カトリック・サプリ」で知られる文化史家・竹下節子氏の書き下ろし作品。裏切りのキャラクターとして突出しているユダが「キリスト教の神学の中でどのように解釈されてきたか、ヨーロッパ世界でユダ伝説がどのように必要とされてどのように形成されてきたのかを概観する」(「はじめに」より)なかで、カトリック的なもの、プロテスタント的なもの、またロシアにおける正教的なものにまで視野を広げている。「反ユダヤ主義とユダ」は、本書の最も大きな貢献であるかもしれない。ヨーロッパ文化の深層で「裏切り者」の記号となってユダに注目して、照らし出される諸関係はしばしば陰鬱である。
現代のカトリック教会も、第2バチカン公会議による近代化を認めない教条主義分派から「伝統を時の流れに売り渡したユダ」と呼ばれているのだという。「おわりに」で著者自身も語っている。「ユダを通してキリスト教社会の確執を眺めていく作業にかかってみると、たくさんの気づきをもらうと共に、人間の心の深淵をうかがい見るような重い気分にさせられた」(209ページ)、「ユダに託す自己弁護の隠れた欲求が芬々(ふんぷん)とする毒気にあたられたとい言った方がいいかもしれない」(210ページ)と。
上林順一郎師の「復活は誰のために」、石原綱成氏の「図像で追う ユダの原風景」(別稿参照)、水野隆一氏の「ユダは何を問いかけるのか 『ジーザス・クライスト・スーパースター』から」の三編の記事が集められている。ユダへの注目と信仰の観点、文化史への展望も含む問いかけは、尽きることなく続いている。
最後に紹介するのは、『寅さんとイエス』(筑摩書房 初版2012年、改訂新版 筑摩選書 2023年)、『寅さんの神学』(オリエンス宗教研究所 2022年)というユニークなタイトルの著書で知られるドミニコ会司祭・米田昭男師の最新刊。その第一章と第二章で、『ユダの福音書』が取り上げられ、この書についての解説、イスカリオテのユダについての論考が収められている。全体の三分の一ほどにも及ぶ扱いである。しかし、全体は「笑い」を主題としたイエス研究、イエス論であり、それ自体が興味深い。