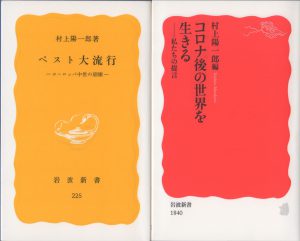ペストは、そのときだけでなく、その後もたびたびあって、1665年のイギリスでの流行のときは、ニュートンが大学の休校中の休暇の間に万有引力の法則を発見したという逸話があったことまで紹介されています。
19世紀末に中国大陸から始まったペストの流行は1910年代まで影響を及ぼしていて、それを背景にアルベール・カミュが『ペスト』という小説を生み出したそうですよ。この小説も今年は注目されましたね。
今、国境を超える地球全体の問題がこの事態に深くかかわっていることを知り始めたに違いない。環境破壊、過剰な人口、膨大な食料の生産、野放図な自由主義経済、そこからの脱落者の切り捨て、地球全体の資源配分の誤り(軍事費の増大など)等々、多くの問題が連鎖して今回の事態に至っている。……来るべき世界はむしろ、何の分野であれ無用の敵対的競争を抑制し、自然とも和解し、人間が境界を超えて共生する世界であるだろう。
この危機を境に、禍々(まがまが)しいものの象徴としての「近代」が終わる。いや、終えなければならないし、いまが最大の好機なのだ。
(『コロナ後の世界を生きる――私たちの提言』196~197ページ)
ちょうどそのころクラウス・リーゼンフーバー師(1938年生まれ)が中世思想研究所を創立して、「中世思想」という名のもとで古代の教父思想から15世紀ぐらいまでの思想原典集成という大事業を始めたのだよ。日本では未知の原典が知られるようになったという点が、大きな貢献となっている。
自分も若きリーゼンフーバー先生の授業の学生のひとりだった。わからないことが多かったけれど、あの博識の知性の“雰囲気”には触れた授業は感動的な懐かしい思い出だよ。
ちなみに、阿部謹也さんについては、この特集で、伊藤淳神父が自分の大学の時の恩師だったということで、その面影を書いてくれている(西洋中世社会史学者阿部謹也の秘密)。貴重な記事なので、ぜひ、読んでもらいたいな。
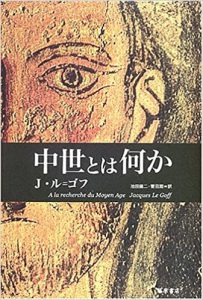 ずいぶん昔のことのように言われてしまったな。今も十分、その動きの中にあるのではないかと思っているけれどね。
ずいぶん昔のことのように言われてしまったな。今も十分、その動きの中にあるのではないかと思っているけれどね。さっきあげたル・ゴフからは『煉獄の誕生』(邦訳 法政大学出版局 1988年)でとくに刺激を受けたけれども、最近の『中世とは何か』(邦訳 藤原書店 2005年)では、彼自身が20世紀フランスの歴史学の革新の中でどのような学問人生を歩んできたかをインタビュー的に語っているのが面白かった。
ともかくも、世界史で学ぶヨーロッパ中世は王朝の変遷や戦争の歴史や皇帝と教皇の対峙という社会の上層の出来事が中心になっているのに対して、新しい歴史学は社会の構造の歴史、無名の民衆のメンタリティ、信仰心、人生観、生活文化を解明してくれているようで新鮮だったよ。
今年4月、皆川達夫さん(1927~2020)が亡くなっただろう。ラジオで長くバロック音楽のことを渋いお声で紹介してくれた人だった。キリシタン音楽の研究も重要な業績とされている人だ。
1990年代、CD時代になると中世音楽、グレゴリオ聖歌もほんとうに親しまれるようになり、「古楽」という分野が研究や演奏の分野として確立されて今に至る。宇宙の音楽、人間の音楽、楽器の音楽があると紹介してくれたのも新鮮だった。
けれどそんな音楽思想は中世に限らず普遍的なのではないかなと思うよ。そんなところも、この特集で東京藝術大学の渡辺研一郎さんが書いてくれているね(現代の音楽家にとってのネウマ)。
考えてみると「古代・中世・近代」という三区分にはヨーロッパが前提とされていて、いわばヨーロッパが世界と同一視されていたニュアンスがあるし、古代から中世へ、そして近代へという直線的な進歩史観が前提にもあったようだ。
なので、日本の歴史には、一応の研究専攻カテゴリーとして「日本古代史」「日本中世史」という区分があって、さらに「日本近世史」「日本近代史」という区分もあるという具合で、あんまり適合しないことがある。「近世」という中世と近代の中間概念があって、ヨーロッパにも適用されるなど、時代区分概念も用語もいろいろだよ。
そんなあたり、この特集の中の倉田夏樹さんの記事(コンスタンティノープルのニコラウス・クザーヌス枢機卿――イスラームと対話した「暗黒中世」の教会政治家)と一緒に考えてみてもよいかもしれない。
そんななかで「中世的なもの」とか「近代的もの」という時代区分論的な評価はもう役立たなくなっている。中世が暗黒時代として克服されるべきものではなくなり、近代がだれもが目指すべきものとしての普遍的価値を失っている時代だからかもしれない。
そうはいっても、便宜的に「ヨーロッパ中世」とくくられる時代のさまざまな事象は厳然として存在するし、そこをどう見ていくかということが課題になる。
キリスト教はパレスティナで生まれ、地中海世界や東方にも広く伝播していった。ヨーロッパ大陸というべき方面への宣教は1000年頃までずっと継続されていって、とくにその西方ヨーロッパのキリスト教が近代宣教で広がるカトリックやプロテスタント諸教会のもとになるから、どうしても、キリスト教をヨーロッパの宗教と思いがちだ。でも、違うということだね。
あんなに「キリスト教的」といわれている時代が、典礼を基準に考えると、それほど「キリスト教的」とはいえないという逆説になってしまう。ただ、今の典礼行為の中や典礼・秘跡神学の中には実際、中世というヨーロッパ・キリスト教において発生して、大事に継承されているのも多いからね。
ただ、それが近代への反省や中世に対する見直しの一定の実りといえるけれども、本当に新しい時代を創り出せているか、あるいはキリスト教の新しい時代のあり方を反映するものとなっているかどうか、といえば、まだわからない。
すべては「キリストの時」、あるいは今はキリストの第一の来臨から第二の来臨の間を生きる「中間の時」(教会の時代)だという観点をもって、その中の具体的な一時代、諸世紀として考えていったらどうかな。
「キリストの時」に基づく歴史観(救済史観)や典礼史的な見方を、新しい歴史学がもたらした成果とも絡ませていくことが必要なのではないかなと、つねづね思っているところだよ。
おっと、だいぶ長話になったかな。リモート出演も、そろそろ失礼しよう。この辺で。
(企画・構成 石井祥裕/イラスト・脚色 高原夏希)