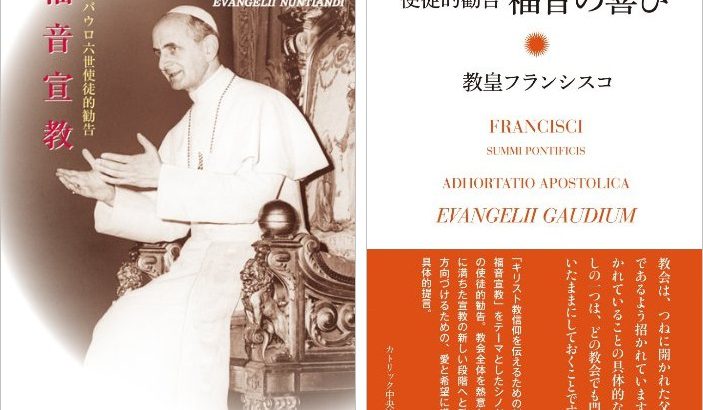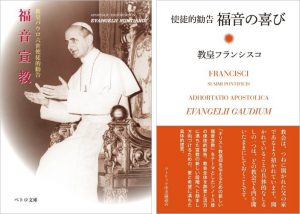石井祥裕(典礼神学者)
決して新しいものではない
教皇フランシスコが、実質的に自身の理念を言葉にしたといえるのが、2013年11月24日付で発表された使徒的勧告『福音の喜び』(Evangelii Gaudium)です。前教皇ベネディクト16世が開いた「信仰年」(2012年10月11日開幕~2013年11月24日閉幕)にちなみ、その閉幕の日付をもって発表されたこの使徒的勧告は、信仰年開幕時に開催されていた世界代表司教会議(2012年10月7日~28日)のテーマ「キリスト教信仰を伝える新しい福音宣教」と、そこでの討議を踏まえて出されているものです。
あたかも1975年のパウロ6世の使徒的勧告『福音宣教』(Evangelii Nuntiandi)が、前年開催された「現代世界の福音宣教」をテーマとする世界代表司教会議にこたえて出されたことと似ています。どちらも、第2バチカン公会議(1962~65年)の理念を、「福音」というキーワードのもとにとらえてキリスト教本来の使命を確認し、全教会に向けて実践を励まそうとしているものです。状況としては同じです。
その意味では、『福音の喜び』はテーマとしては新しいものではありませんが、第2バチカン公会議から半世紀たったところで、この公会議が意図したことを、新たな感覚で述べたものといってよいと思います。もちろんいろいろなところに、フランシスコらしい表現が散りばめられています。「先送りできない教会の刷新」とか、福音宣教者に求められる姿勢として「出向いていくこと」「率先すること(プレメレアル)」「寄り添うこと」を掲げるところなど。しかし、それらばかりに注目するのではなく、公会議から引き継がれているキリスト教の使命に対する考え方を、この文書を通しても確認しておくことが大切だと思います。
思い起こさせる「ケリュグマ神学」
筆者が注目するのは、この勧告で「ケリュグマ」という言葉が積極的に使われていることです。「ケリュグマ」はケリュッソー(告げ知らせる)という動詞から来るギリシア語の名詞で、新約聖書では、福音を告げ知らせるという意味で多用され、神学用語としては、根源的な福音告知を指しています。福音宣教という原点・核心を思い起こさせようとした20世紀前半からの、とくにドイツ語圏の神学でよく使われました。その意味で、この用語を見るだけでも、使徒的勧告『福音の喜び』は、現代神学における福音宣教論の文脈に立脚していることが感じられます。

ヨゼフ・アンドレアス・ユングマン
実は、20世紀の前半に、この用語でその立場が表現された「ケリュグマ神学」または「宣教神学」というものがありました。その立場を代表するとされる神学者がオーストリアのイエズス会司祭ヨゼフ・アンドレアス・ユングマン(Josef Andreas Jungmann, 生没年1889~1975)です。どちらかというと典礼学者として有名な人です。日本でも、『ミサ』(福地幹男訳、オリエンス宗教研究所、1992年刊)、『古代キリスト教典礼史』(拙訳、平凡社、1997年刊)が訳されています。
しかし、ユングマンの思想家としての特色がもっともよく表れているのは、むしろ福音宣教論の著書『福音と現代の宣教』(1936年)というものでした。今から思えば、この本の意義は、それまであまりカトリック神学の世界では多用されていなかった「福音」という言葉をクローズアップしたことでした。しかも、そこで使われているのは、ドイツ語のフローボートシャフト(Frohbotschaft)で、文字通りには、「喜びのメッセージ」です。この著作の生まれた背景は、第1世界大戦後、司祭になった著者が、教会での司牧体験を通して、伝統的なキリスト教生活のあり方に限界があると考えるようになったことがきっかけでした。そこでの気づきは、たとえば、次のように語られています:
……
(そうなると信者の意志に)逆らって果たされたような義務は、必然的に、次のような問題を提起するように迫る。すなわち、何のために、我々は、そもそも教会を必要としているのか? いったい教会がないと、人はキリスト者でもいられなくなるのか? 人は、自由な本性に従って、穏やかな心の内奥において祈ることができないのか? なぜ、日曜日、宗教的束縛にお構いなしに、早朝から田舎や山々に行ってはいけないのか?
一方で伝統と義務感に縛られたような信仰生活観、他方で現代化しつつある社会に生きる普通の生活感覚との間の乖離、遊離といった状況を顧みて、ユングマンは、キリスト教の教えの根源は「福音」であること、神からの喜びのメッセージにあることに気付かせようと努めていました。「掟」のキリスト教から「福音」のキリスト教への転換、この課題が、このあたりから意識化されるようになっています。
第2バチカン公会議の時代になると、このような特別な神学的立場を表す「ケリュグマ神学」や「宣教神学」という呼び名は使われなくなります。といっても、この神学的立場が消滅したわけではありません。むしろ、普遍化され、全面化されたといっても良いと思われます。まさにこの公会議が、神学が本来、福音宣教の神学であることを示したからです。
1000年の課題へ
このような20世紀神学の歩みを見てみると、『福音の喜び』は、第1次世界大戦以後のさまざまなキリスト教刷新の潮流のど真ん中にある関心事やモチーフにしっかりと結びついています。逆に、あの時代から気付かれていた教会の体質が、今なお欧米の教会には強く根付いたままであることも思わされます。
このような100年規模の振り返りを進めている折しも、教皇フランシスコが、100年前の前任者、教皇ベネディクト15世(在位年1914~1922)の世界宣教に関する使徒的書簡『マクシムム・イルド』(1919年発表)から100周年を記念して、今年の10月を「福音宣教のための特別月間」として主題化し、宣教への意識化を喚起しています。ユングマンをはじめ、あの時代の神学者の努力を大きな展望から顧みたくなります。そうすると、この勧告のメッセージの意義はもっと輝いてくるでしょう。
では、わたしたちはそれをどのように受けとめたらよいでしょうか。日本社会にある者として、多少とも教会にかかわるものとして。福音宣教はもちろんキリストから始まる2000年来の使命です。今、3000年期に突入したばかりの世界を見据えて、100年どころか1000年の規模で、福音と宣教のあり方を、考えていってよい時であるのでしょう。教皇フランシスコの来日を、そのきっかけにもしていきたいと思います。