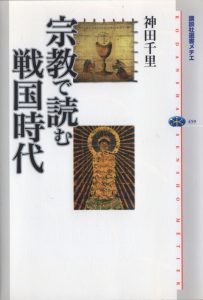石井祥裕
所属教会で歴史の学習会を実施している。その中で教会書的に知っていた「島原の乱」に関して、研究が目覚ましい変貌をとげていることを知った(書籍紹介参照)。大きな視野で語ってくれる著者たちから示唆を受けて、目を開かれるところは多いが、島原天草一揆として今は呼ばれるこの事件の全貌も意味もなお捉えがたい。専門の歴史家ではないので、研究者の示唆に頼るしかないが、しかし、それでも、歴史認識を刺激してくるいくつかのポイントがある。
この一揆の主導者たちの意図においては、信仰運動として、宗教運動として、徳川幕府の迫害・禁教政策に抵抗して起こしたものという面が確かにあった。その場合、宣教師の指導がなくなった信徒だけの集団としてのある種の信仰の変質の予兆もあったようだ。同時に、かつての信徒組織(コンフラリア)のきずなの存続という面もある。キリシタン史の転換期の到来である。もちろん圧政下での生活の困窮が動機となった参加者もいた。一揆集団は混成集団で、雑多な人々がいたことは矢文の史料も物語る。その人々を統合するためにも、主導者たちには宗教的(キリシタン的)理念を強調していったようである。そこにはキリシタン宣教黄金期の記憶も投影されたことだろう。キリシタン宣教師と信徒が活躍していた時代が壮絶な終わりに向かっていく。そこには信仰の苦悩と同時に哀しさが漂う。
一揆集団は、客観的には混成体だったかもしれないが、真実の信仰心から参加していた者もいたことはたしかである。矢文史料の一つにみられる「宗門さえお構いなくしていただければいうことはありません」という声。また混成集団をまとめるために腐心した一揆主導者の意識を伝える『四郎法度書』にある「互いを大切に思って意見を交わすべきである。城内の者は、後世までも友達なのだから」という言葉も、原城に籠もった集団の中にある人々の意識の一端を示す。「大切」とか「友達」という言葉の用法はとても近代である。幕藩体制から敵視された原城内の人々には意識や動機の多様性も含めて近代性が感じられる。
幕府のキリシタン弾圧は、この事件後にも一区切りを迎える。1639年のペトロ岐部の処刑もその局面でのことだ。宣教師の時代が終わる。宣教師自身の棄教(転びバテレン)が見られるのもその時期。遠藤周作が『沈黙』で対象とする時代である。キリシタン史は潜伏期に向かう。そうした、キリシタンの活動時代から潜伏時代への転機、日本宗教史の室町戦国時代史から徳川時代史への転機という意味では、この島原天草一揆の位置はとても大きい。
この事件は、それがどう取り締まられ、どう鎮圧されたかのプロセスにも興味を抱かせる。事件発生からどのような連絡系統で江戸幕府に伝わり、またどのような指揮系統で鎮圧が実行されたのか。ここには軍事体制としての幕藩体制の確立の度合いが試されている感も強い。西南諸藩の大名の原城攻撃の布陣図は、2万人ほど(と最近は思われている)の困窮農民たちを取り締まろうとするには大きすぎる規模だ。実際総攻撃時の虐殺も、幕府統治の圧力のほうをより大きく感じていての所業だったのではないか。
混成集団といわれた人々の思いは、人骨や十字架やメダイ、ロザリオなどの遺物の中にその断片を遺している。彼らが求めたものは、信仰の歴史の「あす」に実現したのだろうか。幕藩体制が近代国家への第一歩であったとするなら、この事件を経験した統治者は、その後、民衆やキリシタンに対してどのように臨んでいっただろうか(浦上信徒迫害事件を思い起こそう)。戦後が日本キリスト教史の「きょう」だとすれば、明治以降~戦前はいわば「きのう」。そして徳川時代は「おととい」になる。こう考えると、島原天草一揆はその「おととい」の始まりである。日本の国もキリスト教も道半ばの大きな事件であり、多くの犠牲であったのだ。民衆史においても、キリスト教史においても、日本の国の歴史においても、この事件にもっと関心を向け、語り合ってよいのではないだろうか。
(典礼神学者・実践神学者)