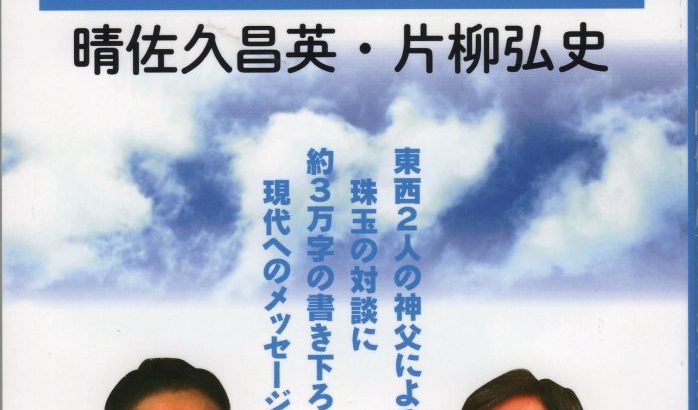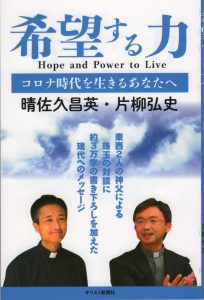石井祥裕
今年、新型コロナウイルス問題が発生して、教会で前代未聞のミサ非公開という措置がとられて以来、さまざまな論議や知識啓発、情報提供が続いています。このAMORでも、テレビ番組や書籍など、顕著に目立つものを少しずつ追っていますが、今回はカトリック教会の中で動き始めている新しい思索に目を向けてきます。
この状況に突入してから筆者がカトリック教会発行物の中で注目しているのは、『カトリック新聞』の月一回連載、イエズス会司祭・川村信三神父の『カトリック時代エッセー』と、ドン・ボスコ社発行『カトリック生活』誌にある竹下節子氏の連載『カトリック・サプリ』のここ半年ほどの記事です。それらを通して、「教会」「ミサ」「祈り」「いのち」に関して、今までにない情報や指摘がしたたりおちてきています。世界的危機の共体験の中から、新しい教会論、新しい神学、生きていくための新しい知恵が紡ぎ出されているような予感と期待が抱かされます。もちろん、それは傍観対象ではありえません。だれもが、そこで一緒に考え悩むべき共通のステージです。なんでも読み過ごすのではなく、心でとどめ、反芻し、共有できるものを育んでいくことが必要でしょう。
そんな思いでいたところ、刺激的なのに等身大のトーンで響いてくる近刊に出会いました。晴佐久昌英・片柳弘史『希望する力 コロナ時代を生きるあなたへ』(キリスト新聞社 2020年9月15日発行 全123ページ)です。発信力旺盛な二人のカトリック司祭……広島教区での司牧しているイエズス会司祭の片柳弘史神父と、カトリック東京教区司祭の晴佐久昌英神父による、対談とその後の書き下ろし原稿が編まれた書です。その中から、この時勢と自分なりの探求を前向きに励ましてくれるような光ることばに出会いました。いろいろな気づきに満ちていて、それらすべてに対する感想を記すときりがないので、たぶん広く共有できる考えの芽生えのようなものを、ここできっちり受けとめておきたいと思います。
ミサが非公開になるという、ショッキングな時期となった今年の3月から6月半ばまでのカトリック教会。ちょうど四旬節~聖週間~復活節でした。ミサに来ることが至上の務めと意識され、ミサに参加するために集まることが至上の価値と思われていたなかで、一人ひとりが外出自粛や巣籠もりをし、自宅での祈りを求められる現実、しかし、その中でミサや祈りのもつ、独特な性質が気づかれるようになっています。
片柳神父はこのことについて次のように語っています。
「対談でも触れましたが、私は『祈りこそ究極のテレワーク』だと考えています。祈ることによって、私たちは物理的な距離やあらゆる障壁を越え、神の前で一つに集うことができるのです。相手の心に深く寄り添い、相手の傷を愛のぬくもりで包み込むこと。……〈中略〉……祈りの中でできることは無限にあります。一カ所に集うことが出来なくても、私たちは一つの教会として心を一つにすることができるのです」
(79ページ)
これは、川村神父も上述の連載の中で少し触れている見方でした。ここでは、祈りすべてのことが言われていますが、とくに信徒にとって教会の祈りのもつ力をもっとも典型的に味わい、支えられるところの主日のミサのことを思うと、まさしく「テレワーク」という言葉こそがその性質や様相をよくとらえるものであるという気がしてきます。「テレ」とはギリシア語で「遠く離れた」を意味する語で、これがテレビジョンやテレグラムのもとになっています。英語の「リモート」は「レモートゥス」というラテン語から来ていて、やはり同じ意味です。
「物理的な距離やあらゆる障壁」があることで人間的、社会的な意味で集まれていないことを、祈りは越えていくものだということです。それは神の前での集いを実現するものであるということす。祈りが究極のテレワークであること、リモートワークであるということは、典礼の祈りが具体的に考えさせてくれます。ミサには共同祈願というものがあります。また奉献文の中でとりつぎの祈りというものがあります。これは、一つの共同体でささげられるミサの中でも、他の共同体、遠く離れたところにいるさまざまな人のことを思い、そのために祈る祈りです。
あるいは自分たちのことを顧み、憶えていてほしい、わたしたちのために祈りをもって支えてほしいと、すでに地上にはいない聖人たちに頼む祈りもあります。「われらのために祈りたまえ~」です。現代の典礼によって育ってきた人間としていえるのは、こうした祈りを通して、その一つの共同体家族だけではない、全世界を包括する無限に広いつながりの中に自分はあるという事実と真実があるということです。「物理的な今ここ」を超えた集いの次元(「霊的」とこれをいうべきでしょうか)に招かれていくという不思議な経験です。
このような祈りは、たとえミサの祈りを(印刷媒体を活用しつつ)家で、一人だけで祈ったとしても、心の中で祈ったとしても、やはり導かれていくものです。実際のミサの集いの経験が基盤になるとはいえ、その祈りの真骨頂ともいえる「神の前での一つになること」は、どこにどのようにいても、一人ひとりの前に開かれています。非公開でミサに集えなかった経験は、逆説的に「神の前で集う」こととしての祈りの真実に気づかせてくれているのかもしれません。いや、きっとそうなのでしょう。祈りには、究極のテレワークの実質を守り続ける力がある……そんな再発見と希望ある励ましが含まれる、片柳神父の指摘ではないかと思い、ぜひ共有し展開していきたいと感じています。
一方、晴佐久神父の文章は、硬質な考察とピリリとした提言の文章になっています。個性的な表現、はっと思わせることばが目白押しで、現状に鋭く切り込んでいきます。「恩寵のウイルス」としての新型コロナウイルス、教会が陥っている「自分の教会ファースト」、「隠れ原理主義」……カトリックの枠に納まらず、諸教会、諸宗教の指導者とも交わり、なによりも「福音家族」の実践に裏打ちされた発言は、実践神学としての神学を力強く切り開いていくようです。
一介の信徒には、まだ消化できないところもあるなか、すぐに共有できた実感ある言葉が「新普遍主義」でした。パンデミック状況で、だれもが感染すると同時に感染させる者になりうる状況に響く概念だからです。
「人類がこれほどセーフティネットに関する当事者意識を持たされた、そのことこそがコロナの時代の最大の特徴だろうと思う」(106-107ページ)
「救いの普遍性を宣言し続けてきたつもりの一司祭が、……自らの普遍感覚を研ぎ澄まさざるを得なくなっているというこの状況は、まさに恩寵のうちにあるとしか言いようがない」(92ページ)
「新普遍主義とは、つまりは『普遍主義に奉仕する普遍主義』なのであって、それこそが『すべての人に仕える者』(マルコ9・35)になるということだろう」
抽象的に響くかもしれませんが、「隠れ原理主義」と対比されていることがわかると、それはどちらも極めて現実的で、一方で現実批判力、他方で大きな実践駆動力をもっている概念だとわかります。あとは、実際に本書をお読みください。短い中でも第2バチカン公会議の評価、そして教皇フランシスコの最近のメッセージの受けとめ方にもつながる、さまざまな思索と考察の種が蒔かれています。今後の(多くの人による)思索と連帯の広がりに期待していきたいと考えます。
(AMOR編集部)