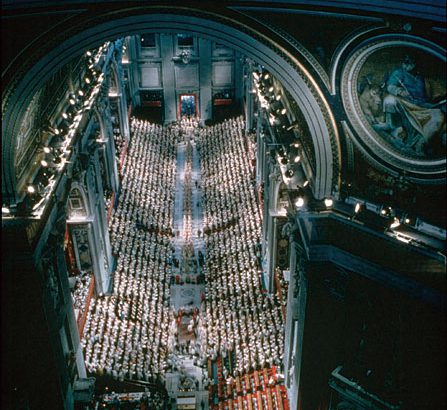前々回紹介した『トリエント――公会議で何が起こったか?』の著者オマリーが2008年に発表した第2バチカン公会議についての書を紹介する。日本では、司教団によって『第二バチカン公会議公文書』の改訂公式訳が2013年に出ており、この公会議の経緯や意義についての新しい視点が求められるところである。その刺激の一つにしたい:
ジョン・W・オマリー著『第2バチカン公会議で起こったのは何か』
John W. O’Malley, What Happened at Vatican II, Cambridge, Massachusetts. : The Belknap Press of Harvard University Press, 2008,xi+380 Pages.
第2バチカン公会議の経過については、1965年から2006年にかけて各国語に翻訳されて出版されたジュセッペ・アルベリゴの『第2ヴァティカン公会議史』をはじめ、日本語に翻訳された小史を含めて、いく冊の本がすでにある。カール・ラーナー(生没年1904〜1984)は、公会議後数十年経た時点を「教会の冬の時代」と呼んだが、半世紀を経た今日、この公会議で意図されたものは何であったかをあらためて考える必要がある時期が来ているようである。
公会議は教皇ヨハネ23世(在位年1958〜1963)が開催のスローガンとしてアジョルナメント(教会の現代化)をあげたが、今日では公会議のルスースマン(〔仏〕Ressourcement =源泉回帰)が教会当局によってスローガンとして折に触れて強調される時代となっている。ルスースマンとは手っ取り早く言えばリサイクルのことである。確かに、ルスースマンは本書の著者オマリーがあげる三つ、アジョルナメント(現代化)、デヴェロプメント(未来志向)とともに過去との連結を保証するものであるが、今日盛んに使われる意味では、第2バチカン公会議から純正な要素をリサイクルして再解釈するということ、それがスローガンになっているのである。
【さらに読む】
イエズス会司祭である教会史家オマリーは、教会史における幾多の公会議を歴史的に概観し、近代、特に、「長かった19世紀」の背景をふり返ったあと、4会期にわたった第2バチカン公会議の成果を分析している。そして個々の論点を超えて、この公会議が教会のために何を達成し、将来にどのような方向を示しているかを語ろうとしている。
「長かった19世紀」は、間にレオ13世(在位年1878〜1903)のやや開放的な時期もあったが、グレゴリウス16世(在位年1831〜1846)の治世に始まる、近代主義に包囲された教会のカルチャーから理解されなければならない。イヴ・コンガール(生没年1904〜1995)が日記で記しているように、冷戦時代においてこのカルチャーのゆえに、教皇庁は、イタリア国内での共産主義政府樹立によるバチカン包囲への恐怖感によって、世俗世界への対立姿勢を強めていた。だから「長かった19世紀」は、20世紀が後半に入りまもなくの第2バチカン公会議開催直前まで続いたと言える。その姿勢は、数々の近代主義的傾向の排斥に見られるものである。
著者は、教会典礼用語としてのラテン語がすべてを統括する普遍主義を象徴していたことを指摘する。ハンス・キュング(生年1928)は自叙伝の中で、公会議の最初の文書がもっと重要であるはずのテーマでなく、典礼についての憲章であったことに対して滑稽感ともに幻滅感をもったと回想しているが、著者は『典礼憲章』の採択は、公会議において重要な、象徴的出来事として受け止めている。それは、以後、公会議で「起こったこと」、特に19世紀に高揚した教会の中央集権的メンタリティとの決別を象徴しているからである。
ヨハネ23世の「アジョルナメント」は、「現代世界を恐れるな」ということであった。当時もっぱら進歩的若き神学者として評価が高かったラッツィンガー(生年1927。教皇ベネディクト16世としての在位年2005〜2013)は、『第二バチカン公会議をふり返って』(原著1966年、再版2009年)という小著の結論として、「教会は喜ばしい時にも、悲しむべき状況でも、心の単純な人々の信仰に生きている。……彼らこそが新約の希望の灯火を後世に伝えるのである」と述べている。しかし「単純な人々の信仰」には、たしかに信徒のローマと教皇に対する強い愛着がつきものであるが、ローマ中枢の聖職者主義的カルチャーとは無縁であったのではなかろうか。オマリーの説明をたどれば、公会議の結末をなす重要な文書『現代世界憲章』は『典礼憲章』から出発したうねりの帰着、大団円であったのである。
『現代世界憲章』は、もっとも激しい議論を経て出来上がった文書であった。ルター派の義認論的人間観を意識したドイツ司教団は、フランス語圏の顧問が作成した原案に賛成しなかった。おそらくその背後には、よく言われるようにアウグスティヌスから出発するラッツィンガーの考え方があったのかもしれない。彼は公会議閉幕の典礼が「バロック的」雰囲気を醸し出したとコメントし、以下のように述べている。「しかし、公会議後の仕事はもっと深いところに及ぶ。ローマで起こったことは与えられた使命の公文書化にすぎない。その遂行が今や始まるのである」。つまり、それらの文書が現実に教会の制度に受肉されていくかどうかが問題なのだということであろう。
近代世界は、技術の次元にとどまるものではない。重要なのはそこに生きる人々である。著者によると、第2バチカン公会議は、外面的様相においても内面的姿勢においても、第1バチカン公会議とはまったく異なる教会の姿を夢想する一種のユートピアを掲げた。第2バチカン公会議で起こったのは、長すぎた「19世紀」の影と決別し、近代世界に対して識別の眼差しをもって積極的に関わらなければならないと考えた多数の司教たちの考え方が優位に立ったということである。しかし『教会憲章』で打ち出された司教の「共同性=コレジアリタス」の原理は、世界代表司教会議(シノドス)の制度化へと矮小化され、結果的にはそれを超えることなくとどまり、一極集中型の制度自体を本質的に変えるためにはさほどの影響を与えなかった。
オマリーの冷徹な歴史眼は、この公会議がそれまでと同様の権力中枢で開かれ、その名前(バチカン)を戴き、その組織の助けによらなければ成果を上げることができなかったという矛盾を内包していた事実を見抜いている。保守派は、かつて国務長官だったパウロ6世の後ろ盾によって最後まで結束を保っていた。ハンス・キュンクは、保守派の頭目オッタヴィアーニ(生没年1890〜1979)枢機卿が公会議閉幕時に「我々は勝利した」と喝破した、と記している。その後、改革を推進しようとするならば、さらに保守派の助けによって行わなければならないというジレンマが第2バチカン公会議の行く手にはあったというのである。
(高柳俊一/英文学者)