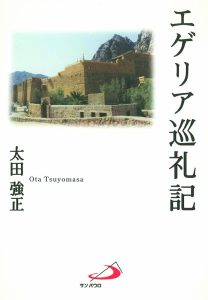石川雄一(教会史家)
古代末期に著されたエゲリアの『聖地巡礼記』から今日のSNSにいたるまで、古今東西の巡礼者たちは巡礼の体験を文字にして人々に伝えてきました。その中には『エゲリア巡礼記』のように邦訳があるほど有名なものもあれば、人々にほとんど知られていないものもあります。そんな数多ある巡礼記の中から、今回はヴァティカン図書館に所蔵されている写本(Vat.lat.4951)に書かれている一つの物語を脚色して紹介します[1]。
物語に入る前に時代背景を簡単に説明しましょう。物語の冒頭に、大司教ランフランクスの死(morte Lanfranci archiepiscopi)により教会が荒廃(desolata)した若ウィリアム王(Rex Wilelmus iunior)の時代と書かれているので、11世紀末の英国が舞台となっていることがわかります。若ウィリアム王とはウィリアム2世として知られている英国王で、征服王ウィリアム1世の息子で、1087年から1100年まで王位にありました。
父のウィリアム1世は、元はフランスのノルマンディーの公爵でしたが、証聖王エドワードの死により英国のアングロ=サクソン朝が断絶するとイングランドに攻め込み、ノルマン朝を開いた英国史でも特に重要な人物です。このウィリアム1世による英国征服、いわゆるノルマン・コンクェストにより英国の支配者層はフランス語を話すノルマン系貴族となり、それ以前のアングロ=サクソン人たちとの間に軋轢が生じるようになった状況については、ウォルター・スコット卿の歴史小説『アイヴァンホー』などで触れられた方も多いのではないでしょうか。
いずれにしましても、ノルマン・コンクェストにより大陸から多くの人々がブリテン島に渡ったのですが、カンタベリ大司教となるランフランクスもその一人でした。ノルマンディーで教鞭をとっていたランフランクスはウィリアム1世から信頼された聖職者であり、1070年にカンタベリ大司教となると教会改革を推進しました。そのランフランクスが没したのは1089年のことでしたが、種々の政治的事由から後継者はしばらく選ばれませんでした。
つまり、教会の荒廃状態とはこの時代を指していると考えられるため、この物語はランフランクスが没した1089年から後継者が選ばれる1093年の間の出来事であると推定できます。なお、ランフランクスの後継者としてカンタベリ大司教となったのは、彼の弟子であり、後に「スコラ学の父」と呼ばれるアンセルムスでした。
本物語の主人公となる修道士ジョセフ(Ioseph)は、こうした激動の時代の英国からエルサレムへ巡礼の旅に出ます。11世紀の西ヨーロッパでは、様々な理由から巡礼が人気を博していました。例えば、1064年から1065年にかけてマインツ大司教を筆頭とした約7000人ものドイツ人からなる大巡礼団がエルサレムに詣でたと伝えられています。こうした巡礼熱の高まりが、11世紀末からの十字軍につながるのですがそれはまた別のお話。それでは、ある写本に書かれた修道士ジョセフの物語を見ていきましょう。
* * *
偉大な征服王が没し、清廉潔白な大司教も死んだ時代。若王は教会の財産を我が物とし、新たな大司教も選ばれることなく、英国は混沌とした世に突入していた。こうした末の世にあって、ジョセフという名の修道士は、聖地エルサレムに詣で、人々の救いのため、そして英国のために祈ることを決意した。
欧州の辺境に位置するブリテン島からの長旅の末に着いたエルサレム、そこは、主キリストが受難された地、使徒たちが人々に福音を告げ知らせた地、聖書の舞台となった地に他ならなかった。ジョセフの魂は欣喜雀躍した。「『主の家に行こう』と人々が言ったとき、私は喜んだ。エルサレムよ、あなたの城門の中に、私たちの足は立っていた。都として建てられ、家々の連なるエルサレムよ。そこへ、もろもろの部族、主の部族は上った、イスラエルの定めとして、主の名に感謝するために。」(詩122・1-4、聖書協会共同訳)
聖地巡礼を終えたジョセフは、他の巡礼者と共に故国へ帰ろうとしたが、彼の「祈りたい」という心の叫びが止むことはなかった。ジョセフと同じ思いを抱いている巡礼者たちも何人かいたが、その中の一人がこんな話をしてくれた。
「ビザンツ帝国の帝都コンスタンティノポリスには、この世のどことも、それこそローマとも比べられないほどたくさんの聖遺物があるって噂されてるぜ。どうせ帰り道だし、一緒に聖遺物を見に行かないか」
聖地で祈るのと同様、いにしえの東方帝国に隠された聖遺物を観る機会は一生に一度あるかないかである。この機を逃す手はない、そう考えたジョセフは何人かの同志と共に、西ヨーロッパへ帰る巡礼者の群れから抜けて、コンスタンティノポリスへ向かった。
キリスト教を公認したコンスタンティノス大帝に由来する大都市コンスタンティノポリスは、西欧のどんな都市よりも大きく華やかであった。古代ギリシアとローマ帝国の遺産を伝えるビザンツ帝国の首都は、西欧人にとって“オリエンタル”な謎と魅力に満ちた蠱惑的な場所だった。世界中の色々な場所から来た多様な人々が街を行きかい、色々な言語が聞こえてきたが、その中にはジョセフにとって耳なじみのある言葉もあった。「同郷人だ!」ジョセフが振り向くと、そこには重装備に身を固めた皇帝の親衛隊がいた。
ビザンツ帝国では100年もの間、ノルマン系の外国人が皇帝の親衛隊を務めてきた。陰謀の多いビザンツ帝国では、腹黒い同胞よりも外国人の方が信頼できたのである。ノルマン人といえば、最近では南イタリアを征服したという噂があるほど勢いのある人々であり、事実、ジョセフの出身地イングランドでもノルマン人の王朝が開かれていた。ノルマン人の国際的な活躍が、遠い異国の地でジョセフに新しい友人を用意してくれたのである。
「修道士さんよ、お前さんは何しにコンスタンティノポリスへ来たんだい」
「聖地巡礼の帰りでね。ここには沢山の聖遺物があるって聞いたんだけど、ぜひともそれを一目見たくて」
「そうかい。お前さんが言ってるのは皇帝陛下のコレクションのことだね。普段は見られないんだが、ここで会ったのも何かの縁だ。俺は皇帝の警護をしてるから、特別に取り計らってやるよ」
神の導きか、ジョセフは偶然会った同郷人の取次により、一般には解放されていない皇帝の聖遺物コレクションを見せてもらえることになった。親衛隊が紹介してくれた通訳に皇帝の私的礼拝堂へ連れていってもらったジョセフは、そこに収蔵されている数々の聖遺物を恭しく見学していったが、中でも彼の関心を引いたのは、ある聖遺骨であった。
「そちらが気になりますか。それは聖アンデレ様の遺骨でございます」
聖アンデレ様! 十二使徒の一人にして、聖ペトロの兄弟! そういえば聞いたことがある。聖アンデレ様はギリシアで宣教し、そこでX型の十字架にかけられて殉教された、と。また、こうも聞いたことがある。コンスタンティノポリスにキリスト教を伝えたのは、聖アンデレ様の弟子の聖スタキス様だ、と。聖スタキス様は初代コンスタンティノポリス司教になられ、だからコンスタンティノポリスの人々は聖アンデレ様を大切に崇敬しているのだ。その熱心さから、まだ昔のローマ帝国があった時代、コンスタンティノポリスの人々は、ギリシアから聖アンデレ様の御遺体を持ってきたのだった。それを今、私はこの目で見ている!
ジョセフは筆舌に尽くしがたい感動を覚えた。気づいた時には、彼は地面にひれ伏して、敬愛する使徒の聖遺物に熱烈な祈りをささげていた。そして、「もし神のみ旨に叶うのであれば、この最も尊い聖遺物を荒廃する故国に持って帰りたい!」と口に出して祈っていた。
皇帝の個人的な聖遺物を欲しがるとは、何ということだろうか。下手したら、この外国人の修道士は無礼者として切り捨てられていてもおかしくなかった。実際、ジョセフの口をついて出た危険な願いは、聖遺物を守る衛兵の耳にも入っていたが、幸い、彼にはジョセフの話す言葉が理解できなかった。
「なんて言ったんだ」
ギリシア語話者の傭兵は、ジョセフを案内してきた通訳に聞いた。ジョセフの言葉をそのまま伝えてしまっては、この修道士のみならず、自分の身まで危険だ。そう考えた通訳はあたふたしながらジョセフに、どうしたものかと相談した。するとジョゼフは、驚くべきことに、そのまま翻訳するように通訳に頼んできた。恐る恐る通訳がジョセフの不躾な願いを衛兵に伝えると、さらに驚くべき返事が返ってきた。
「ほう、じゃあよ、もし誰かがその願いを現実のものにできるってんなら、いくら出せるんだい」
なんと、皇帝の最も大切なコレクションを守る衛兵がワイロを要求してきたのだ。
「私は長い巡礼の帰路にあるため、あまり金銭に余裕がなく……。それに、これから先の旅路も長いですし……。ただ、仮に誰かが私の願いを叶えてくれるのであれば、その人に対してある程度のお礼を出す余裕くらいはありそうです」
負けじと修道士も値切り交渉を始めた。
「そもそも聖遺物は蒐集品として展示されるものではなく、人々から崇敬されるべきものです。私が英国へ持ち帰った後には、必ず人々の信心の的となるような場所に安置されることを約束しましょう。そういえば、最近、聖アンデレ様に捧げられた教会ができたんですよ」
「そうかい、とりあえず一旦宿屋に帰ってよく考えな。後で、この通訳を介して、細かいことは練っていこうぜ。こういう“仕事”はよ、慎重にいかねぇとな……」
果たしてジョゼフは、聖アンデレの聖遺物を英国にもって帰れるのでしょうか!?
* * *
と、映画の予告編のような終わり方になってしまいましたが、これは何も私が翻訳や脚色に疲れたから誤魔化しているのではなく、写本がここで終わってしまっているからなのです。残念ながら私たちは、修道士ジョセフがワイロを払って聖アンデレの聖遺骨を手に入れられたのかどうか、気になる物語の結末を知ることができません。
ですが、聖アンデレの聖遺骨は、西欧人がコンスタンティノポリスを征服した第四次十字軍の後に奪われているため、ジョセフの望みが叶ったとは考えにくいでしょう。なお、西欧人に奪われた聖アンデレの聖遺骨は、20世紀になってようやくコンスタンティノポリスの教会に返還されました。
【注】
[1] Charles H. Haskins, “A Canterbury Monk at Constantinople, c. 1090,” The English Historical Review, Vol. 25, No. 98, Oxford University Press, Oxford, 1910, pp. 293-295.参照