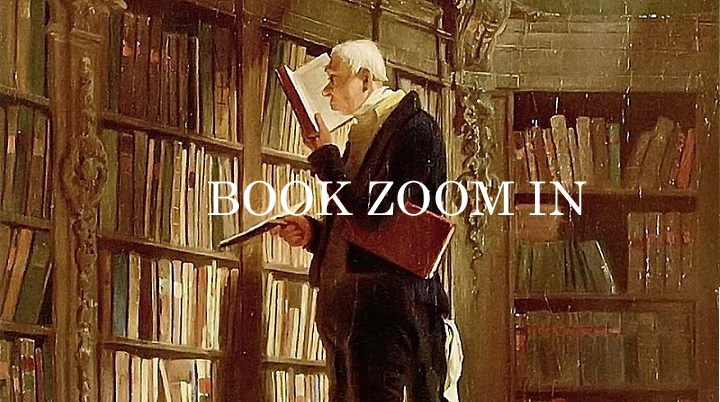池上健一郎『ハイドン』、音楽之友社、2023年、2300円+税
石川雄一 (教会史家)
音楽之友社から出版されている「作曲家◎人と作品」は、これまでバッハやモーツァルト、リスト、武満徹に至るまで古今東西の作曲家の生涯と作品を紹介してきた、音楽好きには必携のシリーズです。その「作曲家◎人と作品」シリーズが遂にフランツ・ヨーゼフ・ハイドンを扱うこととなりました。「作曲家◎人と作品」を愛読してきたうえに、大作曲家の中ではハイドンが最も好きな筆者からすると嬉しい限りです。
ところで、皆さんはハイドンについてどのようなイメージをお持ちでしょうか。音楽の教科書にも載っているし、肖像画も音楽室に飾られている。名前も聞いたことはあるし、曲もいくつか耳にしたことがある。だけど、詳しいことはあまり知らない……。ハイドンとは、一般的にはこのようなに受け取られている大作曲家ではないでしょうか。
実際、ハイドンの音楽は耳心地の良い調和のとれた音楽ですが、それゆえにロマン派音楽のような激しさや感情への訴えは乏しいといえるでしょう。また、哲学的な深みにも欠け、人類普遍の芸術というよりも時代性に束縛された、貴族文化が生んだ最後の“古典”というような批判もあるでしょう。さらに彼は、映画化もされているモーツァルトやショパンのような波乱万丈の人生を送ったわけでもないので、どうもパッとしないのです。今回紹介する「作曲家◎人と作品」の『ハイドン』は、彼に対する上記のような固定観念(偏見といってもいいかもしれません)を打破するような伝記となっています。「ハイドンの精神で書くこと」(237頁)が意識された本書は、その意図通り、読み心地の良い軽妙な筆致で書かれており、ハイドンに興味がある人も、そうでない人も一度読んでみてほしい本です。

ここでハイドンの生涯について簡単に紹介しておきましょう。1732年にオーストリアで生まれたフランツ・ヨーゼフ・ハイドンは、その美声を評価されて聖シュテファン大聖堂の少年聖歌隊に加わり、音楽活動を始めました。声変わりを迎えたため少年聖歌隊で歌えなくなったハイドンは、音楽指導やミサでの楽器演奏で糊口をしのぎつつ、音楽理論を学んでいきました。こうして地道に下積みをしていったハイドンは、人脈を広げていき、フォン・フュルステンベルク男爵やモルツィン伯爵といった貴族から仕事をもらえるようになります。なお、この時期にハイドンは伝承されている最古の作品である《ミサ・ブレヴィス》を作曲しています。
1761年、29歳のハイドンは、ハンガリーの貴族エステルハージ家の侯爵パウル・アントンに宮廷副楽長として雇用されます。以降、ハイドンは1809年に77歳の長寿を全うするまで、エステルハージ家に仕えることとなります。優雅なオーストリアの帝都ヴィーンを離れ、ハンガリーの田舎にあるエステルハージ家の離宮エステルハーザに住むようになったハイドンは、そこで団員をまとめつつ、侯爵のために曲を書き続けました。中間管理職の雇われ作曲家ハイドンは、そこで孤独を感じつつ、持ち前の勤勉さと几帳面さ、そして多少のユーモアと商魂で規則正しい人生を送ることとなります。
おそらく、これがハイドンの人生が大衆受けしない理由でしょう。ハイドンは各地を転々と旅もしなければ、大病を患って苦悶もせず、激しい恋愛や宿敵との対立もありませんでした。むしろ、宮仕えのハイドンは(英国旅行を除く)人生の大半をオーストリア(ハンガリー)で過ごし、規則正しい健康的な生活により病気とは無縁であり、礼儀正しく人付き合いも上手かったため多くの人に好かれ尊敬されていました。そんな一般的には「つまらない」と思われるような彼の人生ですが、「手堅い生き方を好んだひとりの人間が、なぜ生涯にわたって豊かな創造の泉をその内に持ち続けることができたのか」(231頁)という著者の問いはとても興味深いのではないでしょうか。
専門家でない筆者がこの問いに何か言うのはおこがましいですが、個人的にはハイドンの信仰心が彼の作曲を支えたと思います。フリーメイソンと接触があったとはいえ、カトリック信仰を生涯保ち続けたハイドンは、楽譜の最初に「神の御名において」、最後に「神に賛美を」または「神に栄光」と記していました(150頁)。彼の現存する最初の作品はミサ曲ですし、最後の大作も《ハルモニーミサ》と呼ばれるミサ曲です。また、当時から今日に至るまでハイドンの傑作とされてきたのは、《スターバト・マーテル》、《十字架上のキリストの最後の七つの言葉》、そして《天地創造》という宗教曲でした。100を越える交響曲を作曲した宮廷音楽家であったハイドンは、同時に、深い信仰に支えられた宗教音楽家でもありました。この点も含め、本書を通じてハイドンの魅力に触れていただければ幸いです。