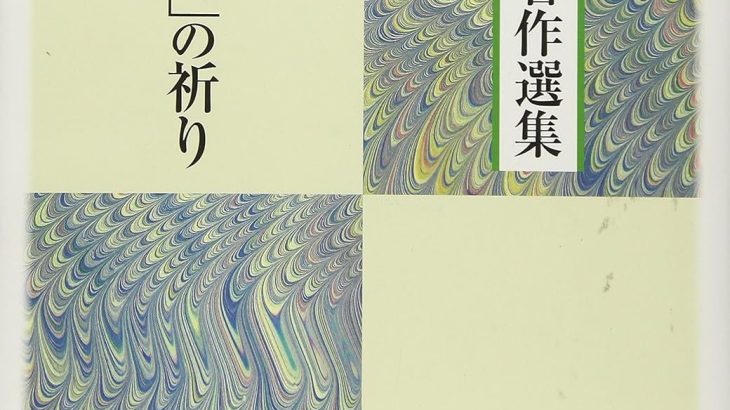山根息吹(東京大学大学院総合文化研究科学術研究員)
帰天十周年にあたって、日本文化とキリスト教という課題に生涯一貫して取り組んだ井上洋治神父の歩みを、東方キリスト教の霊性との出会いという視点から捉えていく。さらにその視点から、井上神父が求めた霊性と教皇フランシスコによる回勅『ラウダート・シ』との重なりを示すと共に、井上神父の霊性の継承者・伊藤幸史神父による「信州 風の家」における「自然の霊性」への新たな展開を紹介したい。
井上神父は、リジューのテレーズの『自叙伝』に導かれて受洗し、そのテレーズの霊性を自らも生きることを願い、カルメル会に入会するために1950年に渡仏する。しかし井上神父は、司祭養成のための神学を学ぶなかで日本人である自らの感性と西欧キリスト教との距離を痛切に自覚するようになるが、その葛藤に苦しんでいた時に、東方キリスト教の霊性と出会う。
カトリック教会は、東方正教会と最初の約1000年間の信仰の遺産を共有しているが、ラテン語への翻訳が限定的であったこともあって西方教会では、ギリシア語で思索した教父(Church Father)たちの霊性を十分には受容できていなかった。東方正教会はまさにこのギリシア教父たちの霊性を生き生きと継承しており、ジャン・ダニエルー、アンリ・ドゥ・リュバック、ハンス・フォン・バルタザールなど、20世紀を代表するカトリック神学者たちが、カトリック教会の刷新を求めてギリシア教父・東方神学の研究に取り組んでいくという大きな流れが存在した。その意味で、井上神父はそのような第二バチカン公会議前夜の空気にいち早く触れた日本人であったと言える。
東方キリスト教の霊性と出会った感動について井上神父は、著書『余白の旅』(『井上洋治著作選集第2巻』 日本キリスト教団出版局)で次のように語っているのである。
当時リールのカトリック大学で、たまたまレイモン・ヴァンクールの「東方神学」の講義に出席した私は、西方の神学とは非常に異なったアプローチを持つ東方キリスト教の考え方に深い心の共鳴を感じはじめていた。それは長い日本文化の歴史の流れのなかで生まれ育ってきた私の心の琴線にふれてくるものであった。
院長の特別な許可をもらって消灯後おそくまで、東方教会の神学者、ウラジミール・ロスキの『東方教会の神秘神学』をむさぼるように私は読みふけったものであった。
(77頁)
『余白の旅』で井上神父が特に「長い日本文化の歴史の流れのなかで生まれ育ってきた私の心の琴線にふれてくる」ものとして具体的に挙げる東方キリスト教の神学の考え方は、「否定神学」と「汎在神論」である。まず「否定神学」への着目に関しては、井上神父が当時司祭養成の過程で、新スコラ主義に基づいて神学命題を模範的に論証した教科書を丸暗記することを強いられていた時代状況を理解する必要がある。井上神父は「信仰の対象になるべきものさえ、やたら人間の理性で証明していこうといった姿勢」に苦しみ、「精神的には殆ど窒息寸前のような状態にあった」と回顧している(同書、54-55頁)。そのような中で井上神父は、「神は人間の理性にとっては「神聖なる暗闇」であって、決して概念によって表現しうるようなものではない」(同書、78頁)点を強調する東方キリスト教神学と出会い、強い共感を持つ。さらに井上神父は、否定神学的な神の捉え方は、「後に私のなかで、次第に東洋的な「無」という考え方に結び合わされていくことになる」と語っている(同書、78頁)。
さらに、『遺稿集「南無アッバ」の祈り』に収録されているエッセイ「私の血のなかに流れているもの」において井上神父は、神が「絶対他者としての超越神」であるだけでなく「すべてを包みこんでいてくださる神」であるという内在性を重視する東方キリスト教の霊性に学ぶことの重要性を次のように主張している。
キリスト教は決して汎神論ではないけれども、本質とはたらきを断絶する超越一神論ではなく、汎在神論(パンエンテイズム)と呼ばれるべきなのだ、ということを東方神学によって目覚めることが絶対に大切なことだと思われます。
(143‐4頁)
ここで井上神父がその重要性を強調する「汎在神論(パンエンテイズム)」(『岩波キリスト教辞典』では「万有内在神論」と訳されている)は、汎神論のように万物が神であると考えるのでは決してないが、神は超越者でありながら同時に万物に内在していると考える立場である。このような考えにおいて自然・被造世界は、人間が神に出会う場となり得るのであり、自然のなかに大いなるいのちや聖なる働きを感じる東洋的感性を否定することなく、キリスト者としての道を歩んでいけることになるのである。さらに『余白の旅』で井上神父は、このような東方神学が、あとになって「場」としての神理解へと自らの思考をかりたてていくものとなったと述べている点は、そのインカルチュレーション論を考える上で特筆すべきである(同書、79頁)。
実際に井上神父は、「人間理性にとって無としかとらええない「場」こそがまさに「キリストの体」なのだというのが、パウロをはじめとする原始キリスト教の信仰」であるのであれば、個を中心とした西欧的考え方よりも「「人と人との間」とか「場」とか「無」とかを基底にしている日本的なものの考え方の方がパウロの人間存在のとらえかたに近い」のではないかと論じている(同書、181頁)。このように東方キリスト教の霊性に学びながら、日本人としての自らの感性に対して誠実にキリストの道を生きようとする井上神父の模索は、福音への原点回帰という方向性を持つものでもあったという点を見落としてはならない。
ちなみに、井上神父のこうした思索から大きな影響を受けていた作家の遠藤周作は、『私にとって神とは』において「見直すべき東方教会」という小見出しで「東方教会の考え方を見直そうじゃないかというのがヨーロッパでもどんどん起こっています」という動向を指摘し、日本に根付くキリスト教の在り方を考える上でその宗教性に注目することの重要性を語っている(光文社文庫 125-6頁)。
以上に見てきたような「否定神学」や「汎在神論」と通じる発想は、井上神父が『余白の旅』の中で東方キリスト教の神学と重ね合わせる形で中世哲学研究の泰斗であるジルソンの『存在と本質』を取り上げているように(78頁)、カトリック神学の伝統においても確かに存在する。しかし井上神父が1950年代にローマで受けた神学カリキュラムにおいてはその重要性が強調されておらず、さらに司牧のレベルにおいてはかなり忘却されていた面が否めないように思われる。
2015年に出された回勅『ラウダート・シ』では教皇フランシスコが、「神と出会うということは、この世界から逃げ出すことでも、自然に対して背を向けることでもありません。このことは、とくに東方キリスト教の霊性において明らかです」(235)と語っており、井上神父が懸命に訴え続けてきた問題意識の重要性は、日本のカトリック教会でも今ようやく理解されはじめてきたという状況であるように思われる。
井上神父の後継者である伊藤幸史神父が、そこに集う人々が「自然との出会い」を体験することを通して「真の自己との出会い」さらには「神との出会い」へと導かれる場となることを願って創設した「信州 風の家」は、まさにそのような自然の霊性の具体的展開であると言える。
伊藤神父が語る「自然」の霊性の特徴は、時に自傷や依存症のような形をとる「自己否定感」という現代人が抱える「心の闇」に対する癒しを求める必死さである。つまり、現代人の「心の闇」に神の愛を届けるために必死になれば、「自然」に力をかしていただかなければならないというところにたどり着くという(伊藤幸史「風土・食(ふーど)といのち、その霊性―食と自然体験を通しての救い―」、『風(プネウマ)』106号)。実に、キリスト教文化内開花の試みは、現代人の「心の闇」の癒しに向かう、福音と日本的宗教性の協働という次元へと深まっていく必要があるに違いない。井上神父の思索の遺産は、まさにその方向に向かって展開されていく可能性に満ちた霊性なのである。