石井祥裕(AMOR編集部)
「笑い」、といっても、心底ユーモアが醸しだす笑いが今回のテーマとなっている。このテーマについて、やはり見逃せない本が二つあるので紹介したいと思う。
と、その前に、一つ、筆者がオーストリア留学時に読んでいた『チロル日刊新聞』にあったジョークを記しておきたい。どうしても心から離れない話なのだが、再現できるかどうか…
あるとき一人の司祭が一人の修道女と一緒にゴルフに興じていた。ドライブ・ショットを何度も打っても、狙いどおりに行かず、いつも逸れていく。司祭は、そのたびに「フェアダムト(地獄に堕ちろ)!」と叫んでいた。その言い方はあさましく、司祭の品格もあったものではない。何度ショットを繰り返しても、同じように逸れ、そのたびに「フェアダムト!」と叫ぶ。(天の神さまがお怒りにはならないのだろうか……)。いよいよもって、繰り返しの極まるショットをした瞬間、かたわらの修道女が雷に撃たれて死んだ。すると、天から声が聞こえた。「フェアダムト!」
「地獄に堕ちろ!」(チロル・ジョークより)
余分な注釈だが、この「フェアダムト(Verdammt)」というドイツ語は、感嘆詞としては「いまいましい!」「こんちくしょう!」といった感覚の語なのだが、教会用語としては、神がある人々に永劫の罰を宣告するときのことばでもあり(その意味で「地獄に堕ちろ!」)、また、教会の教導職(教皇勅書や公会議決議書)で誤謬説や異端説を厳しく断罪するときのことばでもある。神や教会の絶対的権威を象徴することばが織り込まれた、いくえものブラックなユーモアが含まれている話だと思われないだろうか。
ユーモアが醸し出す笑いというテーマに関連して、思い浮かんだのが昨年9月6日に帰天したイエズス会司祭・上智大学名誉教授のアルフォンス・デーケン神父(1932~2020)である。生と死を考える会の創始者、死への準備教育・死生学といったことばや分野を一般化させるにあたっての功労者であることはよく知られていよう。
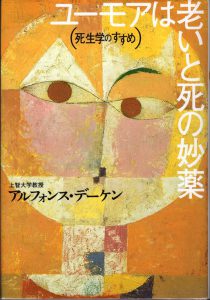 そのデーケン神父の授業を筆者が初めて聞いたのが1975年。上智大学の人間学の枠組みの授業で、死の哲学という講義だったと思う。彼のライフワークとなるテーマを展開し始めたころで、日本語がまだそれほど上手くないなあという印象の一方で、「ユーモア」を授業のテーマとして初めて耳にしたことが深く印象に刻まれている。そのころ出版されていたユーモアに関する分厚いドイツ語の研究書を紹介して「こんな分厚く書くとはね! あまりユーモラスな本ではないのですけれど」と、いたずらっぽく笑っていた神父の明らんだ顔を覚えている(Werner Lauer, Humor als Ethos, 1974年刊であったかと思う)。ジョークを飛ばしながら、赤面している先生だった。
そのデーケン神父の授業を筆者が初めて聞いたのが1975年。上智大学の人間学の枠組みの授業で、死の哲学という講義だったと思う。彼のライフワークとなるテーマを展開し始めたころで、日本語がまだそれほど上手くないなあという印象の一方で、「ユーモア」を授業のテーマとして初めて耳にしたことが深く印象に刻まれている。そのころ出版されていたユーモアに関する分厚いドイツ語の研究書を紹介して「こんな分厚く書くとはね! あまりユーモラスな本ではないのですけれど」と、いたずらっぽく笑っていた神父の明らんだ顔を覚えている(Werner Lauer, Humor als Ethos, 1974年刊であったかと思う)。ジョークを飛ばしながら、赤面している先生だった。
本書は、その頃から授業で語り始め、1985年から1993年までに新聞や雑誌に寄稿したエッセイを再編集してまとめたもの。内容は、ユーモア論というだけでなく、デーケン神父の生い立ち、そのライフワークへの思いなどが、実際に経験したユーモラスなエピソードとともにふんだんに含まれている。それは実際に読んでみてほしいところである。
次のことばは、まず共感できるにちがいない。
「毎日を心豊かに生きるためには、自分の失敗を客観的に眺めて、それを周囲の人たちと一緒に、笑いのネタにしてしまう自己風刺のユーモアが、何よりも必要ではないだろうか」(20~21ページ)
「ユーモアと笑いは、愛と思いやりの大切な表現方法の一つである」(26ページ)
「ユーモア感覚は、……高齢化社会を心豊かに過ごすための良きパートナーだ。何よりもお金のかからない健康法である」(29ページ)
そして、「ドイツには、『ユーモアとは、にもかかわらず笑うことである』という有名な定義がある」(35ページ)と教える。そこに老いと死にとって、なぜユーモアが妙薬なのか、という本書のテーマの出発点がある。
とりわけ、デーケン神父は自身の戦中・戦後の体験を語る。友人や親戚が空襲の犠牲になったこと、自身も学校の帰り道に突然飛来した敵機の機銃掃射にあって右耳を弾丸がかすめていった体験、一家が住む町を連合軍が占領した際、白旗を掲げて歓迎しようとして家を出た祖父(反ナチ抵抗運動に命懸けでかかわっていた)がいきなり連合軍兵士によって射殺されてしまったこと、しかし、アルフォンス少年はこの兵士たちを「ウェルカム」と告げて迎えたという。祖父の死と、そのときの自分の決断は、以後、人生を決める出来事となったのだと……。
現在の日本における死生学や生と死を考えるという実践分野の詳細はわからないが、その発端を築いた、神父の功績は不朽だろう。その主題と不可分にユーモアと笑いが語られていたことを受けとめ、その指摘を大切に受けとめたいと思う。死を意識し、それに迎える姿勢や営みが、今や軽やかに「終活」と語られるようになった背景にも、「ユーモアの伝道師」であったデーケン神父の働きが隠れているのかもしれない。
キリスト教的関心事から「笑い」をテーマにするにあたって、真正面からこれを表題としている本書もやはり欠かせない。東北大学名誉教授、宮田光雄氏の『キリスト教と笑い』である。恥ずかしながら、この高名な政治学者、ヨーロッパ政治思想史の専門家、「宮田学生聖書研究会」の主宰者である独立伝道者のことを、この本から初めて知ることになった。氏は1928年生まれでご健在である。
その膨大な著作は主に二つの著作集にまとめられている。一つは『宮田光雄集-「聖書の信仰」』(岩波書店 1996年)、もう一つは『宮田光雄思想史論集』(創文社 2006~2017年)。ドイツ近現代の政治思想、とりわけ、ナチズムやドイツの教会闘争、カール・バルト(1886~1968)やボンヘッファー(1906~1945)について単著も多い。
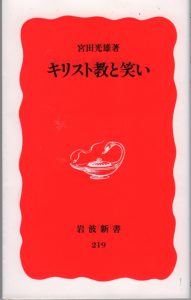 それらの中につねに織り込まれているテーマ「ユーモアと笑い」をピックアップしているのが岩波新書版の本書である。著者がこのテーマに目を開かれたのは、1960年頃、バーゼル大学で直接講義を聴いたバルトとの出会いによってだったという。「主の祈り」の「御国を来たらせたまえ」に関する講義の教室は、バルトの飛ばすユーモアで笑いに包まれていたのだと……。
それらの中につねに織り込まれているテーマ「ユーモアと笑い」をピックアップしているのが岩波新書版の本書である。著者がこのテーマに目を開かれたのは、1960年頃、バーゼル大学で直接講義を聴いたバルトとの出会いによってだったという。「主の祈り」の「御国を来たらせたまえ」に関する講義の教室は、バルトの飛ばすユーモアで笑いに包まれていたのだと……。
本書のモチーフは「はたしてイエスは笑っていたか」にある。その観点から聖書を読み直し、喜びと解放のメッセージとしてのキリスト教の新しい側面を探っている。たしかに本書前半で披露される「ヨナ書」の分析、福音書の分析は聖書への新しい興味を呼び起こす(著者はもちろん「イエスは笑った」という立場で先行研究を前進させようとしている)。
そして、このテーマから見たキリスト教思想史がかいつまんで紹介される。もちろんパウロ、ルター、バルトとボンヘッファーに重点が置かれているが、教皇ヨハネス23世のことも紹介されている。興味深いのは、デーケン神父の上掲書と、本書で共通に紹介されている人物としてトマス・モア(1477~1515)と(特集52「インスブルックの山影に」で紹介した)ガレン司教(1878~1946)がいることだ。殉教という苦難、そして第2次世界大戦という歴史状況を背景にしてユーモアが語られうることを、二人の著者が奇しくもほぼ同時に示していたのである。今の世界、そして日本の現実におけるわれわれにとって、大切な“時のしるし”に思えてならない。
最後に、本書が締めくくり(209~210ページ)に引用する二つのことばを、本書自体と、このテーマそのものへの入口として示しておきたい。
一つは、オランダのある神学者が「主の祈り」を言い換えたテキスト:
願わくはわれらのユーモアによって御名をあがめさせたまえ。
われらのユーモアを通して御国を来たらせたまえ。
御こころをわれらのユーモアにおいてならせたまえ、
天における笑いのごとく、地における笑いにおいても。
われらの信仰のユーモアを今日もあたえたまえ。
われらをユーモアによって傷つけるものをわれらがゆるすごとく、
われらのユーモアをゆるしたまえ。
われらをサタン的ユーモアから救い出したまえ。
なぜなら、それは何らユーモアではなく、真のユーモアは汝のものなればなり。
最後に、イエスのことば(ルカ6:21)。
あなたがたは笑うようになる。










