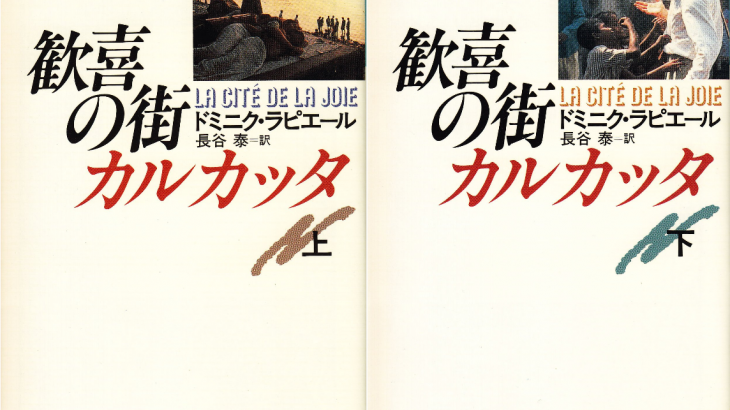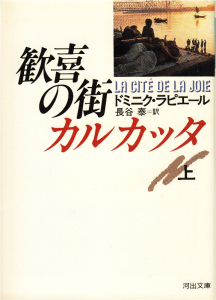私はこの『歓喜の街カルカッタ』(ドミニク・ラピエール著、長谷泰訳、河出書房新社、1987年)を見つけて読んだときにとても感動した。フランクルの『夜と霧』を読んだときと同じような感動だった。どうしてこの本を見つけたかは覚えていない。誰かに薦められて読んだという記憶もない。
『夜と霧』がそうであるようにこの本も読みにくい本である。この目を覆いたくなるような過酷な現実に満ちた世界最大のスラムがなぜ「歓喜の街」と呼ばれているのか、この本を読むと納得がいく。
サッカー場を3つ合わせたくらいの場所に7万人が住む、カルカッタ有数のスラム「歓喜の街」―。皮肉にもそう呼ばれる場所で彼らは、ゴミあさりや人力車を引きながら、1日20円ほどで家族を支えている。「20世紀に生きるわれわれにとって最も刺激的な体験は、月旅行をのぞけば、この『歓喜の街』で過ごすことである」と登場人物の一人は語る。
「パリは燃えているか?」の著者がマザー・テレサの国インドで体験した愛とヒロイズムの大型ノンフィクション! 全世界で12か国語に翻訳、300万部の大ベストセラー。日本語版ついに刊行!(単行本下巻帯より)
この街には、西欧の豊かな町のどこよりも、ヒロイズム、思いやり、そして喜びと幸福があった――確かに彼らは何も持っていない。しかし、この人たちはすべてを所有しているともいえるのだ!(単行本上巻帯より)
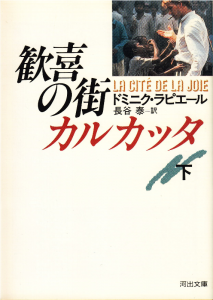 さらにこの本を原作とした映画がある。1992年作ローランド・ジョフィー監督の「シティ・オブ・ジョイ」。その紹介文はこちら。
さらにこの本を原作とした映画がある。1992年作ローランド・ジョフィー監督の「シティ・オブ・ジョイ」。その紹介文はこちら。
貧困のシンボルの様な町カルタッタに、一人の少女の手術の失敗から立ち直れない青年外科医が吸い寄せられる。容赦なく彼を襲う“歓喜の町”の厳しい現実。年端もいかぬ少女の売春、顔役の息子の非情な搾取、暴力……。そして彼は、干ばつの北インドを逃れてこの大都会に家族共々職を求めに来た男ハザフに出会う。その友情を軸に、町の腐敗に立ち上がる主人公の、自力更生していく様をドラマティックに描く。
小説の方には農村からコルカタに出てきて人力車の車夫をしているバザリ、マイアミの裕福な家庭に育ったユダヤ系アメリカ人の医学生のマックス、そしてこのスラムにすみたいと言ってやってきたフランス人のカトリック神父ランベール。この3人が主人公となって物語が展開する。
映画の方には残念ながらカトリック神父は出てこない。だから宗教色はほとんど消されている。
 小説の方がずっといいのだが、映画の方も決して悪くはない。私はこの映画を高校2年生の「宗教研究」のクラスの修道院泊まり込みの夜に見ることにしていた。感想については聴かないことにしているが、きっと生徒の心の奥深いところに感動を刻み込んだはずである。
小説の方がずっといいのだが、映画の方も決して悪くはない。私はこの映画を高校2年生の「宗教研究」のクラスの修道院泊まり込みの夜に見ることにしていた。感想については聴かないことにしているが、きっと生徒の心の奥深いところに感動を刻み込んだはずである。
小説の上巻の最後の部分にランベール神父が、マザーテレサを訪ねる場面がある。映画にはない。マックスがハンセン病の患者の施設を作りたいので助けてほしいとマザーに頼む。
「ユー・アー・ドゥーイング・ゴッズ・ワーク(あなたは神の望まれる仕事をなさっている)。わかりました。ハンセン氏病患者の世話をしつけたシスターを、三人行かせましょう」
ひとの身体がずらり並んだ部屋に目をやり、さらにマザー・テレサはいいたした。「あの人たちはわたしたちがあたえる以上のものを、あたえてくれます」
(中略)
ポール・ランベールは感無量の思いだった。
「カルカッタよ、たたえられてあれ。禍(わざわい)のなかにも、おまえは聖者たちを生みだしたのだ」
土屋至(元清泉女子大学「宗教科教育法」講師、SIGNIS JAPAN(カトリックメディア協議会)会長)