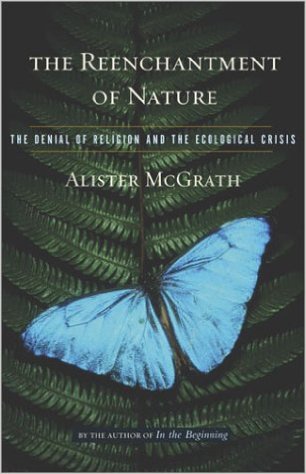環境問題に対するキリスト教の責任を問うような論調に触れたこともあるだろう。環境問題やエコロジーとキリスト教との関係を考察する書物に引き続き注目したい:
アリスター・マクグラス著『自然の再魅力化』
Alister McGrath, The Reenchantment of Nature : The Denial of Religion and the Ecological Crisis (New York:Doubleday, 2002), xviii+204 pages
環境問題(危機)は、自然科学が巨大化し、大量生産によって人類に幸福をもたらすと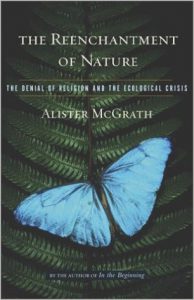 考えて自然を搾取してきたつけがついにまわってきて世界中が直面している大問題である。このような人為的災害の根源にキリスト教の考え方を見る識者もいる。環境危機をキリスト教の責任にする米国の識者は、東洋宗教やネイティヴ・アメリカンの考え方にその精神的解決を見いだそうとしている。さらに自然が神聖なものであるとして自然を女性神としてあがめようとする「環境フェミニズム」がある。それに対し、ここに紹介する本書の著者アリスター・マクグラスは、英国教会(聖公会)の聖職者であるとともに自然科学者として、キリスト教と自然科学が相対立する分野でなく、洞察を交換しながら人類のために奉仕できるという確信を伝えようとしている。
考えて自然を搾取してきたつけがついにまわってきて世界中が直面している大問題である。このような人為的災害の根源にキリスト教の考え方を見る識者もいる。環境危機をキリスト教の責任にする米国の識者は、東洋宗教やネイティヴ・アメリカンの考え方にその精神的解決を見いだそうとしている。さらに自然が神聖なものであるとして自然を女性神としてあがめようとする「環境フェミニズム」がある。それに対し、ここに紹介する本書の著者アリスター・マクグラスは、英国教会(聖公会)の聖職者であるとともに自然科学者として、キリスト教と自然科学が相対立する分野でなく、洞察を交換しながら人類のために奉仕できるという確信を伝えようとしている。
【さらに読む】
著者は、近代において人間が自然科学のせいで自然の魅力を感じることを忘れてしまったとし、その感覚を再び取り戻すべきだと訴えている。そしてそれが究極的にこのような環境問題の危機の克服の第一歩だと述べている。
このために彼は、キリスト教伝統における自然観を掘り起こし、現在の環境危機にとってキリスト教がその問題の一部であるとする主張が偏見と無知によるものであることを示すばかりでなく、将来の自然に対する態度を本来の姿に戻そうとする。根本的問題は人間の自律性を主張した近代の出現とともに、自然は人間に従属する組織体とみなされるようになり、キリスト教がこの世界観の出現に責任を負わされたことにある。その結果、自然利用に際しての人間の責任感の喪失が生じ、自然が特別なものであるというどの考え方も時代遅れとして斥けられた。自然はかつて特別な魅力をもつものとして扱われていたが、近代においてその特権を剥奪され、非神聖化された。だから、現代の環境危機を乗り越えるために自然を再魅力化するとしたら、キリスト教伝統に戻らなくてはならないと言うのである。
著者はまず、キリスト教の創造に関する考え方によって人間、自然、神の関係を説明し、そこから環境問題についての示唆を得ようとする。アウグスティヌス(354~430)、ボナヴェントゥラ(1217~1274)、フランスのルネサンス期の哲学者ジャン・ボダン(1530~1596)やアメリカ植民時代の神学者ジョナサン・エドワーズ(1703~1758)の考え方を使って、創造された世界に神の美しさの反映を見る伝統がキリスト教にあったことを指摘する。マクグラスの創造論では、人間を神の似姿、神のかたどりと見る人間観が核になっている。神の似姿である人間は神の美を反映する自然を尊重し、世話をする使命を与えられている。この認識がキリスト教の環境論的意識のもとである。
著者は、1961年のニューデリー世界教会協議会大会でのジョーゼフ・シットラー(Joseph Sittler, 1904~1987. シカゴ・ルーテル神学校教授)の演説がその意識の最初の現れであったとしている。また、彼は、最近のものとして一九九一年に米国カトリック司教団が発表した文書『地を新しくする』や、ユルゲン・モルトマン(1926~)の『創造における神』の三位一体論的環境論に触れながら、カトリック神学、エヴァンジェリカル神学、そしてプロセス神学におけるプロテスタント自由主義神学などが人間を自然の管理人であると考え、エデンの楽園の回復という終末論的希望のもとで自然と向かい合うというキリスト教的自然観を有していると考えている。そして自ら提案するのは、キリスト教の豊かな伝統から学ぶことである。
この観点から著者は、近代啓蒙思想期とは人類が自然を収奪し、支配者的種として世界を改造し、神を抹殺しようとした時代であり、そこには自然科学と無神論との間における一時的同盟関係が存在したとし、これを「ファウスト的契約」と呼ぶ。そして、これは近代技術の意識を無限に生み出すが、そこから生じる弊害を考えない、パンドラの箱なしのプロメテオスだとし、この意識をもつ近代人の自然への働きかけが「スターリン主義的環境論」であったと非難する。著者はこのように、自然支配の思想の背後に啓蒙主義の自然観である機械論的宇宙観、法則で動く時計仕掛けの自然という思想があったと考え、それに対して、マルティン・ブーバー(1878~1965)のいう「我と汝」の関係を人間と自然の間の関係に応用することを提案する。この人格的な関係は究極的には神と人間の関係である。ここで著者は、機械論的宇宙観の反論として起こったロマン主義の自然観に注目するのである。
機械論的宇宙観は楽観主義的のように表面的に見えても、その根底において「自然に肯定的である」のではなく、「自然に対して猜疑的」である。著者は、ホッブス(1588~1679)の考えを例にあげなから、啓蒙主義の自然観が「権力獲得のための闘争と生存」という観点から生まれたものであり、技術はここから生じたとする。啓蒙主義は自然の粗野さを文明化するという称賛すべき目的をもっていたが、結果的に自然破壊と貧困をもたらした。その典型的症例が産業革命で、それがもたらした「アーバニゼイション」(都会的にすること)という語は人間を社会的に洗練されたものにするという元来の意味から農村地帯を都市化するという意味に変わっていった。
これに対して、ロマン主義は人間と自然が調和して存在しうると主張する啓蒙主義への反論である。著者は、特に詩人ジョン・キーツ(1795~1821)の「自然は超越的存在を垣間見せる」という考え方に注目し、それを証聖者マクシモス(580頃~662)に代表されるギリシア正教の自然観「宇宙は神の典礼である」に結びつけている。自然はこのように見られたとき、その意義が変化する。この自然観は、もはや人間が孤独な存在でなく、精神的空虚の中に生きているのではないことを教えるのである。著者は、マッハ(1838~1916) やドーキンズ(1941~)らが唱えるような科学的自然主義に対して、近代の終わりの時代にあたって自然に再び魅力を取り戻させることを提案する。そのためにキリスト教は豊かな思想的資源をもっていると本書を通じて主張し続けるのである。
自然科学の攻勢と宇宙の法則と精神の倫理的要請を峻別したカント(1724~1804)の影響を受けてドイツ・プロテスタント神学者たちが長い間、歴史の意義に集中し、自然界の問題を取り上げなかったのに対して、英国教会の神学者たちは宇宙論を視野に入れていた。本書からもそのことがうなずけるが、それは彼らの中に護教学が残っていたことを暗示する。マクグラスも20世紀を終えた時代における自然科学の雰囲気を前提にしているが、それは自然科学が自然科学者の手の終えないところまで進歩し、彼自身では解決できない多くの問題が集約される環境問題に直面したところでの、キリスト教神学者による自然観の提案である。それゆえに信仰の弁明である護教学が内包されているのである。
(高柳俊一/英文学者)