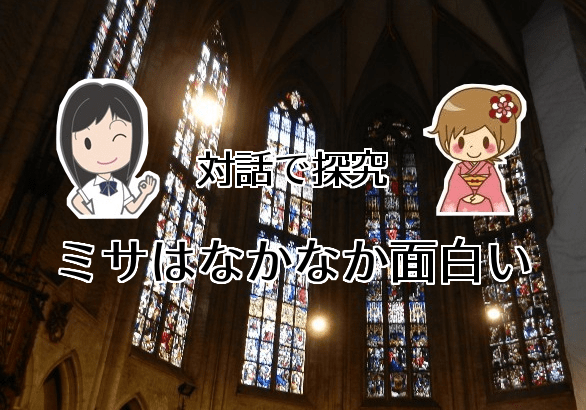「聖餅」登場……聖体をめぐる中世の経過
答五郎 さて、ミサ、とくに交わりの儀、聖体拝領に関して、古代教会の歴史を見てきたけれど、どんな点が印象深かったかな。
問次郎 イエスが最後の晩餐を使徒たちと行った記憶がずっと保たれている感じがしました。食事という形を保持しながら、イエスが行ったような賛美の祈りや感謝の祈りを、パンとぶどう酒の上にして、それを皆に配っていく……と。
美沙 そして、それがイエス自身のからだと血であるわけですから、それを食べ、飲むことは、イエスと深く一致するということなのですね。
問次郎 しかも、日常食べているのと同じパンを使っていたらしいことが興味深かったです。今のミサでは、明らかに日常のパンとは違いますからね。
美沙 ただ、そこで、聖体そのものが畏れ多いものという意識がだんだん強くなって、信者が拝領を遠慮するようになるという傾向が出てきたのですね。
答五郎 そうだったね。きょうは話を西方教会の中世に移すことにするよ。フランク王国のカロリング朝時代のことは世界史で習っているよね。
問次郎 はい、もちろん。756 年、ピピン(ペパン)3世、教皇領を寄進。800 年、カール(シャルル)が西ローマ帝国皇帝となる、といった出来事が有名ですね。
答五郎 実は、西方ラテン教会の歴史や典礼の歴史でも、この時代は重要な意味をもっているのだよ。フランク王国とローマ教皇との相互提携関係の象徴として、『サクラメンタリウム』と呼ばれる司式者用典礼書を代表とするローマ典礼様式が移入されていってね。
問次郎 政治的なことと典礼とは、案外、つながっているのですね。
美沙 それは、16世紀の宗教改革の時代にもまざまざと現れてきますよね。「キリスト教国」の宿命なのでしょうか。
答五郎 キリスト教であるかぎり、政治と無関係なことはないというべきか。イエス自身が「神の国」「神の支配」を告げ知らせたのが、そもそものことだ。
問次郎 で、聖体についてはどのようになっていったのでしょうか。
答五郎 そう、ミサをはじめ典礼全般に関していうと、4、5世紀から7、8世紀にかけて、主要地域ごとに古典的様式が出来上がっていたのだが、その一つであるローマ典礼様式がフランク王国に受容されると、当地伝来のガリア典礼の要素と融合しながら、今度は9世紀から10世紀にかけて、いわば「ローマ=フランク典礼様式」と呼ばれる、緩やかな統一的様式が形づくられていくのだよ。そこで、実はミサの姿、聖体拝領の姿も新しい様相を示すことになるのだ。
問次郎 カロリング朝というと今のフランス、ドイツ、イタリアの土台となる帝国ですね。つまりは、ヨーロッパのカトリック教会の典礼様式になるということですね。
答五郎 その時代に、聖体にされるべきパンの形状が小さく丸く薄い無酵母パンになってくる。つまり日常の食用パンとは最初から形が違い、さらに配るために便利なように最初から小さく分けられているものへとね。司祭用には大きめのものが使われ、「パンを裂く」というよりは「パンを割る」ものとなり、あくまで象徴的な意味の行為になっていく。
美沙 つまりは、今の教会でも普通に使われているような聖体用パンの始まりというわけですね。約1000年前なのですね。実は、フランスの小説を読んでいて聖体用のパンについて「聖餅」と訳されていたのを見つけて面白いなと思ったことがありました。日本人の感覚だとまさしく「煎餅」を連想させますものね。
問次郎 たしかに、煎餅にもいろいろ形はあるけれど、口に入れやすい煎餅などは聖体用のパンと同じような大きさになっているな。
答五郎 今、大事なことを言ったよ。聖体用のパンがあらかじめそのような小さな煎餅型の薄いものになっていくということは、信者に配りやすくなっているということだ。それと、その大きさも口に入れやすい程度にしてあるということは、この時代、だんだんと口で拝領することが広がっていったこととも関係している。
問次郎 なるほど。「聖餅」(いい訳だね)にしていることで、司祭の手で直接、信者の口に入れる、その舌に載せるというのが授け方の基本になっていくわけか。
答五郎 そう、それが基本となったということは、まずは信者のための便宜と教育を考えたのだろうね。配りやすいという点と、最初から聖体用パンが日常のパンとは違うものとなっていることで、聖体の秘跡について教えやすくなるという点で。そのような意味で司牧的教育的な配慮が形になったのが、カトリック的聖体用パンの形成ではないかと思う。
美沙 少し待ってください。最初はイエスの晩餐の記憶が大切で、ミサも初めは実際の会食の中で始まったのではなかったのですか。日常で使うパンやぶどう酒を用意して、イエスがしたように賛美と感謝の祈りをささげ、それを集まっている皆に配り、皆一つの心で分かち合う……それが感謝の祭儀の原風景だったのではないでしょうか。最初から聖体用のパンにしていては、だんだんと日常と離れていくのではないでしょうか。
答五郎 それは、鋭く、重要な質問だよ。たしかに、最初から聖体用のパンにしようとした背景には、キリストのからだと血を含む聖体であることを教えやすくするという教育的な意図も一つにはあったように思う。それと同時に、ふだんから聖体の秘跡に対する尊敬、畏敬、さらには畏れ多いという気持ちが、この時機に高まっていくということがあるのだよ。口で受けることの広まりもそれと関係がある。
問次郎 信者が手で触れるのは汚れるとでも……。
答五郎 実際、そういう意識が芽生えていったようなのだよ。
問次郎 でも、そういうやり方は廃止されて、今は皆、手で受けていますよね。
答五郎 いや、そうではないのだよ。実は今でも、ローマ・カトリック教会には聖体は口で受けるというのが原則として残っていてね。手で拝領するということについては教皇庁に許可を願い出るという手続きが必要なのだ。おおかたの教会(各国・地域の司教協議会)は許可を受けているから、どこでも手で拝領しているように見えるけれど、それでも、今でも口で受けることを原則としている教会もあるよ。
問次郎 なるほど、そういう意味で、ローマ・フランク様式が現在の基盤となっているわけなのですね。
答五郎 さらに、聖体に対して畏れ多いという感覚が強くなれば、だんだんとミサの中で聖体そのものを拝領しなくなるというのが、並行する中世の経過だ。そしてミサではない、別な聖体礼拝のさまざまなものが形成されるというのも、ヨーロッパのカトリック教会の歩みなのだよ。それについては、次回にしよう。
(企画・構成 石井祥裕/典礼神学者)