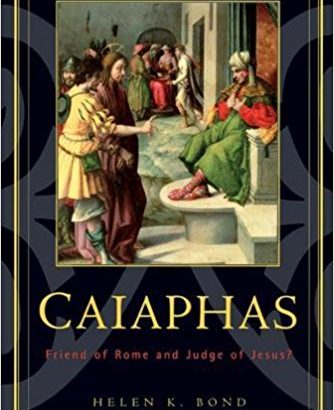福音書が物語るイエスの受難史の中で、大きく立ちはだかるローマとユダヤそれぞれ体制の代表者総督ピラトと大祭司カイアファ。この二人の人物の歴史的実像はどのようなものなのだろうか。特にピラトは使徒信条を唱える際に繰り返し名を告げるだけに興味深い。近年の研究の様相を伝える2書を紹介ししよう:
ヘレン・K・ボンド著『ポンティオ・ピラト:歴史と解釈における』
同著『カイアファ:ローマの友、イエスの裁判官?』
Helen K. Bond, Pontius Pilate: in History and interpretation (Cambridge: Cambridge University Press, 1998) (Society for New Testament Studies Monograph Series 100), xxv+249 pages.
Helen K. Bond, Caiaphas: Friend of Rome and Judge of Jesus? (Louisville: Westminster John Knox Press, 2004), x+220 pages.
以上の2点は同じ女性新約学者によるイエスの裁判におけるそれぞれローマ行政官とユダヤ教大祭司であった2人の当事者についての研究である。
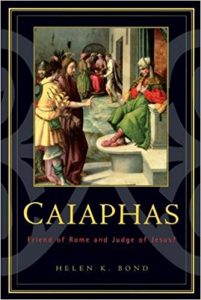 『ピラト』では、著者はまずローマの歴史家タキトゥスらの資料に基づいて、この第5代ユダヤ総督の政治・行政的状況をシリアとパレスティナの関係についての地政学的見地から説明している。すでにこの問題については多くの研究者の研究対象となっており、意見が分かれる点が多い。著者は序論で研究・学説史を展望して自分の立場を明らかにしようとする。ついで、新約時代におけるギリシア化したユダヤ人著作家フィロンとヨセフスの著書におけるピラトの記述を出発点として、彼らそれぞれの立場からのこのローマ総督に対する見方を紹介している。続いて、マルコから始めて第4福音書ヨハネまでのそれぞれの福音書の神学からなされたピラトの性格解釈を引き出す方法が取られ、最後に総括として、福音書の受難物語の背後に何があったのか、いわばイエスの史的裁判ともいうべきものを再現しようと試みている。著者は『ピラト』を発表した後、このローマ総督に対してイエスの受難史におけるもう一方の立役者エルサレムの大祭司長カイアファの研究を著している。
『ピラト』では、著者はまずローマの歴史家タキトゥスらの資料に基づいて、この第5代ユダヤ総督の政治・行政的状況をシリアとパレスティナの関係についての地政学的見地から説明している。すでにこの問題については多くの研究者の研究対象となっており、意見が分かれる点が多い。著者は序論で研究・学説史を展望して自分の立場を明らかにしようとする。ついで、新約時代におけるギリシア化したユダヤ人著作家フィロンとヨセフスの著書におけるピラトの記述を出発点として、彼らそれぞれの立場からのこのローマ総督に対する見方を紹介している。続いて、マルコから始めて第4福音書ヨハネまでのそれぞれの福音書の神学からなされたピラトの性格解釈を引き出す方法が取られ、最後に総括として、福音書の受難物語の背後に何があったのか、いわばイエスの史的裁判ともいうべきものを再現しようと試みている。著者は『ピラト』を発表した後、このローマ総督に対してイエスの受難史におけるもう一方の立役者エルサレムの大祭司長カイアファの研究を著している。
ピラトとカイアファ。両者のついての見方は、ピラトが東方教会では聖人とまで考えられるほどの高い評価を与えたのに対して、西方教会では反対にピラトに対する評価は低く、その死が恐ろしいものであったとしている。カイアファについては多くの場合、彼の人物はユダヤ人一般のイメージの中に取り込まれ、キリスト教徒の想像力をかき立てるものにはならなかった。
 【さらに読む】
【さらに読む】
『ピラト』において、著者はローマ属領史とその行政的区分と関係の問題、さらには当時のユダヤ側資料としてのフィロン(生没年 前25~後45)の著書やヨセフス(生没年 37/38頃~100頃)の『ユダヤ古代誌』や『ユダヤ戦記』については多くの研究がなされていることを指摘し、そのおおかたの意見をまとめるが、福音書が描くピラトを細かく検討した研究は英語圏ではほとんど見られないと述べている。二人のユダヤ人著作家によるピラト像はそれぞれの立場や利害関係の網をとおして解釈されたものである。福音書におけるピラト像もその記述者の背景や意図のリトマス紙を通したものである。つまり、著者が言うには、共観福音書マタイとルカのものがどのようにマルコのものから違ったものになっているかが重要になってくる。あるいはヨハネ福音書の場合はどうであるのか。そして、それが1世紀のそれぞれ異なったキリスト教団がもっていたローマ当局に対してもっていた態度にどのように反映されているのかを見ることは重要である。
共観福音書の最初であるマルコは原始的な段階のものとされてきたが、著者はこのような古典的聖書学の見方には反対のようである。マルコの目的は、彼の教団の信者たちを来るべき迫害の困難のために準備させることであった。ピラトはこうしていわば強い性格の迫害者の原型としてマルコによって描かれる。マルコにとってイエスは何の非もなく処刑された救い主である。ピラトは有能な政治家で、けっして優柔不断な弱い性格の持ち主ではない。イエスは彼の前で沈黙したが、その沈黙が彼を十字架の刑に導いたのである。著者はこの点に関してマルコ4章17節と8章34~38節に言及している。すべての責任はユダヤ人祭司の側にある。ピラトによる処刑はねたみと誤解に由来する。マルコの福音は無実な人の子が決して失敗した政治的指導者などではなく、多くの人のために命を代価として支払った救い主であるとするものである。
マタイはこのテーマを受け取ったが、ユダの自殺の話や、ピラトの妻が見た夢、バラバのことなどを加えて語りとして引き立つようにした。著者はマタイにおいて群衆の役割とその責任を強調する。ある意味でマタイは反ユダヤ人主義的である。著者はピラトが総督ピラトと呼ばれることに注意を喚起する。裁判はあくまでもローマ当局による裁判である。しかしマルコに較べてマタイでは、ピラトの裁判での役割はあまり重要でなくなる。マタイの関心事はキリスト教徒とユダヤ教の関係の断絶であり、イエスの死の責任はユダヤ人祭司階級と群衆にある。ピラトにまったく責任がないのではないが、マタイの記述には、ピラトがローマとユダヤ人との微妙な関係を背景にして、事件の責任をユダヤ人側に押しつけようとしたことがうかがわれる。
ルカは受難物語の前にすでに3度ピラトの名前を出している。(ルカ3・1、13・1、20・20以下)。著者はルカがマルコの記述を大いに書き換えたと考える。ルカのキリスト教弁明の中心路線は23章1~25節で披瀝(ひれき)されているが、それはピラトをイエスの無実についての公的証言者として利用し、イエスの十字架刑の責任をユダヤ人の代表である大祭司たちの陰謀に結びつけることであった。最終的には群衆がローマの正義に勝つことになる。
ルカは初めてピラトを弱いローマ総督として描いたのに対して、ヨハネにおけるピラトは優柔不断の支配者ではなく、イエスを直ちに裁判し、彼がローマの支配にとって脅威であることを見抜く総督である。しかし彼はイエスを嘲ることを最後までやめない。ヨハネ福音書においてユダヤ人もピラトもともにイエスに敵対的である。イエスのこの世のものでない支配とカエサルの権力のはっきりとした対照は、この福音書の読者の教団が帝国主義的ローマの力をつねに意識していたことを暗示する。
聖書外からの証言は、ピラトが強力な行政官であり、同時に地域の平和を維持するために柔軟であったことを示し、水道の建設は彼が大祭司たちと協力関係をもつことができた有能な政治家であったことを示している。イエスの処刑は過越祭というもっとも手腕と緊張を要求する時期に行われた。ここでもピラトは、神殿当局と協力して秩序を守ることができることを示している。ヨセフスは彼が反乱を抑圧するのに容赦しない残忍な人物であると述べているが、フィロンが述べているように、過越祭のエルサレムで、兵士たちの盾から帝国のイメージを消させたような配慮ができる行政官であった。
次に『カイアファ』を紹介しよう。カイアファは代々大祭司を出していた一族であった。なぜ彼が長くこの職に就くことができたかはヘロデ・アンティパスの政策とのかかわりがある。著者はまず1990年11月の終わり頃、エルサレムの南で行われていた公共工事の現場で偶然発見された墓の石棺の文字からそれがカイアファ一族のものである可能性が取りざたされた墓について語る。その中にあった60歳前後の男性の骨は不確かだが、カイアファのものの可能性はある。それが、カイアファが実際の歴史の中で重要な人物であったことを示す証拠になりうると著者は述べている。
5世紀の外典『ピラトの言行録』では、彼と叔父のアンアは一貫してイエスの裁判で彼を糾弾するが、イエスの神性が証明されると、彼は回心して敬虔なキリスト教徒になる。アラビヤ語の幼児福音とも呼ばれる『ヨセフ・カイアファの本』は同じような見方をしている。しかし、この人物に対する好意的見方はキリスト教の中で一般的にならなかった。中世の神秘劇ではカイアファはおきまりの登場人物となったが、彼の滑稽さだけが強調された。そして後の時代でも現代に至るまで彼を好意的に見る者はいない。
カイアファは、裁判でイエスに出会う以前に彼自身の歴史をもち、それがイエスの裁判で大きな役割を演じた。この裁判はエルサレムの大祭司一族に生まれ育った人物とガリラヤの農村部で生まれ育った人物の文化的衝突であったことを著者は暗示する。カイアファはその生涯中多くのメシアや反乱者を経験し、大祭司として神殿で公的中心人物として生き、その政治的に重要な役目はローマ軍を彼の同胞に近づけないようにすることであった。その観点で彼とピラトとの関係は見られなければならない。こうして本書で著者はヨセフスと他のユダヤ教文書、死海文書やクムラン文書さらには後世のユダヤ教文書、考古学的知見を福音書に照らしあわせて「史的カイアファ」にたどりとこうとする。
まずカイアファという名前だが、それが「籠」を意味するようであるので、著者は祖先がおそらく市場で籠を売っていた商人か、ロバで籠を運ぶ運搬業者だったのではないかと推測する。しかし紀元前1世紀頃からエルサレムとその周辺に土地をもつ富豪になっていて、周辺の土地管理は代理人に任せてエルサレム市内に住む貴族となっていた。そのような貴族の中から、彼はエルサレム神殿で奉仕する大祭司に上り詰めるのだが、もともと祭司の一族でなかった彼がその地位に着くことができたのは彼が結婚によって大祭司アンナスの一族とつながりができたためであった。
ローマ属領、ヘロデ・アンティパスの支配の時、大祭司の第1の使命は神殿の行事がスムースに運ぶようにすることであり、そのために、ローマ当局と複雑で広い神殿構内の運営が任されるように微妙な妥協をすることであった。カイアファが受けた教育は当時の文書から知られるものであったはずである。ローマ支配時代はすべてのユダヤ人にとって困難なものであったが、彼は政治的現実を受け入れなければならず、ローマ当局が要求するところと神への義務の間を調整しなければならなかった。カイアファが19年間も大祭司でありえた事実は、彼の調整能力と外交的手腕のほどを暗示している。ある意味でそれが可能であったのはピラトとの良好な関係であった。ピラトがローマに召還され、パレスティナの現地を離れたとき、彼は大祭司の地位を失う。その後、彼はどうなったのか、彼の死はその誕生がヴェールに包まれているように神秘に包まれている。
著者は以上の考察の後、それぞれに1章をふりあてて4つの福音書における「文学的カイアファ」がどのようなものであり、どう違うかを詳しく分析する。最初のマルコ福音書は大祭司を名指しすることを拒否し、イエスの死刑が神殿の祭司団の責任であったことを暗示する。ルカは歴史的人物カイアファに興味をもったように見えるが(ルカ3・2、使徒言行録4・6)、実はマルコと同じで、カイアファの名前を出していないし、大祭司は使徒言行録の初めのペトロと弟子たちが神殿で起こす騒動には姿を見せない。マタイとヨハネにおいては、イエスの裁判をめぐって彼とイエスの対決の図式が使われている。マタイではまだ萌芽の段階だが、ヨハネはそれをはっきりと打ち出している。4人の福音書記述者とも「史的カイアファ」についての歴史的正確さには興味をもたず、なぜイスラエルの指導者、祭司たちがイエスを受け付けなかったのか、教会がどのようにして「新しいイスラエル」なのか、誰がそのメンバーなのかに興味を寄せるだけなのである。
(高柳俊一/英文学者)