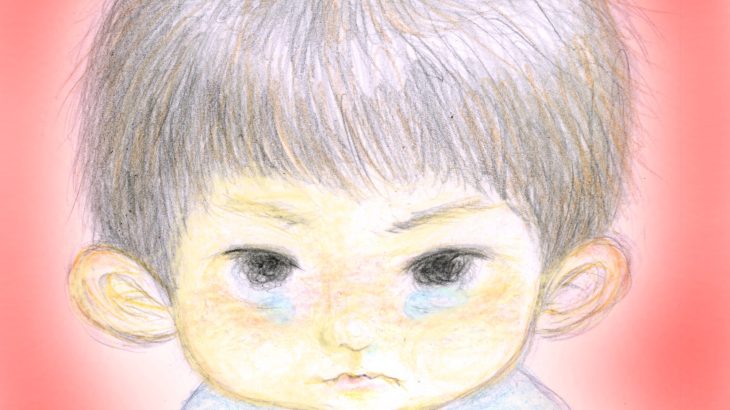片岡沙織
最近の私の大きな悩みといえば、子どもたちの第1次反抗期です。もともと次男は母親に向かって「ばか」と叫ぶくらいですから、生まれたときから反抗期といえばそうなのですが、最近それはそれは顕著になってきました。長男も次男と比べて程度が大きいか小さいかの差でしかなく、しっかりと反抗期に突入したわけです。
最近の彼らといったら、右と言ったら左へ、座れと言ったら立ち、止まれと言ったらジャンプをし、静かにしなさいと言えば叫びます。そのようなときに私たち夫婦はどうするかというと、昭和の漫画のように、メラメラと怒りの炎をあげ、カンカンになってりつける。子どもたちはお決まりのように、どの程度親が怒るかチラチラ見ながらふざけの大小を調整し、親が怒りの最上級まで行ったところでやっと(5分くらいだけ)静まり返る。しかしまた、子どもたちは互いの顔をチラチラ見はじめ、くすくすと笑いだしてまたふざけ始める。そしてまた親の逆鱗に触れて、子どもたちはとうとう痛い目を見、涙を流して「もうしません」と許しを請い、親はまったくもうと言いながら少し怒りすぎたことを自戒していると、また二人でふざけ始める……。日々このような生活を最近は送っています。
言葉もずいぶん達者になってきました。最近では、母親が何か言えば「ママも~しなさい!」「ママもごはん食べ終わってないじゃん!」「あとで準備する」「めんどくさい」「~ちゃんもやってないよ」「なんでわかってくれないの」「~って言ってたじゃん、あやまって!」などなど。
このような言葉を子どもたちが発してきたときは、私という母親ときたら、子どもの言葉を真正面からキャッチして、このように応酬をするわけです。最近の教育の風潮ですと、子どもの気持ちをまずは受け止め、子どもの話を傾聴し、言葉にならない思いを質問して吐き出させてあげる、などという対応が挙げられるかもしれませんが、そんな余裕は私にはまったくないわけです。
「そんなこと言ったら~あげないからね!」「ママは忙しいんです! いろいろやることあるんだから!」「今やりなさい今! 後でなんて絶対やらないから!」「そんなこというならもう食べなくていい! もうママ食事作ってあげないからね!」とまぁ、大人の力を最大限に利用して大人げないわけです。
しかし、子どもたちは強い態度や言葉を使って生意気を言ってきているかと思いきや、夜中に「ママ~」と泣き出すこともあるわけです。何を泣いているのかと問うと、「怖い夢を見た」と。そして「ママ、抱っこ」と全身を預けてくるわけです。これはこれは赤ちゃんに戻ってしまったかのような様子です。また、遠出をして歩き疲れてしまったときには、都合よくそのときばかり幼い頃に戻ったかのように「抱っこして」と甘えてくることもあります。
当然親としては悩みます。なぜ子どもたちは、こんなにも親を悩ませる行動をするのか。そして私の子どもたちへの対応はこれでよいのか、と。そして自分の子どもたちに対する言動を省みては落ち込んでしまうのです。またやってしまった、と。
とある心理学の研究によると、「親子関係」は生まれてから大人になるまでの間に、5つの段階を経て変化していく、と言います。
- 1段階目:親が子を手の届く所に置く
- 2段階目:親が子を目の届く範囲に置く
- 3段階目:親が子を信じ、遠くでつながっている
- 4段階目:親が子と距離を取り、離れる
- 5段階目:親と子が対等になる
この5段階を見ますと、現在私と子どもたちとの関係は、年齢的にも実情でも2段階目といえるのかと思います。2段階目の子どもは、自分で歩けるようになり、自分の意志や興味を持ち、自分で歩いて行動していける段階なのだそうです。しかし、親のほうが1段階目にとどまり、抱きかかえてしまう例があるようです。それが「だからママが言ったとおり転んだでしょ。」と行動に制限をかけ、子どもの自立心をそいでしまうことがあるということです。
私はこの話を聞いて、愕然としたのでした。子どもが育っているのに、親である自分が子どもの成長に追い付いていなかったのだなと。私の口癖は「だからママ言ってたでしょう!」でしたから。少し自分を振り返ってみますと、実は母である私の本当の気持ちとしては、寂しさがあるのです。赤ちゃんで危なっかしく、私を頼り切っていた子どもたちが、今や母を頼らないで自立しようとしているのですから。待って、そんなに早く大人にならないで。まだもう少しの間は、ママのほうを向いて頼ってきてほしいと。しかし、母の思いとは裏腹に、子どもたちは母の想定をいつも超えてくるのです。まだ自分の範囲内に留めておきたいと、無意識的に私は感じていたのかもしれません。
現在5歳の子どもたち。5歳の段階で、私が、親が、心理的に子離れを心掛けなければならないのだと、初めて思い至ったのでした。
 いま子どもたちは、成長のはざまで一生懸命もがいているのでしょう。自立と依存のはざまで内側から揺り動かされているのだと。そのようなときに思い出すのが、放蕩息子を抱える父親についての聖書箇所(ルカによる福音書15章11~32節)です。2人の子どもがそれぞれの理由で迷う中、父親は彼らを受け入れ続けます。
いま子どもたちは、成長のはざまで一生懸命もがいているのでしょう。自立と依存のはざまで内側から揺り動かされているのだと。そのようなときに思い出すのが、放蕩息子を抱える父親についての聖書箇所(ルカによる福音書15章11~32節)です。2人の子どもがそれぞれの理由で迷う中、父親は彼らを受け入れ続けます。
このような親になりたいと思う反面、これは神様の在り方だ、私には一生かけてもこのようにはなり切れないと諦めの気持ちももうすでにあります。
ここで良い考え方を共有したいと思います。
それは、イギリスの精神科医ドナルド・ウィニコットの「ほどよい母親―Good enough mother―」という考え方です。子どもの要求に対して、親が完ぺきに応じることはできません。時には壁として彼らの前に立ちはだかりながら、自立までの過程を支えていく、時には失敗もする人間らしい親の在り方が、この言葉には表現されています。この考え方は、どれだけの親を慰め支えるだろうかと感じます。子どもを育てる保護者の方と話をすると、皆さん一生懸命子育てしています。それぞれの置かれた環境で、急速に変化する社会に翻弄されながら。
時々、このように思うときがあります。すべての保護者の方が、だれかにふと「ほどほどで良いのよ」と「あなたは頑張りすぎなくらいよ」と声をかけてもらえたらな、と。それだけで救われる人がいるのではないかなと、そう思うのです。
この言葉を知ってから、「失敗しちゃったな」と思う日は、息子たちに「ごめんね」と言うようにしています。ヒステリックに怒ってしまったり、大失敗をして落ち込んでいたり、職場のイライラを子どもに向けてしまったり。欠点だらけの親ですが、それはそれで子どもたちの成長の糧になっていると信じて、「ママ怒りすぎちゃった、ごめんね」と。そんなことを言うようになってからは、子どもたちのほうから「さっきはごめんね」なんて言うようになりました。そのあとは、互いに少し素直に言葉を伝えあえている気がしています。「こうしてほしかったんだよ」「これはしないでほしかったな」などです。まだまだ反抗期真っ盛りですが、この仲直りの瞬間があるから、また自分を律しながらも頑張る気持ちがわいてくるのかもしれません。
放蕩息子のたとえで描かれる父親のようにいつかなりたいと憧れながら、私は子どもたちとともに、一進一退を続けながら、成長していきたいのです。