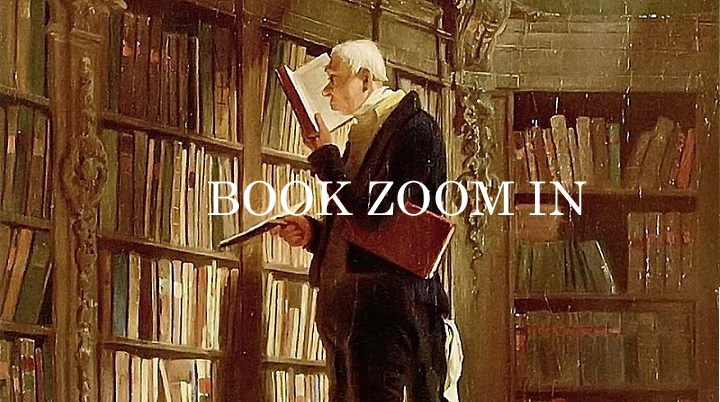丹下和彦『ご馳走帖: 古代ギリシア・ローマの食文化』、未知谷、2023年、1980円。
マムレの樫の木の下での食事、過越の食卓、カナの婚宴、最後の晩餐など、聖書には印象的な食事の場面がいくつも描かれています。「上質の小麦粉を三セアこねて、パン菓子を作りなさい」(創18・6)や「肉を火で焼き、種なしパンに苦菜を添えて食べる」(出12・8)といったように、素材や調理法、さらには分量にまで具体的な描写がある個所も珍しくありません。「食べ、飲み、楽しむことよりほかに人に幸せはない」(コヘ8・15)という言葉すらあるように、食事は単なる生命活動を超え、喜びであり、人と人をつなぐ大切な営みでることを聖書は伝えているのではないでしょうか。
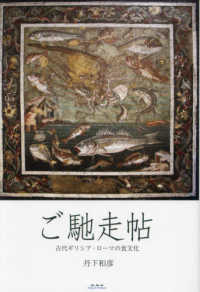 ところで、聖書が書かれた古代、イスラエル人以外はどのような食生活を送っていたのでしょうか。そんな疑問への手がかりを与えてくれるのが、今回紹介する『ご馳走帖: 古代ギリシア・ローマの食文化』です。古代ギリシア文学の専門家である丹下和彦によるエッセイ集である本書は、古代ギリシア時代に書かれた様々な作品を手掛かりに、当時の食文化に思いをはせています。
ところで、聖書が書かれた古代、イスラエル人以外はどのような食生活を送っていたのでしょうか。そんな疑問への手がかりを与えてくれるのが、今回紹介する『ご馳走帖: 古代ギリシア・ローマの食文化』です。古代ギリシア文学の専門家である丹下和彦によるエッセイ集である本書は、古代ギリシア時代に書かれた様々な作品を手掛かりに、当時の食文化に思いをはせています。
パンやオリーヴといった定番の食材にとどまらず、日本人にもなじみ深いマグロを古代ギリシア人も好んでいたこと、ワインだけでなくビールも飲まれていたことなど、思わず「へぇ」と声が出るような話題が次々と登場します。また、古代ギリシア小説における食の描写や、生け贄の文化など、専門家ならでは文章も掲載されています。引用される文章もテーマに負けず劣らず多彩で、古代の食について研究する際には欠かせないアテナイオスの『食卓の賢人たち』に始まり、アイスキュロスやアリストパネスといった著名な作家から無名の人の詩、さらにはアリストテレスに至るまで、多種多様な人々の声が紹介されます。
戦後に生まれ育った著者自身の経験やカラオケスナックの話題などを通じて、古代ギリシア人と今日の日本人という時代も場所も遠く離れた二つの民族の共通点、いや食に対する人類普遍の態度に著者の眼差しが注がれます。
石川雄一 (教会史家)