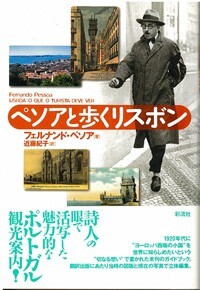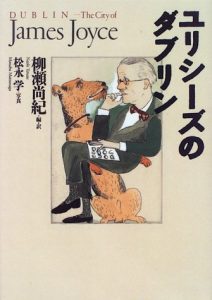倉田夏樹(南山宗教文化研究所非常勤研究員、立教大学日本学研究所研究員、
同志社大学一神教学際研究センター・リサーチフェロー)
われは御訓戒(おんいましめ)を破れる身にて
功も徳もなき者なれども、
限なき御慈悲(おんあわれみ)に依頼(よりたの)み、
諸悪の絆(ほだし)に引かれながら、
あえて御前に進み奉る。
――「完全なる痛悔の祈」
『カトリック祈祷書』(長崎大司教認可)
本年2023年は、遠藤周作生誕100周年である。出版社は勿論のこと、文学館の企画展も含め、学会、研究会も大いに盛り上がっている。本特集は様々な視点から、「遠藤周作生誕100年」について考えるものである。長崎出身のカトリック信徒である筆者に編集部から課せられたテーマは、「遠藤周作の文学と長崎はなぜ相性が悪いのか」ということである。この問題は、性質上、実証的に問うことが困難であるが、体感、所感を含めて、筆者なりに考えてみたい。
周知のとおり、遠藤周作は100年前、1923年の生まれで、東京府巣鴨で生まれている。1926年に父の転勤に従い、満州・大連に移り、1933年、父母の離婚により帰国。神戸市六甲を経て、西宮市夙川に転居している。カトリックの洗礼を受けたのは、1935年、12歳のころで、兄と一緒に夙川カトリック教会においてである。洗礼名はパウロ。
遠藤と長崎が地理的に交わったのは1964年4月、41歳のころである。カトリック信徒になって29年目の出来事で、早熟な遠藤にしては意外と思われる。遠藤と長崎の精神的交わりは、1959年の短編『最後の殉教者』にまで遡る(『遠藤周作事典』455頁「長崎」の項)。その後1960年に肺結核が再発して入院し、病床でキリシタンに関する本を読み始め、キリシタン史を背景にした小説を書く構想を描く。初めて長崎を訪ねた際、大浦天主堂の下にある十六番館で見た踏絵をきっかけとして『沈黙』の構想を得たと言われている。来崎から2年後、1966年に『沈黙』という結実を果たす。第二バチカン公会議(1962~65年)の直後であることも覚えておきたい。
その後も、遠藤は何度も長崎を訪ねている。若松英輔は、「長崎は私の『心の故郷』である、と遠藤周作は一度ならず書いている」と記している(「愛しみの哲学 第五章 哀しみの彼方――遠藤周作と長崎」『文藝』2014年冬号、422頁)。
遠藤の死後10年目に、遠藤周作、芸術新潮編集部編『遠藤周作と歩く「長崎巡礼」』(とんぼの本)という本が新潮社から出版されている。長崎県下のキリシタン巡礼地を文と写真を交えて案内する内容で、長崎カトリックも知らないような巡礼地をも網羅している。恐ろしくまとまった巡礼ガイド本である。この本を初めて見た時に、類書に、柳瀬尚紀=編・訳、松永学=写真『ユリシーズのダブリン』、フェルナンド・ペソア著、近藤紀子訳『ペソアと歩くリスボン』があることを想起した。「作家+観光地」のパターンである。
- 遠藤周作、芸術新潮編集部編『遠藤周作と歩く「長崎巡礼」』(新潮社、2006年)
- フェルナンド・ペソア著、近藤紀子訳『ペソアと歩くリスボン』(彩流社、1999年)
- 柳瀬尚紀=編・訳、松永学=写真『ユリシーズのダブリン』(河出書房新社、1996年)
ダブリンもリスボンもカトリックの地である。長崎はと言うと、「カトリックの地」とは言い難いが、少なくともカトリックに縁がある地である。ジェイムズ・ジョイスもフェルナンド・ペソアも、決してカトリック作家とは呼ばれないが、ともにカトリック学校(ジョイスはイエズス会)を卒業しており、小説にも色濃くカトリックの伝統が現れる。『ユリシーズ』の第一挿話「テレマコス」の冒頭で、主人公の一人スティーヴン・ディーダラズの友人バック・マリガンが、サンディ・コーヴのマーテロ塔において「ワレ神ノ祭壇ニ行カン」(Introibo ad altare Dei)とおどけて言っていたことが印象深い。『ペソアと歩くリスボン』の方も、ジェロニモス修道院、サン・ロケ教会、サン・ヴィセンテ・デ・フォーラ教会などが、信仰的というよりも美学的な視点で案内されている。両作家ともに、実際はさほど反カトリックという感はない。
『遠藤周作と歩く「長崎巡礼」』が、紹介した他の二冊の本と違うのは、ジョイスがダブリン出身、ペソアはリスボン出身であるのに対し、遠藤は長崎出身ではないことである。しかし、この本において「異邦人」の遠藤周作が紹介する長崎は、とても奥深い。あえて乱暴に言えば、「長崎人には長崎知らずが多い」のであって、大体が長崎を出てから長崎の奥深さに気づくものである。長崎カトリックは、隣の教会にすら行くことが少ない。県外から来た巡礼者は長崎中の教会を周遊する。県外から来た巡礼者の方が長崎の教会全般に詳しくなるわけである。
『遠藤周作と歩く「長崎巡礼」』は、長崎市内の大浦天主堂、浦上天主堂、日本二十六聖人記念館(西坂処刑場跡)、コルベ記念館、外海の黒崎教会、遠藤周作記念館、出津教会、大野教会、島原半島の雲仙地獄、島原城跡、日野枝城跡、原城跡のほか、平戸市の田平教会、聖フランシスコ・ザビエル記念聖堂、宝亀教会、紐差教会、五島の貝津教会、水の浦教会などを網羅している。県外の方も、そして特に長崎のカトリックの方も、ぜひこの本を片手に「長崎巡礼」をしていただきたい。巻頭に所収されたエッセイ「私の心の故郷」で遠藤はこう書いている。
長崎の歴史を知れば知るほど、それを学べば学ぶほど、この街の層の厚さと面白さとに感嘆した。更に私の人生に問いかけてくる多くの宿題も嗅ぎとった。それらの宿題のひとつ、ひとつを解くために私は『沈黙』から今日までの小説を書いてきたと言っていい。
(遠藤周作、芸術新潮編集部編『遠藤周作と歩く「長崎巡礼」』4頁)
筆者が遠藤文学と出会ったのは、上京してからである。長崎には18歳までしかおらず、当時は日本文学を読んでいなかったので、おそらく遠藤の名前も知らなかったであろう。東京での浪人時代は外国文学を濫読していたので、遠藤周作の名前は知っていたが、読むことはしなかった。ノストラダムスによって世界滅亡が予言された世紀末の1999年に文学部キリスト教学科という学科に進んでからは、講義の内外で、教師から、学友から、「遠藤周作」という名前を数多く聞いた。遠藤の死は1996年、没後すぐの「キリスト教学科」であったから当然と言えば当然だろう。
予備校生時代の筆者は、文科的教養のある東京の地で「カトリック文学」という存在を知り、耽読の日々となった。予備校の恩師は、大学の名誉教授で英文学専攻だったので、そこからすぐにグレアム・グリーンに到達した。『情事の終り』や『権力と栄光』などを読んだ。英文学専攻の恩師は仏文科も経ていたので、フランソワ・モーリヤックの話もされていた。東京・駿河台の坂を下り、三省堂や古書店街で、モーリヤックの文庫『テレーズ・デスケイルゥ』、『イエスの生涯』などを買い求めたのを覚えている。
大学入学後、前述の理由から、遠藤周作は無視できない状況になった。また、母からの段ボール支援物資に雑誌の一部があり、それは遠藤についてのページであった。雑誌上の遠藤は、長崎・外海を「神様が僕のためにとっておいてくれた場所」と呼んでいた。何と大仰な人だろうとも思ったが、郷里を褒めてもらえることは嬉しくて、『沈黙』、『侍』、『死海のほとり』、『イエスの生涯』、『キリストの誕生』、『わたしが・棄てた・女』などの文庫を次々に手にとった。
一番のインパクトはやはり『沈黙』であった。郷里を舞台とした小説であることが大きかった。そして、「棄教」という、できれば考えたくないテーマだ。読んでいくうちに、ストーリーにどんどん惹き込まれていく。キリシタンの殉教と、宣教師の「棄教」は、信徒読者としては苦しい箇所だ。後半部を読んでいくと、まるで棒で殴られたような衝撃が走った。
自分は彼等を裏切ってもあの人を決して裏切ってはいない。今までとはもっと違った形であの人を愛している。私がその愛を知るためには、今日までのすべてが必要だったのだ。私はこの国で今でも最後の切支丹司祭なのだ。そして、あの人は沈黙していたのではなかった。たとえあの人は沈黙していたとしても、私の今日までの人生があの人について語っていた。
(遠藤周作著『沈黙』295頁)
非力であることが常と言われる「たかが小説」にこんな力があるとは思っていなかった。普通の小説とは次元の違う、極めて高次元の小説だと思った印象がある。これからも普遍的な価値を持ち続ける作品だ。
*続きはこちらです。