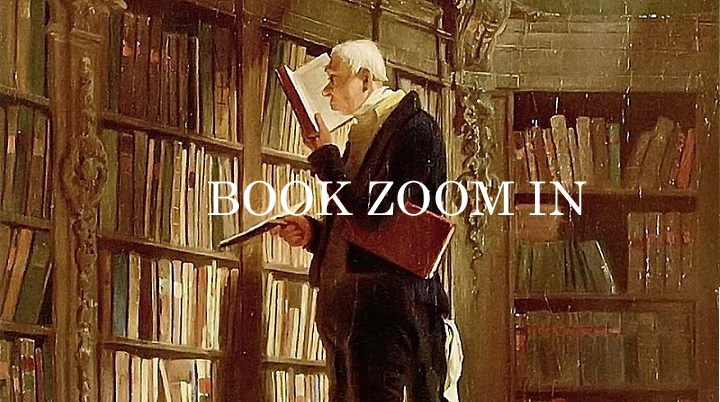ジェフリー・バラクロウ『中世教皇史【改訂増補版】』藤崎衛訳、八坂書房、2021年。
定価:3800円+税 341頁
英国の歴史家バラクロウ(1908〜1984)による『中世教皇史』(原題:“The Medieval Papacy”)は、中世の教皇権(papacy)を教義史の観点でも聖人伝のようでもない政治史の視点から論述した一冊です。
教皇という存在は教派によってとらえ方が異なり、時には対立の原因となってきました。そんな教皇という役職についてバラクロウ は、神学的問題に立ち入るのではなく、中世政治史の文脈で史料にもとづいた議論を展開します。つまり、教派主義や伝説から解放された世俗的な学問である歴史学に教皇の歴史をゆだねることで、行政や法の観点から教皇権が中世で果たした重要性を描きだそうとしているのです。その一例として、「ペトロが初代教皇である」というカトリックの主張は歴史的には3世紀にまでしか遡れないと述べられています。歴史学では「本当にペトロは初代ローマ司教であったか」という問いよりも、「いかに教会はペトロの権威を利用してきたか」という問いのほうが主な関心になることもあるのです。このように著者は、立場や解釈によらない客観的な事実に依拠して教皇という地位を探ることで、人類史上最も長く続いている組織であるカトリック教会の長の歴史を描出します。
は、神学的問題に立ち入るのではなく、中世政治史の文脈で史料にもとづいた議論を展開します。つまり、教派主義や伝説から解放された世俗的な学問である歴史学に教皇の歴史をゆだねることで、行政や法の観点から教皇権が中世で果たした重要性を描きだそうとしているのです。その一例として、「ペトロが初代教皇である」というカトリックの主張は歴史的には3世紀にまでしか遡れないと述べられています。歴史学では「本当にペトロは初代ローマ司教であったか」という問いよりも、「いかに教会はペトロの権威を利用してきたか」という問いのほうが主な関心になることもあるのです。このように著者は、立場や解釈によらない客観的な事実に依拠して教皇という地位を探ることで、人類史上最も長く続いている組織であるカトリック教会の長の歴史を描出します。
 は、神学的問題に立ち入るのではなく、中世政治史の文脈で史料にもとづいた議論を展開します。つまり、教派主義や伝説から解放された世俗的な学問である歴史学に教皇の歴史をゆだねることで、行政や法の観点から教皇権が中世で果たした重要性を描きだそうとしているのです。その一例として、「ペトロが初代教皇である」というカトリックの主張は歴史的には3世紀にまでしか遡れないと述べられています。歴史学では「本当にペトロは初代ローマ司教であったか」という問いよりも、「いかに教会はペトロの権威を利用してきたか」という問いのほうが主な関心になることもあるのです。このように著者は、立場や解釈によらない客観的な事実に依拠して教皇という地位を探ることで、人類史上最も長く続いている組織であるカトリック教会の長の歴史を描出します。
は、神学的問題に立ち入るのではなく、中世政治史の文脈で史料にもとづいた議論を展開します。つまり、教派主義や伝説から解放された世俗的な学問である歴史学に教皇の歴史をゆだねることで、行政や法の観点から教皇権が中世で果たした重要性を描きだそうとしているのです。その一例として、「ペトロが初代教皇である」というカトリックの主張は歴史的には3世紀にまでしか遡れないと述べられています。歴史学では「本当にペトロは初代ローマ司教であったか」という問いよりも、「いかに教会はペトロの権威を利用してきたか」という問いのほうが主な関心になることもあるのです。このように著者は、立場や解釈によらない客観的な事実に依拠して教皇という地位を探ることで、人類史上最も長く続いている組織であるカトリック教会の長の歴史を描出します。古代末期から中世初期を扱った第一章と第二章は、中世の教皇権へのイントロダクションのような役割を担っています。ローマ帝国が衰亡する一方でゲルマン勢力が勃興する西ヨーロッパを舞台とした教会の制度化過程が語られ、ローマの司教に過ぎなかった教皇が中部イタリアに領土を持つ世俗君主となり、西欧全体に教皇権を及ぼすようになった歴史が解説されます。
本格的に中世教皇史が論じられる第三章から、本書の独自性が遺憾なく発揮され、様々な新しい知見を提供してくれます。例えば、従来は「グレゴリウス改革」と呼ばれていた11〜12世紀の教会刷新運動を再吟味することで、教皇庁の官僚化や制度化の実際的流れを
決定づけたのは、グレゴリウス7世(在位:1073〜1085)ではなくウルバヌス2世(在位:1088〜1099)であったと主張します。他にも、「インノケンティウス3世(在位:1198-1216)時代に教皇権は絶頂期を迎えた」という教科書的説明が批判されることで、中世教皇権の青写真を描きなおそうとしています。日本の世界史の教科書でも教皇権の絶頂期はインノケンティウス3世と説明され、彼の時代以降の教会史はほとんど取り上げられません。ですが、中世教皇史に関する全体像が再検討されることで、これまでは軽視されてき
たインノケンティウス3世以降の時期が再評価され、従来は衰退と考えられてきたこの時代に教皇君主制が確立されたという著者の理論が展開されます。その結果、「アヴィニョン教皇庁」や宗教改革前夜の教皇史が見直されます。
決定づけたのは、グレゴリウス7世(在位:1073〜1085)ではなくウルバヌス2世(在位:1088〜1099)であったと主張します。他にも、「インノケンティウス3世(在位:1198-1216)時代に教皇権は絶頂期を迎えた」という教科書的説明が批判されることで、中世教皇権の青写真を描きなおそうとしています。日本の世界史の教科書でも教皇権の絶頂期はインノケンティウス3世と説明され、彼の時代以降の教会史はほとんど取り上げられません。ですが、中世教皇史に関する全体像が再検討されることで、これまでは軽視されてき
たインノケンティウス3世以降の時期が再評価され、従来は衰退と考えられてきたこの時代に教皇君主制が確立されたという著者の理論が展開されます。その結果、「アヴィニョン教皇庁」や宗教改革前夜の教皇史が見直されます。
『中世教皇史』は英国の読者に向けて書かれたため、西洋史の様々な知識が前提とされており、日本人の一般的な読者には難解な個所も少なくありません。義務教育で学んだ世界史の知識だけでは追い付かないかもしれませんが、改訂増補版は用語の注や豊富な図版により、こうした敷居の高さを解決しようとしています。また、索引や教皇一覧、文献案内が付録されており、さらなる勉強にも役立てることができます。
(石川雄一、教会史家)
(ここでご紹介した本を購入したい方は、ぜひ本の画像をクリックしてください。購入サイトに移行します)