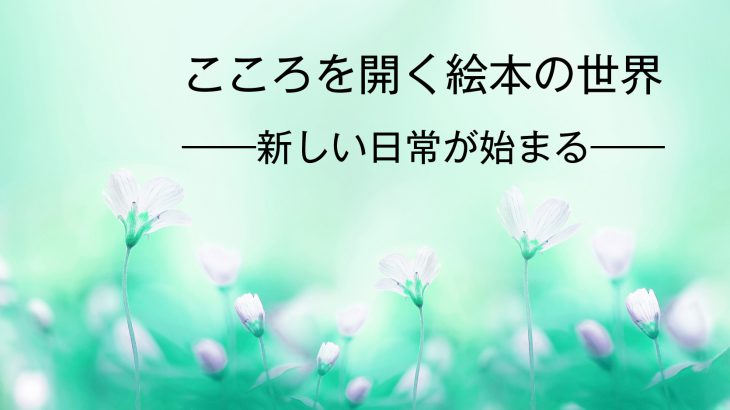山本潤子(絵本セラピスト)
消えるもの生まれるもの
私の住んでいる街は駅前の開発が進み、高層マンションがニョキニョキ建ち始めました。学生時代に住んでいたこの地域に再び引っ越してきたのは15年前、私鉄が地下を走るようになり踏切が消え、線路のあったところは遊歩道になりました。変わったのはそれくらいで、駅前は昔からの焼きトリ屋さんが朝から賑わい、小さなお店が隙間なく軒を連ね、一歩路地に入れば迷路のように立ち飲み屋さん、天ぷら屋さん、スナック、ワインバー、時々、喫茶店や花屋さん、よく分からない不思議なお店もありました。かつて東洋一と言われたアーケードの商店街には学生時代からの本屋も家具屋も洋品店も健在で、知っているお店を見つける度に第二の故郷に帰ってきたようでホッとするのでした。
しかし、しばらくすると駅前は様変わりしました。行きつけのお店は閉店や移転のお知らせが目立ち、100以上もあったお店は取り壊され、工事車両が行き交う建築現場となりました。駅前は賑わいも音も匂いもすっぽりと白いフェンスに覆われ、フェンスに掲げられた開発計画を横目にやり場のない哀しみに家路を急ぐのでした。
そんな鬱々とした気持ちの中で手にした1冊の絵本、この絵本もまた必要があって私の元に来てくれたのでしょう。
『THE DAM―この美しいすべてのものたちへ—』
デイヴィッド・アーモンド:文、レーヴィ・ピンフォールド:絵、久山一太:訳、評論社
イングランド最北の州、ノーサンバーランドに1981年に完成したキールダー・ダムがあります。ダム工事が始まる前、この美しい谷には多くの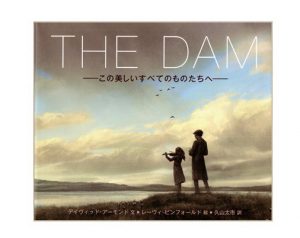 人々、音楽家たちが暮らしていました。音楽に溢れた谷だったと言われています。ダム建設のためにすべての住民は立ち退き、主人を失った家々が残されていました。
人々、音楽家たちが暮らしていました。音楽に溢れた谷だったと言われています。ダム建設のためにすべての住民は立ち退き、主人を失った家々が残されていました。
ダムが完成する直前、その谷に音楽家の父とヴァイオリン弾きの娘がやってきました。二人は打ち付けられた板を引き剥がし空き家に入るとヴァイオリンを奏で歌い踊りました。次の家も、また次の家も……。こうしてダムに沈む運命のすべての家々は最後の演奏によって音楽で満たされたのです。
「あるものは、すがたを消し、あるものは、水におおわれ、あるものは、ダムの底に沈んだ。」
やがて、谷は美しい湖に姿を変え、豊かな森林に囲まれ、多くの観光客が訪れるようになりました。再び訪れた父娘は失われた谷のあらゆるところに音楽が湧き上がり、響き渡り、また、離れていても思い出した時、夢を見ている時、あらゆる時に音楽が流れていることを語ります。「音楽はいつも、わたしたちの心にとどく。ダムでせきとめられても、わたした ちに流れこむ。」
ちに流れこむ。」
ダークな色調の美しい絵と心に沁みわたる散文詩、音楽のなんたるかを体感したような気がしました。
ある会でこの絵本を読みました。六十歳前後の男性も10人ほど、「絵本なんて……」という声が聞こえてきそうな雰囲気でしたが、背広を脱いでワインをお供に和やかに読み進めました。読み終えて私は古い集合住宅ビルが取り壊される時の話をしました。音楽家の友人が『ビルを葬る』イベントでこの父娘のように取り壊し直前の建物を音楽で満たしたのです。それはまるで神事のようで、雨風も日差しもビルを舞台に天地創造のドラマのようでした。
話し終えると、長年開発事業に携わってきた人から、その胸のうちを聞くことができました。開発には取り壊しも樹木の伐採も伴います。失うもの と生まれるものは背中合わせです。力任せにできることではなくいつの時代でも永遠の課題なのかもしれません。
と生まれるものは背中合わせです。力任せにできることではなくいつの時代でも永遠の課題なのかもしれません。
この絵本にはダム建設について否定的な表現は一切ありませんでした。美しい音楽が風になびく羽衣のように最後まで物語を覆っています。 描かれてないのに“住み慣れた家を後にする人々の哀しげな後ろ姿”が心に映し出される、また新しい絵本の読み方を体験しました。
ところで、私の街はといえば、新しくなった駅前の一角はこの街に相応しくないほど華やかになりました。改札を出て地上に上がると強いビル風がスカートの裾をめくり、高層マンションの隙間、狭くなった夜空に満月を探す人は私だけではありません。そして、モダンな開発エリアを抜けて家にたどり着くまでの間、何度消えた街を懐かしみ溜息をついたことでしょう。
しかし、年月の経過と共に新しい街は私の街になってきました。うれしいことに開発工事中立ち退いていたなじみのお店も形を変えて少しずつ戻ってきました。
開発はまだまだ続きます。私の家も計画地域に入っていて、いつまでここに住んでいられるか分かりません。同じ立場の街の人たちとこの流れの中で思いを分かち合い、これからを語り合う時間が増えてきました。逆らうことのできないこの波に気持ちよく乗っていこうと思います。心はいつだって満たされているのだから。
季節の絵本
『わたしのもみじ』岩間史郎:写真と文、ポプラ社
表紙の美しい写真と「わたしのもみじ」という言葉に、抱きしめるようにレジに向かいました。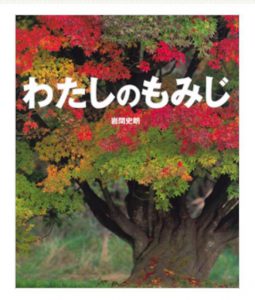
写真家は高原で一本の紅葉に出会いました。あまりの美しさに言葉が見つからず、体で感じようとしました。一枚だけ撮った記念写真、そこから写真家はこの紅葉のことが気になって仕方なかったのです。
海抜1000メートルの高原、四季折々に姿を変える大紅葉に写真家は何度も会いに行きました。寒くて凍えそうな雪の日、赤い冬芽が伸びる新緑の5月、虫たちの羽音が聞こえる開花、夏は虫たちにとってかけがえのない地球のような広い世界。季節ごとの写真は紅葉に出会った写真家の感動と驚き、そして一瞬にして心奪われたのでしょうか、深い愛や強い絆さえ伝わるのです。
なぜ、たった一本だけ高原にこの紅葉が残っているのか、地元の人は古い話をしてくれました。一人の若者が畑を作ろうと開墾を始めたけれど、この大きな紅葉が気に入り残すことになったと。50年前は「若者のもみじ」だったのです。
ある日、写真家は「今日は、であうことができる」と感じ、もみじの前に立ちました。
「1分2分……5分、にじです、 、 、 」写真家は気持ちが通じ、大紅葉にかかる虹を見ることができました。
紅葉に出会ってから10年、誰もいない静かだった高原の紅葉の周りはとても賑やかになりました。たくさんの人にとっても「わたしのもみじ」になったのです。
私にも「わたしのもみじ」があります。私の生まれた家には桐、柿、紅葉、無花果、柘植やツツジ、南天など、たくさんの庭木がありました。庭木といっても小さかった私にはとても大きな木として記憶に残っています。無花果と渋柿は祖母が加工して美味しいおやつになり、庭の木々は私の遊び場の延長にありました。
中でも紅葉は葉の多い季節にはかくれんぼに丁度良く、とっておきの場所でした。なかなか探してもらえない時の小さな不安も、私の紅葉は知っ ているでしょう。
ているでしょう。
雪国の庭木は雪の重さで枝が折れないように、初雪の前に雪吊りをまといます。私の紅葉も大事にしてもらっていたはずなのに、真っ直ぐに伸びることができませんでした。道路近くにあったため除雪の雪圧がかかり年々幹が曲がって成長したのです。雪圧に耐えたその紅葉は盆栽のように見事な形だと造園業者さんから所望の声がかかったこともありました。
すっかり忘れていた「わたしのもみじ」、誰にとっても心通わせた木々があるかもしれません。毎年、この季節にこの絵本を開きます。声に出して読んでいると、途中から懐かしい『紅葉』の歌が聞こえてくるようです。
(ここでご紹介した絵本を購入したい方は、ぜひ絵本の画像をクリックしてください。購入サイトに移行します)
東京理科大学理学部数学科卒業。国家公務員として勤務するも相次ぐ家族の喪失体験から「心と体」の関係を学び、1997年から相談業務を開始。2010年から絵本メンタルセラピーの概念を構築。