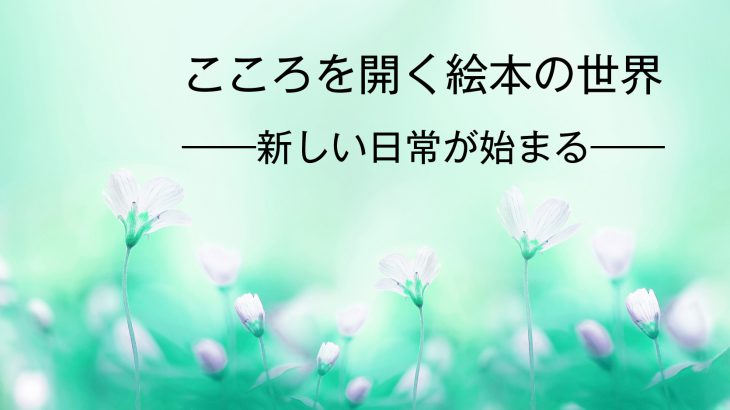山本潤子(絵本セラピスト)
それぞれの役割
新型コロナの影響で母とは1年半以上も会っていません。「会いたい、会いたい」と綴られた手紙は、もう20通を超えました。毎日の電話では喜怒哀楽、さまざまな感情が飛び出しますが、手紙に認められた言葉はどこか自分を俯瞰しているように感じます。「私は何のためにこうして生きているのだろうか」「生き続ける意味を探しても今は何も見出せない」、そんな問いかけを繰り返している母に着地点を示すことなど到底出来ません。世界中の思想家や偉人たちも同じように自問自答し続け、それは人類がある限り終わることがないのでしょう。
私自身、考える間もなく目の前にやりたい事がいくらでもあった若かりし頃、そして、仕事や家族も増えてやらなければならない事が山積みの年代もありました。今はといえば、やりたい事なのかどうか選択が許される年代なのかもしれません。いつか母のように思い悩む日がくるでしょう。そんなことを考えながらレオ・レオニの作品の中からこの1冊を紹介したくなりました。
『フレデリック ちょっと かわった のねずみの はなし』
作:レオ・レオニ、訳:谷川俊太郎、好学社
冬を迎える牧場の古い石垣の周りで、野ネズミたちは冬支度に励んでいます。昼も夜も休まず集めているとうもろこしや木の実は冬籠の大事な食料です。
ところがフレデリックだけは違います。じっと牧場を見つめるだけ、動かずに眠っているようにも見える日もあるのです。仲間の ネズミにどうして働かないのかと尋ねられ、「光や色や言葉を集めている」とフレデリックは答えました。
ネズミにどうして働かないのかと尋ねられ、「光や色や言葉を集めている」とフレデリックは答えました。
やがて牧場に雪が降り始め、野ネズミたちは石垣の隠れ家に篭り、集めた食料を食べながら噂話も楽しく過ごしていました。でも、食べ物はだんだん底をつき、おしゃべりを楽しむ気にもなれません。そんな時、野ネズミたちはフレデリックの言葉を思い出しました。集めていた光や色や言葉はどうなったのかと。
フレデリックは野ネズミたちに目をつむるように言い「おひさまをあげよう」と温かい光をイメージし誘導しました。すると、凍えていた仲間たちは暖かくなったのです。次は色です。フレデリックの語る草花の色は心の中で塗り絵のようにはっきりと見えるのです。最後に言葉、フレデリックは舞台俳優のように野ネズミたちひとりひとりが四季折々にどんな役割を果たしているのかを語り始めました。そして、それが一つ欠けても増えてもちょうど良くはないのだと締めくくったのです。野ネズミたちは驚き拍手喝采です。
読んでいて途中までは「アリとキリギリス」のように感じますが、読み終えると全く異なる教訓が見えてきました。
まず、野ネズミたちは働かないフレデリックを非難することはありませんでした。むしろフレデリックの集めていたものを楽しみ
 にしていたようにも思えます。みんなで同じ事をしなくても良いのです。そして、フレデリックの披露する見えないものによって温もりや色彩を感じ、寒さやひもじさを忘れてしまいます。厳しい冬の間、食べる物がなくては生きていけません。でも、食べる物があっても春を待つ間に心が枯れてしまうかもしれません。雪国で暮らしたことのある私には、この野ネズミたちの心情がよくわかるのです。レオ・レオニは芸術家である自身の役割を問うだけでなく、誰もがかけがえのない「ひとり」なのだと伝えているように思いました。
にしていたようにも思えます。みんなで同じ事をしなくても良いのです。そして、フレデリックの披露する見えないものによって温もりや色彩を感じ、寒さやひもじさを忘れてしまいます。厳しい冬の間、食べる物がなくては生きていけません。でも、食べる物があっても春を待つ間に心が枯れてしまうかもしれません。雪国で暮らしたことのある私には、この野ネズミたちの心情がよくわかるのです。レオ・レオニは芸術家である自身の役割を問うだけでなく、誰もがかけがえのない「ひとり」なのだと伝えているように思いました。
特に最後の詩の朗読でそれがはっきり見えたように思います。表現者としてのフレデリックだけでなく、せっせと食料を集めた野ネズミたちそれぞれもまた、かけがえのない役割を担っているということを。
先月、久しぶりに友人の演奏会がありました。4人の演奏家が異なる楽器でユニットを結成しての初演でした。すばらしい演奏と開催への決断の思いに胸が熱く心が震えました。 どんなに準備しても緊急事態と言われれば演奏会は中止になり、それは仕方ないこと。チケットを購入した観客側は「ああ〜残念」ですむかもしれませんが、その日のために最高のパフォーマンスのために準備してきた表現者にとっては、残念では終われないはずです。そんなことがこの1年半の間、何回も繰り返されているのです。
一人の演奏家の呟きが耳に入りました。「食べることに必死なのに、音楽が必要ですかと言われることがある」と。そんな厳しい言葉の中での演奏会開催だったとは夢にも思いませんでした。
レオ・レオニは自らもこのような言葉を浴びせられながらも表現活動を続けてきたのでしょうか。数年前に出会った絵本作家さんはちぎり文字作家でもあります。ちぎり文字のワークショップを主催した時に語られた言葉を私は今でも大切にしています。
「自分の表現方法を見つけられた人は幸せだと思います。」
自分だけでなく相手の表現にも興味を持ち楽しむことができたら、どんなにか幸せなことでしょう!
季節の絵本
『ことしのセーター』石川えりこ:作/絵、福音館書店
衣替えの季節、冬を前に小さくなったセーターを編み直します。幼い三人の姉妹弟はバラバラに分解される身ごろや袖を小島に見立て、さっそく遊び始めます。そして、その小島の一枚一枚をほどき一本の毛糸に戻す作業は、いつの間にか楽しい競争になり どんどんスピードアップしました。ほどいた毛糸は湯気の立つヤカンの蓋の穴に通すと、クネクネした編みぐせは蒸気を浴びて真っ直ぐに伸びます。元の形に戻らないうちにしっかり巻いて、いくつもの丸い毛糸玉ができました。
どんどんスピードアップしました。ほどいた毛糸は湯気の立つヤカンの蓋の穴に通すと、クネクネした編みぐせは蒸気を浴びて真っ直ぐに伸びます。元の形に戻らないうちにしっかり巻いて、いくつもの丸い毛糸玉ができました。
新しい毛糸を足して、おばあちゃんとお母さんは毎日セーターを編みます。家族が集まるこたつを囲んで、いつものようにお風呂の順番を待ちながら、子どもたちの様子を横目で追いながら編み続けます。
そして、ある朝、ついに三人の世界で一枚だけの今年のセーターが完成しました。
古いセーターが一本の毛糸に変わっていく作業を読みながら、鼻の奥で懐かしい匂いが漂ってきました。カビ臭いような湿気を帯びた毛糸の匂いです。絵本の子どもたちはお手伝いしながら楽しい遊びを見つけていきます。遊びながら早くほどく方法を工夫し、仕組みや作業工程、技術や科学を学んでいくのでしょう。半世紀前には当たり前だった光景にまるでそこにいるかのような錯覚、体が覚えているということでしょうか、毛糸の山を前に腕が勝手に動くような不思議な感覚になりました。
絵本を読み終えて、セーターにまつわる記憶がいくつも甦りました。子どもの頃、母は家で洋裁をしていました。ミシンの音が夜遅くまでカタカタと聞こえ、「まだ? もう寝ようよ」と、母を困らせた事をよく覚えています。母がセーターを編んでいた記憶はありませんが、絵本のように袖が短くなったセーターをほどいて毛糸玉にする作業は家でもやっていました。その毛糸玉を少し離れた家に持っていき、新しく編み直してもらうのです。その家には編み機があってシャーシャーと左右に手を動かすだけで、下から編まれた物がゆっくりと出てくるので本当に不思議でした。
小学校3年生の頃、とても綺麗な青紫色の新しい毛糸でカーディガンを編んでもらいました。編み直しではないことも嬉しくて「見て、見て!」という気持ちで毎日のように着ていたことを覚えています。そのカーディガンは小さく着られなくなっても編み直しされることが嫌で、結局、従姉妹へのお下がりになったのでした。
私は子どもが小さい頃、睡眠時間を削ってよく編み物をしました。子どもを寝かしつけた後、編み物の本を見ながら、今夜は 袖、明日は前身ごろと計画を立てるのですが、赤ちゃんの小さなパーツはあっという間に編み進んでしまいます。「もうちょっと、もうちょっと」と欲張って夜更かし出来たのは若かったからに違いありません。保育園で「可愛いわね」と保育士さんに褒められた時の嬉しさの後ろには「子どもを預けて仕事していてもこんなに大事にしています」と、自己弁護したい気持ちもあったのかもしれません。当時を思うとそんな私に労いの言葉をかけてあげたくなります。
袖、明日は前身ごろと計画を立てるのですが、赤ちゃんの小さなパーツはあっという間に編み進んでしまいます。「もうちょっと、もうちょっと」と欲張って夜更かし出来たのは若かったからに違いありません。保育園で「可愛いわね」と保育士さんに褒められた時の嬉しさの後ろには「子どもを預けて仕事していてもこんなに大事にしています」と、自己弁護したい気持ちもあったのかもしれません。当時を思うとそんな私に労いの言葉をかけてあげたくなります。
私が編んだ子どものセーターもお下がりに出しました。編み直すという方法もあったけれど世界に一枚だけのちょっとこだわった作品、あみ棒を動かしていた時の気持ちや小さな腕を袖に通した時の情景を思い出すと、バラバラにして編み目をほどくことなどできませんでした。
小さな一目一目を編み進めて出来上がる編み物は『気持ちも一緒に編み込んでいる』ようで、なんだか特別な物に思えてきました。
また、毛糸を無駄にしないで形を変える「編み直し」という文化、そこにはお気に入りを失う喪失感もあれば、新しく生み出す創作意欲も達成感もあります。家族ぐるみの共同作業は遊び名人によって、知らず知らずに手芸も科学も段取りも学ぶ貴重な体験の場なのだと思います。生活文化遺産のようなこの絵本、衣替えの頃に毎年読み続けていきたい絵本です。
今年は寒くなる前に毛糸に触れてみようかしら、今度は私自身のために。
(ここでご紹介した絵本を購入したい方は、ぜひ絵本の画像をクリックしてください。購入サイトに移行します)
東京理科大学理学部数学科卒業。国家公務員として勤務するも相次ぐ家族の喪失体験から「心と体」の関係を学び、1997年から相談業務を開始。2010年から絵本メンタルセラピーの概念を構築。