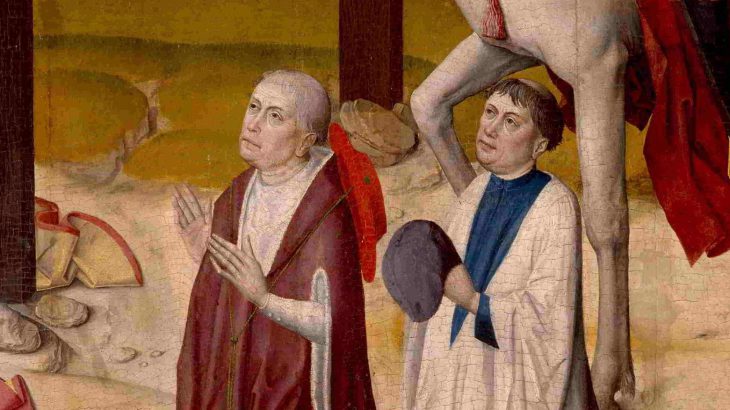倉田夏樹
彼は革新を欲したが、しかしやがて来たような、
全西洋の教会の統一を永久に打ち毀すような
改革を欲したのではなかった
――ヤスパース『ニコラウス・クザーヌス』
「中世」(Moyen Age / Mittelalter)という時代の定義は難しい。14世紀のペトラルカ(Francesco Petrarca, 1304-1374)などイタリアの人文主義者(Umanista)によってこの時代概念「中世」(Medium Tempus)は提唱され、イタリアの歴史家ベネデット・クローチェ(Benedetto Croce, 1866-1952)の「歴史を思惟することは確かにこれを時代区分することである」(『歴史叙述の理論と歴史』〔Teoria e storia della striografia, 1920〕)という言葉は、「すべての真の歴史は現代史である」(同書)と同様有名だ。ドイツ人のプロテスタントの歴史家・人文学者(Humanist)クリストフ・ケラリウス(Christophus Cellarius, 1638-1707)は、歴史の三区分法(古代、中世、近代〔現代〕)の提唱者として知られる。ケラリウスは、337年のコンスタンティヌス帝の死(西ローマ帝国滅亡)から1453年のコンスタンティノープルの陥落(東ローマ帝国滅亡)まで、4~15世紀の約1100年間を「中間の時代(Medium Aiuum)/中世」と定義し、中世を「暗黒時代/暗黒中世」(finsteren Zeiten / finstere Mittelater)と名づけた。この中世の範囲は、近世以降のヨーロッパ世界で定着し、この定義を基本線としながら、歴史家によってそれぞれ独自に定義されることとなった。日本史では、鎌倉時代から戦国時代まで、12~16世紀の約400年間を中世と呼ぶのが定説で、同じ「中世」でも、西洋史と日本史ではこれだけの時代の幅がある。
フランス・アナール学派の中世史家ジャック・ル=ゴフ(Jacques Le Goff, 1924-2014)は、19~20世紀における、中世の伝統的な時代区分法、476年(オドアケル王による西ローマ帝国滅亡)から1492年(コロンブスによるアメリカ大陸の発見/スペイン・キリスト教勢力がイスラーム勢力からグラナダを奪いレコンキスタが完成)まで、を支持せず、「歴史は連続した流れ」と呼び、断絶ではなく継承と転換という考えを重視するとしている(『中世とは何か』〔A la recherche du Moyen Age, 2003〕)。ル=ゴフは「暗黒中世」/「理想化された中世」、双方のイメージを遠ざける。イタリア・ルネサンスを研究したスイスのカルヴァン派の歴史家ヤーコプ・ブルクハルト(Jakob Burckhardt, 1818-1897)は、ル=ゴフと異なり「断絶論」を唱え、中世を「蒙昧」とし、15世紀の「イタリア・ルネサンスから近世が始まる」と境界を設けた。ル=ゴフは、「複数のルネサンス」という言い方をし、中世の始まりと終わりを明確に定義しなかった。ベルギー人の中世史の大家アンリ・ピレンヌ(Henri Pirenne, 1862-1935)は、「ピレンヌ・テーゼ」で「中世の始まり」を、イスラームが地中海を制覇した8世紀中葉以降としたが、「中世の終わり」の方は、歴史家によって解釈が大いに分かれるところであるとした。「中世の終わり」は、東ローマ帝国の滅亡、ルネサンス、レコンキスタ、大航海時代、ルター宗教改革など、史家によって大いに判断が委ねられる。
ドイツのルター派の歴史家レオポルト・フォン・ランケ(Leopold von Ranke, 1795-1886)もまた、ヨーロッパ世界のスタンダードとなった『世界史概観――近世史の諸時代』(Über die Epochen der neueren Geschichte, 1854)で、ルターによるドイツ宗教改革(1517年)の前(第五期〔14世紀及び15世紀〕)までを中世とした。ルターより、ヨーロッパ近世が始まると解釈する。近世が始まる同書第六節を「宗教改革および宗教戦争の時代」とし、「宗教改革によって宗教戦争(ドイツ農民戦争、ネーデルラント=フランスの宗教戦争、ドイツ三十年戦争)も始まった」という道筋を冷静に示す。同じく冷静な史観から、中世を「暗黒時代」と見なすことをしなかった。
ヨーロッパ中世と言えば、イギリスの『アーサー王物語』、イギリス、デンマークの『ベーオウルフ』、フランスの『ロランの歌』、ドイツの『ニーベルンゲンの歌』、スペインの『エル・シッド』、アイルランドの『オシアン』、アイスランドの『エッダ』といった叙事詩(英雄譚)、騎士道物語などが想起されるが、「カトリック的中世」の世界もまた強く想起される。この時代には、修道院の形成・発展があり、学問で言えばアリストテレス哲学を深化させたスコラ神学が隆盛し、宗教的行為としては、イタリア、ドイツ、スペインなどで神秘主義の実践がなされ、神秘主義の著作も多数生まれた。その一方で、負のイメージも大きい。
現代のカトリック教徒は非信徒との会話の中でしばしば、「キリスト教徒は十字軍をもってイスラームを攻撃・排斥したではないか。魔女狩りをしたではないか?」と批判・糾弾される場面に遭遇することがある。十字軍(キリスト教徒による戦争)や魔女狩り(「正統」キリスト教徒による一方的な異端審問)という不寛容な負のイメージは、大航海時代以降のキリスト教勢力による植民地主義(帝国主義と戦争)、人種差別、奴隷制などの容認・看過などと同じく、現代においても、キリスト教が大いに批判される(べき)ところである。「近代の産物」と言われるプロテスタントの信徒は、「十字軍や魔女狩りはプロテスタントとは関係ない」とかわすことができるが、カトリック信徒は、2000年に亘る伝統に対する説明を負う責任があり、「弁明」が難しいことが多々ある。中世は、カトリック教徒にとっての栄光の時代(「信仰の時代」)でもあり、「泣きどころ」(「暗黒時代」)でもある時代だ。
「暗黒中世」の時代区分について、キリスト教史、教会史の分野ではどうであろうか。多くのプロテスタント史家によって書かれた「キリスト教史」の通史のほとんどは、ルター宗教改革から近世を始める。宗教改革の定義自体も実は大変難しく、イギリスのウィクリフ(John Wycliffe, 1330?-1384)、チェコのヤン・フス(Jan Hus, 1369?-1415)による「宗教改革」をどう位置づけるか、という問いがプロテスタントの中でも依然として残っている。アメリカ人の改革派(カルヴァン派)の教会史家ウィリストン・ウォーカー(Williston Walker, 1860-1922)は、長い間、欧米の大学や神学校の標準的教科書となった『キリスト教史』(A History of The Christian Church, 1918)で、ウェールズ南部生まれの聖パトリック(Patrick, 389?-461)のアイルランド宣教(432年)から、アルプス以北におけるルネサンスの受容までを中世期に収め、ルターから近世を始める。ルターにヘブライ語を教えた人文学者ヨハネス・ロイヒリン(Johannes Reuchlin, 1455-1522)は、「源泉に戻ろうとするルネサンスの願望」に倣ってヘブライ語を学習したとウォーカーは書く。同じく、ルターに影響を与えた神学者でプロテスタント最初の組織神学書『ロキ・コンムネス(神学總論)』(Loci communes rerum theologicarum, 1521)を著したフィリップ・メランヒトン(Philipp Melanchton, 1497-1560)、オランダのカトリックの司祭・人文学者デジデリウス・エラスムス(Desiderius Erasmus, 1466?-1536)、そしてニコラウス・クザーヌス(Nicolaus Cusanus, 1401-1464)もまた中世期に入れている。スロヴァキア系アメリカ人のルター派の教会史家でのちに正教会に改宗したヤロスラフ・ペリカン(Jaroslav Pelican, 1923-2006)は、年号があまり書かれないことで有名な大著『キリスト教の伝統――教理発展の歴史』(The Christian Tradition : A History of the Development of Doctrine, 1971)では、本書の特殊な構造上時系列が複雑で読み取りにくいが、おおむね、「アウグスティヌス的総合」(ペリカンは中世神学の成長をこう呼んだ)が始まる5世紀(アウグスティヌス後〔430年没〕)から16世紀まで中世とする。クザーヌスも、「中世後期」に登場する。また、中世を「暗黒時代」と呼ぶのではなく、「信仰の時代」と呼んだ。キューバ系アメリカ人のメソジスト派の教会史家フスト・ゴンサレス(Justo Gonzalez, 1937-)は、政治経済・社会的現実の中に教会史を位置づける『キリスト教史』(The Story of Christianity, 1984)で、アウグスティヌスの死(430年)から西ローマ帝国の滅亡(476年)までの5世紀から西方の大シスマ(教皇庁の分裂)の1417年まで、5~15世紀を中世とし、宗教改革前史、ルネサンスと人文主義、大航海時代に際しての植民地主義のキリスト教から近世を始め、非西洋・非白人・被抑圧者のルーツの歴史家らしく、西洋による中南米、アフリカの植民地支配についての頁が多い。ルクセンブルク人のカトリックの教会史家ヨセフ・ロルツ(Joseph Adam Roltz, 1887-1975)は、主著『教会史』(Geschichte der Kirche, 1956)で、「西洋の支配者としての教会」という自己批判的な言説をもって「中世の教会」の章を始め、東西教会の分裂(395年)からダンテとクザーヌスまでを中世区分に入れ、クザーヌスを「中世的な意味で純粋に敬虔でありながら、あらゆる場合に彼は特徴のある近代的な思想態度を示す」としている。
中世の時代区分について、前提が長くなってしまった。本稿の主人公は、幾度と名前を変えた、カトリック教徒が言うところの都市コンスタンティノープル(330~1453年)である。ちょうど、「中世」と時を同じくする都市だ。もう一人の主人公は、中世コンスタンティノープルにあったドイツ人の哲学者であり、カトリック枢機卿(高位聖職者)であったニコラウス・クザーヌスである。西洋史と東洋史の間、ペルシャ、ギリシャ、スラヴ、ローマの間、中世と近世の間、「暗黒時代」中世の秋にあった都市と人の出来事を通して、宗教的不寛容と寛容、諸宗教対話とエキュメニズムの事例について考えてみたい。
コンスタンティノープル(コンスタンティヌス帝の都)は、324年にコンスタンティヌス帝(1世)がリキニウス帝を破ってローマ帝国唯一の正帝になったことを記念して、デルポイの神託によってビュザス王によって建てられたと伝えられる旧ギリシャ植民市ビザンチオン(Βυζάντιον/324~330年のラテン名はビザンチウム)を改名させた、ボスポラス海峡、金角湾、マルマラ海に面する港町(330年誕生)である。その後、1453年まで、東ローマ帝国(ビザンティン帝国)の首都であり続けた。ローマに次ぐ第二位の司教区(「第二のローマ」)となった。カトリック教徒にとっては馴染みのある地名で、4世紀にはこの地で2回の公会議が開かれ、ニケア信条(325年)、ニケア・コンスタンティノープル信条(381年)という典礼文で現代に伝わる(「ローマ式典礼」の色彩が強い使徒信条と異なり、カトリック、プロテスタントの諸派、正教会にも共通する信条である/プロテスタントの多くではニカイア・コンスタンチノポリス信条、正教会では信経と呼ばれる)。1453年以降は、イスタンブール(中世ギリシャ語「町へ」〔εις την Πόλιν〕の訛りと言われる)に名前が変わり、1923年までオスマン帝国(トルコ)の首都であった。
この多くの名を持つ街は、前述したように前7世紀にギリシャ人が入植した市が起源だが、アケメネス朝の進出により前478年までペルシャの支配下に入り、その後、1世紀にはローマの属州として編入される。要衝にある国境の街として、コンスタンティノープル(330年)の名に至るまでにも、様々な経緯があり、ギリシャ、ペルシャ、ローマと、持ち主が次々と変わり、様々な文化・言語・宗教を経験した。十字軍の遠征の際には、キリスト教徒とムスリム、大いに略奪し取り合うところとなった。「東西の架け橋」「東西交易の結節点」「国際都市」「帝国の縮図」「七つの丘の街」「革命劇場」「寛容なる都」などと異名を持つ所以である。国境・周縁にあり次々に名を変えた都(港町)としては、サンクトペテルブルク(ペトログラード、レニングラード)とも似ているであろう。
コンスタンティノープルがキリスト教徒にとっての哀史として最も語られる日は1453年5月29日である。この「キリスト教徒の都」を是が非でも奪取して、イスラーム・オスマン帝国の都に造り変えようと決意し、精鋭軍団イェニチェリ(新軍の意)と近代兵器の大砲(ナポレオン戦争時の性能と同じ水準と言われ、東ローマ帝国に購買を持ちかけかれるが貧窮下で買うことができず、それがそのままオスマン帝国の武器となった)をもって「世界史的転換」を成し遂げたのはファーティヒ(征服者)と呼ばれたオスマン帝国第7代スルタン・メフメト2世(Mehmet II, 1432-1481)であった。コンスタンティノープル攻略時21歳。1451年に幼帝を殺して即位したので「征服者」と呼ばれた。東ローマ帝国(ビザンティン帝国)最後の皇帝コンスタンティノス11世(Constantinos XI Dragases Palaeologus, 1404-1453)は、崩壊寸前のコンスタンティノープルからローマ教皇へ東西両教会統一と引き換えに援軍を要請するが、5月29日の総攻撃に間に合わず、コンスタンティノープルの城門はイェニチェリに突破され、市街での白兵戦の中で戦死した。こうして、コンスタンティノープルは陥落し、東ローマ帝国は滅亡した。オスマン帝国は首都をエディルネからコンスタンティノープルに遷し、やがてイスタンブールと呼ばれるようになった。東ローマ帝国の象徴アヤ・ソフィア(ハギア・ソフィア/「聖なる叡智」)大教会、及び隣接するギリシャ正教会の総主教座はモスクに改装された。メフメト2世は、キリスト教徒の最低限の権利を守る義務を果たしたが、以後のスルタンは、キリスト教徒たちにさほど寛容ではなかった。教会堂は一つ一つ没収されていった。
メフメト2世は、その後も西に東に征服を進めた。特に西方への進出は帝国の悲願で、セルビア、アルバニアと続いて、アドリア海、エーゲ海の覇者・ヴェネツィアと戦い、地中海を東から取り囲んで、イタリア南部、シチリア島・パレルモへの進出を目前とした。しかし1481年、メフメト2世は急死する。オスマン帝国のイタリア進出は永遠に果たされぬ夢となった。
時代を少し遡って1437年、陥落しつつあるコンスタンティノープルに、救援のため教皇庁よりローマ教皇エウゲニウス4世(Eugenius IV, 1383-1447)の使節団が派遣された。西方教会にとっても、イスラームによる東方教会の「危機」は看過できない歴史的出来事であった。使節団は、東西教会合同を一つの議題とするフェラーラ=フィレンツェ公会議(1438年)参加を名目に東ローマ皇帝ヨハネス8世(Johannes VIII Palaeologus, 1390-1448)とビザンティン教会総主教ヨセフ2世(Joseph II, 1360-1439)の脱出に成功し、イタリアに帰還した。その教皇使節団に、東西教会の和平工作に奔走していたドイツのカトリック神学者ニコラウス・クザーヌスがいた。1437年から1438年まで、クザーヌスはコンスタンティノープルに滞在した。
「学識ある無知」(docta ignorantia/ボナヴェントゥラにも見出されるが、実はアウグスティヌスの言葉である〔エチエンヌ・ジルソン、マルティン・グラーブマン〕)「対立物の一致」(coincidentia oppositorum)などの思想で知られる神学者で、1448年には、教皇のブレーンである枢機卿に任命される。1453年のコンスタンティノープル陥落の報は、ヴェネツィア、グラーツを経由してもたらされ、クザーヌスは枢機卿の立場で、ローマかブリッサノーネ(ブリクセン)で知ることになる。クザーヌスはこの報を聞いて大きなショックを受けるが、キリスト教徒の中に反イスラーム感情が熱狂的に高まる中、陥落直後に『信仰の平和』(De pace fidei, 1453)という書物を著す。『信仰の平和』にはこうある。
最近コンスタンティノープルにおいてトルコ王の手できわめて残虐なことがなされたと伝えられたが、かつてその地を訪れたことのあるある人がその報に接したとき、神への熱愛に向けて誘われた。そして彼は、深甚な悲嘆に打たれつつ、万物の創造者に祈って、諸宗教の差異ある儀礼のゆえにきわめて凶暴なものになっているこの迫害を、万物の創造者の慈悲によって制止して下さるように願った。数日後のこと、熱意に満ちた彼に――おそらくは長時間にわたる瞑想のゆえにであろうが――ある観が現れた。(中略)それらの宗教のあいだに一つのかなりの実現容易な調和を見出しうること、さらにその調和を通して目的に適った誠実な手段によるならば、宗教のなかに永続的な平和を打ち建てることを彼はその観から見出したのである。(中略)
主は、諸宗教のあらゆる差異があらゆる人間の共通な一致によって唯一のまったく侵しがたいそれ〔宗教〕へと調和的に帰一させられるということに満足しておられる。
ニコラウス・クザーヌス著『信仰の平和』八巻和彦訳
『中世思想原典集成 第17巻』584、590頁
以後のカトリック普遍主義の基軸となった「対立物の一致」の思想をもって、この時代の「征服者」であるイスラームと対立することを求めなかった。この時代のキリスト者から、ここまで胆力ある人物を見つけ出すのは困難である。中世哲学史家の大家エチエンヌ・ジルソン(Étiennne Gilson, 1884-1978)は、「実を言うと、当時の状況では、キリスト教国が壊滅に瀕していることをさとるのは、むずかしいことではなかった。しかし、それでもニコラウス・クザーヌスは、人々がかれらの争いをとるにたらぬ哲学的、神学的な意見の相違と見なすようになりさえすれば、惨事は避けられることができるという希望的観測をしていたのであった」(『理性の思想史』)と評している。クザーヌスは、イスラームとの対話の思想をその後も持ち続け、1461年には、『コーランの精査』(Cribratio Alkorani, 1460-1461)を著す。
コーランに、美しさ、真実、明快さが見出された場合、それは最も明るい福音の光によってでなければならない。この事実は、福音を読んだ後にコーランに向きあった人なら誰もがこれを認めるところである。この世界への侮辱と未来の時代への選択はどこから来るのであろうか? 義の説得と慈悲の働きから、あるいは、神への愛と隣人愛からであろうか?
ニコラウス・クザーヌス著『コーランの精査』拙訳
Nicolai de Cusa, Cribratio Alkorani I, p.50
「構想の壮大さと強靭な意志」(八巻和彦)をもって、「敵」ではなく「同じ啓典の民」として、イスラームの聖典『コーラン』を研究し、「対立物の一致」「普遍的和合」の基盤思想に基づき、知イスラーム派のキリスト者としてイスラームとの対話・共生をしようとした。クザーヌスは一個の哲学者・神学者として信仰についての思索を行ったが、1437年に枢機卿になってからは特に「教皇庁外交官」(マンフロート・グローテン)として、教会のためにイスラームとの対話的・協和的な働きをした。クザーヌスの隣人に対しての思想「対立物の一致」と「普遍的和合」(concordentia catholica/当然、「カトリック的和合」と読みとることもできる)は、以後のカトリシズムの基盤思想になり、第二バチカン公会議にも色濃く見られ(イヴ・コンガール)、現代に至るカトリシズムをかたどっている。
前述したとおり、イスラームに対するクザーヌスのこうした思想が当時15~16世紀のキリスト者の大勢だったかというとまったくそうではない。ローマ・カトリックの内部でも、大いに反イスラームの感情が噴出した。1453年のオスマン帝国によるコンスタンティノープル征服後、1492年にはレコンキスタ(スペインにおける対イスラーム国土回復運動)が起こった。ドイツの神学者ルートヴィヒ・ハーゲマン(Ludwig Hagemann, 1947-)は『キリスト教とイスラーム――対話への歩み』で、中世(15世紀)のクザーヌスと近世(16世紀)のマルティン・ルター(Martin Luther, 1483-1546)を対比する。ルターはコンスタンティノープル陥落後の反イスラーム思想が高まった時代に、クザーヌスと同じくドイツで生まれる。両者ともカトリックの聖職者になる。ルターはクザーヌスより約80年後である。
ルターが、雄弁な説教家、精緻な聖書解釈者、激しいそして優れた宗教活動家であることは、誰もが認めるところだ。同時に、プロテスタントの諸教会が各個の国家と結びつきナショナリズムを高揚させる歴史的傾向があることも定説となっている。ルターは「近代ドイツ精神の先駆者」として愛国者に支持され、1930年代にはアドルフ・ヒトラー(Adolf Hitler, 1889-1945)によって、「ドイツ・キリスト者」(Deutsche Christen)というナチズムとルター派を融合させた「キリスト教」が発明され、教会から、旧約聖書全巻と新約聖書のヤコブ書、パウロ書簡、アウグスティヌスの原罪論など、非ゲルマン要素・ユダヤ的要素が徹底的に排除された。教会の香部屋係の息子であったカトリックの哲学者マルティン・ハイデガー(Martin Heidegger, 1889-1976)も、同じくカトリックの政治神学者カール・シュミット(Carl Schmitt, 1888-1985)も、「ドイツ・キリスト者」に改宗し、ナチスのイデオローグ(思想的扇動者)となった。
ルター自身、特定の異民族・異教徒に対して排外的な思想を含む著作を遺している。『トルコ人に対する戦争について』(Vom kriege wider die Türcken, 1529)でムスリムに対して、『ユダヤ人と彼らの嘘について』(Von den Jüden und jren Lügen, 1543)でユダヤ人に対して、排外主義的・差別的とも受けとれる言説をしている。「ドイツ・キリスト者」の異民族・異教徒排斥思想は、これらの著作を「典拠」とした。「ルターからヒトラーの線」について、ドイツは勿論、欧米諸国で、ルター派、他のプロテスタントの研究者による「自己批判的な」研究がなされているが、日本では、教会でも学界でも、このテーマは話題にすることすらタブーと化している。タブーがあると却ってそれに注目が集まり、思想が先鋭化し「歴史の反復」がなされる怖れがあることを西洋文明は知っている。近年のドイツでは、「批判的な研究の史料として」、ヒトラーの『わが闘争』(Mein Kampf, 1925-1926)が発禁を解かれて、批判的な注・解説を付けた上で出版されるようになったほどだ。
最近の日本でも、プロテスタント(カルヴァン派)の研究者である宮田光雄氏が『ルターはヒトラーの先駆者だったか――宗教改革論集』(新教出版社、2018年)という本を出版した。「ルターからヒトラーの線」については終章において触れられているが、宮田氏は日本のプロテスタント学者の大家であるから、立場上、教会内にも大いに影響力があり、このテーマに触れるばかりでなく書名として世に提示するには相当な勇気が必要であっただろうと推察される。この話題についてのタブーが解かれ、今後の新しい研究の機運が生まれる可能性がある。日本におけるルター派唯一の大学・ルーテル学院大学の神学者からは、「私たちはそろそろプロテスタント(抗議信仰/薗田坦の訳語)という言い方を卒業しなければならない」という発言が出るなど、かなり自由な学風が担保されているように見える。宗教改革から500年以上、プロテスタント日本伝来から150年以上が過ぎた。日本でもそろそろルター派の研究者から、ルターと異民族・異教徒についての「自己批判的な」研究書が出版される時期かもしれない。
『トルコ人に対する戦争について』のドイツ語からの日本語訳(石本岩根訳)は、『ルター著作集 第一集第九巻』(聖文舎、1973年)に解説・訳注付きで所収されている。『ユダヤ人と彼らの嘘について』の日本語訳は、『ユダヤ人と彼らの嘘 仮面を剥がされたタルムード』というタイトルで、2003年に雷韻出版から刊行されている。後者の翻訳は「歴史修正研究所」という太田龍氏が所長を務めていた組織のもので、英語からの重訳である。太田氏による巻末の解説には「本訳書が、まさに今、シオニスト・ユダヤを尖兵とするイルミナティ世界権力によって、皆殺しにされようとしている日本民族の覚醒のためにお役に立ってほしいと切に祈念する」とある。同研究所は、反ユダヤ主義を打ち出しており、最初からユダヤ人を批判することを目的にしていると捉えられ、世界中から反ユダヤ主義と人種差別を撲滅するために活動する組織サイモン・ヴィーゼンタールセンター(Simon Wiesenthal Center/本部:米国ロサンゼルス)から抗議を受けたと言われている。21世紀の極東・日本においても、ユダヤという「共通の敵」を批判するために、ルターが政治利用された事例である。この本は、現在中古でも手に入りにくい。『ユダヤ人と彼らの嘘について』は、『ルター著作集』にも入っておらず、日本語訳はこの本でしか読めない。もしこの著作が『ルター著作集』などに所収されていれば、この「歴史修正研究所」の訳による本(本邦初訳)は誕生しなかったかもしれない。このルターの著作を改めてルーテル教会の研究者が当時のドイツ語原典から翻訳し、「自己批判的な」注・解説をつけて出版する必要もあるのではないだろうか。他教派や非信徒の研究者が研究すると、随分角が立つであろうし、最初から特定の陣営を批判することだけが目的の研究や陰謀論、「ルター知らず」による勝手な解釈が横行する。カトリックもまた、ルター宗教改革期のカトリック教会の「腐敗」について、実証的な研究をする必要があろう。自らの痛いところを触れられる教団は、一目置かれる。
参考までに、邦訳されているルターの言説を引用して紹介する。
トルコ人はわれらの主なる神の怒りの笞であり、凶暴な悪魔の僕である(中略)
教皇が反キリストであると同じく、トルコ人はからだをとって現れた悪魔である。これら双方のものに対するものは、私たち、しかも、キリスト教の祈祷である。最後の審判の日がなすべきことであろうが、双方共に地獄に堕ちるべきものである。その日が遠くないことを、私は望むものである。
マルティン・ルター著「トルコ人に対する戦争について」石本岩根訳
『ルター著作集 第一集第九巻』27、40頁
国内には沢山のユダヤ人達が居住しています。彼等は多くの災いをもたらすのである。…あなたがたはこれから述べる事実を知らなければなりません。すなわちユダヤ人達は我らの救世主の御名を日夜冒涜し、汚しているのだという事を。この理由によってあなたがた、閣下並びに権威ある諸氏が、彼らに寛容であることなく、彼らを追放すべきであります。彼らは我々の公敵であり、絶え間なく主キリストを冒涜しています。彼らは我々の聖母マリアを一人の売春婦と呼び聖なる子を私生児と呼んでいます。そして彼らはわれらキリスト教徒に対して、「取りかえっ子」(妖精がかわりに置いていったという醜い子)とか、「かたわ」といった悪口をいっています。
もし彼らが我々全員を殺戮する事ができるなら、彼らは喜んでそうするでしょう。事実彼らの多く、特に外科医とか医者であると称している者達は、キリスト教徒を殺害しているのです。
マルティン・ルター著『ユダヤ人と彼らの嘘』歴史修正研究所訳 77頁
現代における諸宗教対話・エキュメニズムの視点からするならば、このイスラーム(トルコ)、ユダヤ、カトリック、三者に対するルターの言説は、著しく対話を難しくするものである。前述したクザーヌスの言説、後述するライプニッツの言説の真逆を行くものだ。こうしたルターの言説への批判を、カトリック信徒は対岸の火事として静座しているわけにもいかない。ルターは、まぎれもなく元はカトリック・アウグスティヌス会修道士であり、カトリックにとっても重要な考察事柄として、フランスのドミニコ会司祭で第二バチカン公会議の起草者の一人、最晩年に枢機卿となったイヴ・コンガール(Yves Congar, 1904-1995)、ドイツの枢機卿ヴァルター・カスパー(Walter Casper, 1933-)といった20世紀のカトリック神学者がルターについての研究書を著している。両枢機卿とも、ルターに対して感謝を含んだ評価をしている。カトリックにとってもルターによる宗教改革は、結果的には対抗宗教改革(カトリック宗教改革)をもたらし、イエズス会の創設(1534年)、トリエント公会議開催(1545-1563年)につながった「自浄作用」を生み、カトリックの伝統の新しい地平を開いた(結果的に、カトリック的ヒエラルキーの統治機能をより高めることになった)。
現在、ルーテル教会(ルター派/19世紀舞台ドイツ語の発音から、ルターはルーテルと、ショーペンハウアーはショーペンハウエルと、シラーはシルレルと、シュライエルマッハーはシュライエルマッヘルと、ゲーテの『若きウェルターの悩み』は『若きウェルテルの悩み』と日本語で表記された)は、聖公会(英国国教会)同様、カトリック教会とは、まだ不十分・不完全な形かもしれないが相互陪餐(inter-communion)の関係にあり、エキュメニズム(世界教会運動/教派対話運動)が進んでいる。2017年には、「宗教改革500年」という記念すべき年を迎え、世界中でカトリック教会もともに祝うエキュメニカルな式典を開かれた。2017年11月23日には、カトリック浦上教会(長崎市)で、日本福音ルーテル教会・日本カトリック司教協議会共同主催「宗教改革500年共同記念――平和を実現する人は幸い」が行われ(参照:拙稿「新ながさきキリシタン地理 3」)、「キリスト一点しぼり」(橋本勲神父)という日本発のエキュメニズム神学テーゼが生まれた(『福音宣教』2018年3月号13~19頁参照)。ルーテル教会は、カトリック信徒にとって大変馴染みが深い教派だ。ドイツのカトリック司教団は、今やルターのことを「福音の証人」「信仰の教師」と呼び、「聖ルター」(Sanctus Martinus Lutherus)と呼ぶカトリック信徒もいる。
クザーヌスのイスラームに対する宗教対話の姿勢と重なって見えるのが、ドイツの外交官ゴットフリート・ヴィルヘルム・フォン・ライプニッツ(Gottfried Wilhelm von Leibniz, 1646-1716)の教会再合同計画の運動である。『モナドロジー』『人間悟性新論』『弁神論』を著した哲学者、微分・積分法をニュートンと同時期に発見した数学者として著名な人物(ライプチヒ生まれ)だが、マインツ選帝侯に仕える外交官で、1672年にパリに派遣され、1676年の帰国後、ハノーヴァー侯に仕えた。クザーヌスから約250年後のドイツの人物である。
コンスタンティノープル陥落という「破局」をクザーヌスは経験したが、ライプニッツが生まれたのは、まさに三十年戦争(Dreißigjähriger Krieg, 1618-1648年)で荒廃したドイツ、延いてはヨーロッパで、この戦争のために著しくドイツの近代化が遅れたと言われる(ランケ)。長期に亘る戦争であったが、初期は、カトリックとプロテスタントの対立によって始まった戦争であった。戦争を終結させたウェストファーレン(ウェストファリア)講和条約(1648年)は、ライン川左岸アルザス地方のフランスへの編入、カルヴァン派の承認(アウクスブルク宗教和議の適用)、オランダやスイスなど「カルヴァン派国家」の独立などを決定し、近代的ヨーロッパ世界を規定した。中世的価値観はここで完全に打ち破られることになった。この三十年戦争に軍人として従軍したフランスの人物に哲学者ルネ・デカルト(René Descartes, 1596-1650)がいる。ドイツの軍事冬営地で時間がある冬の期間を利用して、思索の指南書である『方法序説』(Discours de la méthode, 1637)をラテン語ではなくフランス語で書いた(ちょうど、パンプローナの対仏戦争に軍人として従軍し重傷を負い、療養中に霊的修養書である『霊操』〔Exercitia spilitualia, 1522-23〕を書いたイエズス会の創設者イグナチウス・ロヨラ〔Ignatius de Loyola, 1491?-1556〕と似ている)。「我思う故に我あり」(Je pense donc je suis/ラテン語著作『省察』〔Meditationes de la prima philosophia, 1641〕で、cogito ergo sumと後に引用される)で広く知られる思索の方法「方法的懐疑」(doute méthodique)を支持する多くのカルテジアン(Cartesian/デカルト主義者)を後世に生み出すことになった。
キリスト教の教派間での泥沼の戦争、三十年戦争という「破局」の後、ライプニッツは『宗教の平和について』(De R[eligionis] P[ace], 1691)という小論を著す。コンスタンティノープル陥落直後に『信仰の平和』を書いたクザーヌスと歴史的類比がある。どちらも、宗教間/教派間対立が「破局」(戦争)をもたらすことを皮膚感覚で知っていた。『宗教の平和について』にはこうある。
宗教の対立から途方もない悪が生じる。すなわち、憎しみと不信、殺し合いの戦争、不信仰者の成功、不敬、(中略)〔宗教的〕自由主義思想、すべての宗教の軽蔑。(中略)
〔教会〕分裂の悪はこれら〔教会の善〕に対置されるものであるが、しかし私は〔善と悪が〕別々に引き離されるのではなく、〔悪は〕ただちに善と同類のものに対比されることを明らかにしたいと考えている。というのも、対立して置かれたものはそれぞれが一致することによっていっそう輝きだすからである。これらの悪に、霊的な悪として、市民の戦争を加え入れることが有益であろう。なぜなら、これら〔戦争〕は魂の大いなる高揚なしに生じることはなく、多くの悪行の機会を提供するからである。
ライプニッツ著『宗教の平和について』町田一訳
『ライプニッツ著作集 第Ⅱ期 2』260、262-263頁
ライプニッツは、北部ドイツ出身者らしくプロテスタント・ルター派のキリスト者であった。ドイツ人としての矜持を持っていたが、国際社会でのドイツ語の評価が高くなかったことから、多くの著作をフランス語で執筆した(タイトルだけはラテン語のケースが多い)。ライプニッツはフランクフルトで、親子ほど年齢の離れた政治家でありながら、神学・哲学・外交に造詣が深かったボイネブルク(Johann Christian von Boyneburg, 1622-1673)から綜合された学術の手ほどきを受け、ボイネブルクがプロテスタントからカトリックへの改宗者であったことから、共同で、新旧教会の再合同案を構想し、教義上の解決のために、『カトリックの論証』(Demonstrationes catholicae, 1668-1671)を著した。教義的には、ライプニッツは完全にカトリックの教義である自由意志論に至ったが、カトリックへの改宗はしなかった(『自由意志論』〔De libero arbitrio diatribe sive collatio, 1524〕を示したエラスムスに反して、ルターは『奴隷意志論』〔De servo arbitrio, 1525〕を著して、これをルター派の立場とした。ルターより20年後に現れるカルヴァン主義の基幹思想である予定説を準備する)。哲学においては、アリストテレスとデカルトの哲学の調停・綜合という、当時影響力があったカトリック神学者マルブランシュ(Nicolas de Malebranche, 1638-1715)と同じ計画を持っており、ガッサンディ(Pierre Gassandi, 1592-1655)、アルノー(Antoine Arnauld, 1612-1694)などのカトリック司祭たちと交流した。自由意志論を信じるライプニッツは、交流したカトリック神学者たちからも、雄弁で知られるフランス・モーのボシュエ司教からも、長年仕えた人物でプロテスタントからカトリックへ改宗したヘッセン=ラインフェルス方伯からも、再三カトリックへの改宗を薦められるが、ライプニッツは固辞した。
ライプニッツは安易に改宗することよりも、カトリック対プロテスタントの対立を超えた理性に基づいた「真の普遍主義」を探求する道を選び、生涯ルター派一信徒の立ち位置のまま教会再合同のために尽力した。ライプニッツの教会再合同計画については、エキュメニズムの視点から、稿を改めて触れてみたい。
以上、本稿は、コンスタンティノープル陥落に際してのクザーヌス枢機卿の言葉と行いを軸としながら、ルター、ライプニッツの言葉と行いと対比させながら、中近世移行期における歴史的出来事と3人のドイツ知識人の在り方を描いてみようと試みたものである。善し悪しを問うものではない。哲学者は、自らの内奥を見つめ、自らの理性を頼り、省察によって思想を深め、理論体系を構築し明文化する。探求の対象は、人間、世界、神であることがしばしばで、探求の主体はあくまで断乎として思索を行う屹立した自己(「方法的懐疑」においてデカルトが最後まで疑い得なかったものである)であり、しばしば哲学者には独我論的傾向もあり、隣人に対しては冷淡とも感じられ、隣人へのまなざしというのは、哲学書からは確認されにくい。クザーヌスもライプニッツも、断乎として自らを探求し、神と世界について考察した著作で現代に伝わっている。同時に、クザーヌスにはイスラームへの、ライプニッツにはキリスト教諸教派へのまなざし、隣人への温かいまなざしを感じる。まさに、諸宗教対話、エキュメニズムの視点から再検討されるべき人物であろう。哲学の領域からの研究は進んでいるが、「枢機卿クザーヌス」「外交官ライプニッツ」といったタイトルの研究書は、まだ本邦には存在しない。
知識人・芸術家の現実政治への参加を意味するアンガージュマン(engangement/古フランス語で「担保の中に入れる」の意味)という言葉が、さかんに1960年代に言われたが、これら15~17世紀のドイツ人神学者・哲学者の態度は、それとは次元の異なるものだった。むしろ、あえて自ら発言するリスクを体ごと負い、現実の「破局/危機」の中、単独者として向かい風(Gegenwind)に抗して稿を興したのではないだろうか。いずれも、一種の「プロテスト」であっただろう。一方で、現代社会・現実政治で行われている事象には一切関わらないという知識人の在り方もある(20世紀では神学者・聖書学者ルドルフ・ブルトマンがそう言われた)。「肘掛(安楽)椅子の哲学者」(an armchair philosopher)という言い廻しもあった。その象徴であるドイツの哲学者イマヌエル・カント(Immanuel Kant, 1724-1804)は、生涯故郷ケーニヒスベルク(現ロシア領カリーニングラード)を出なかったと言われるが、1755年のリスボン大地震の直後には、『地震原因論』(Von den Ursachen der Erdenschütterungen bei Gelegenheit des Unglücks, Welches die westliche Länder von Europa gegen das Ende des vorigen Jahres betroffen hat, 1756)という自然学の著作を書いた。現実政治には関わらなかったとしても、『永遠平和のために――哲学的考察』(Zum Ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf, 1895)というパンフレットを書き、後に国際連盟(Société des Nations / League of Nations, 1920-1946)の理念の一つになったと言われている(カントの『永遠平和のために』と国際連盟の理念、そして「江戸の泰平」が無意識的に戦後日本で結実し、日本国憲法第9条が生まれたという説も人口に膾炙している)。「肘掛椅子の哲学者」も一流になると、たとえ本人の実践的行いはなかったとしても、後世の支持者が行動し、理念を具現化してくれることになる。ヘーゲル(Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831)からはヘーゲル左派(青年ヘーゲル派)が生まれ、資本主義の暴走とそれによる経済格差が起こることを予見し警鐘を鳴らしたマルクス(Karl Heinrich Marx, 1818-1883)とマルクス主義がもたらされた。
コンスタンティノープルと言えば、ごく最近2020年7月10日、トルコのエルドアン大統領がイスタンブールのアヤソフィアをモスクとして再び機能させると宣言したことで記憶に新しい。1934年からは宗教的中立の博物館となっていた。トルコの最高行政裁判所は、「アヤソフィアのモスクとしての利用を停止し、博物館だと定義した1934年の閣議決定は法に則っていない」と結論づけた。1923年にトルコ共和国を建国した初代大統領ケマル・アタテュルク(Mustafa Kemal Atatürk, 1881-1938/ケマル・パシャ)は、旧オスマン帝国のスルタン制を廃止し「政教一致」の軛から離れ、政教分離・世俗化を基軸とした近代国家を建設しようとした。1990年代からは、トルコ国内からもイスラーム原理主義が台頭していた。今回の「決定」に際して、アヤソフィアを世界遺産に指定している国連機関ユネスコは、「非常に遺憾」とし、ローマ教皇フランシスコは7月12日の船員の日に「海は、私の思いをここから少し離れたイスタンブールに運びます。私はアヤソフィアを思い、非常に悲しんでいます」と発言している。東方正教会のコンスタンティノポリ総主教ヴァルソロメオス1世は、「アヤソフィアは現在の所有者だけでなく、全人類に属する。キリスト教とイスラームの出会い、対話・連帯と相互理解の象徴的な場所として深い意味を有する。世界中の多くのキリスト教徒をイスラームに反発させることになりかねない」と警鐘を鳴らす。ただこれは、トルコ国内におけるかつての宗教施設についての決定事項で、トルコ共和国憲法が認める「信教の自由」の範疇だ。イスラームの側の言い分もあろう。欧米列強諸国による内政干渉にも繋がり、判断が難しいところである。この「決定」に、エルドアン大統領支持の宗教的保守派たちは熱狂し、ナショナリズムが高揚しているのは事実だ。
クザーヌスとライプニッツは、ともに、各学問領域にまたがる知の綜合を行った人物である。実に宗教者らしい「綜合」を行った。本稿のはじめに引用した歴史家クローチェにはこう記す。
中世の歴史叙述はキリスト教的神學及び倫理と一致し、十九世紀前半期のそれは理想主義的及びロォマン主義的哲学と一致し、またその後半期のそれは自然主義的及び實證主義的哲學と一致しているということももとより明かである。かく、歴史の立場からしてex parte historicorumは、歴史的思想と哲學的思想とを差別するみちはない。この兩者はその敍述の中に完全に溶合するものである。しかしながらかくの如き差別は哲學の立場からしてex parte philosophorumもやはり保持され得ない。なぜならば何人も知るようにまたは少なくともいうように、各々の時代はそれぞれの哲學をもつ。そしてそれはかれに特有のものでありまたこの時代の意識であり、そしてかくの如きものとしてこの時代の歴史、少なくともその萌芽におけるかれの歴史である。または、われわれがすでにいったように、哲學と歴史は一致する。そしてこの両者が一致するならば、したがって哲學の歴史と歴史叙述の歴史とも一致する。
クロォチェ著『歴史の理論と歴史』羽仁五郎訳、195頁
この指摘は、文学部不要論が唱えられる現代の日本においてこそ特に重要である。戦後、皇国史観を覆した唯物史観の実証至上主義によって、「小さな物語」(Microstoria)ばかり出し過ぎた感がある。「大きな物語」のストーリーテラーが少なくなっている。こうした全―世界的傾向を打開するべく、20世紀の後半以降、主に英語圏から、歴史学内外の諸領域出身の「大きな物語」を描く巨視的歴史家(ウィリアム・マクニール、ジャレド・ダイアモンド、エリック・クライン、ユヴァル・ノア・ハラリなど)が現れ、日本でも翻訳されよく読まれている。日本からは、歴史学の領域からではなく、大学の哲学科からでもなく、主に思想の領域から在野の研究者によって「大きな物語」を描く試みがなされている。
クザーヌスとライプニッツは、両者とも、「危機/破局」にあって、時代を調停し平和をもたらそうとした「修復者」であった。「カトリック教会のコペルニクス的転回」(ポーランド人の天文学者コペルニクスはカトリックの神父であった)をもたらした第二バチカン公会議(Vatican Council II, 1962~65年)もまた、第一次世界大戦(WWI, 1914~18年)、第二次世界大戦(WWII, 1939~45年)という「危機/破局」から問いが立てられた。新約聖書に「平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる」(マタイ5:9)とある。いつの時代にも、平和を脅かし破局をもたらす「破壊者」がいれば、時代を調停する「ピースメイカー」(マーガレット・マクミラン)もいるものだ。
国内外で再び「破壊者」による言葉と行いを目の当たりすることが多い現代である。一神教(ユダヤ教、キリスト教、イスラーム)の対話・共生は、依然として世界の平和維持のための一大ファクターだ。日本でも、いささか低調気味に見える諸宗教対話、エキュメニズムも、今後、大いに行われるべきことであるだろう。コロナ禍の「ステイホーム」(家にいなさいという自粛命令)で、戦時下の防空壕で過ごすような日常の中(しかし、電気は通り風呂に入れる快適な防空壕である)、「調停者」「ピースメイカー」の在り方に関心を持っている。現代国際政治においては、実に教皇フランシスコがこの役割を果たしているように思われる。
(立教大学日本学研究所研究員、南山宗教文化研究所非常勤研究員
元『福音と世界』編集長)
【参考文献】
八巻和彦著『クザーヌス 生きている中世』ぷねうま舎、2017年
八巻和彦、矢内義顕編『境界に立つクザーヌス』知泉書館、2002年
K・フラッシュ著、矢内義顕訳『ニコラウス・クザーヌスとその時代』知泉書館、2014年
渡邉守道著『ニコラウス・クザーヌス』聖学院大学出版会、2000年
E・モイテン著、酒井修訳『ニコラウス・クザーヌス』法律文化社、1974年
ヤスパース著、薗田坦訳『ニコラウス・クザーヌス』理想社、1970年
上智大学中世思想研究所編『中世思想原典集成17 中世末期の神秘思想』平凡社、1992年
L・ハーゲマン著、八巻和彦、矢内義顕訳『キリスト教とイスラーム――対話への歩み』知泉書館、2003年
Nicolai de Cusa, Cribratio Alkorani, Ⅰ Ⅱ Ⅲ, Meiner, 1989
Ian Christopher Levy, Rita George-Tvrtkovic & Donald F. Duclow(ed.), Nicholas of Cusa and Islam: Polemic and Dialogue in the Late Middle Ages, Brill, 2014
渡辺金一著『コンスタンティノープル千年――革命劇場』岩波新書、1985年
橋口倫介緒『中世のコンスタンティノープル』講談社学術文庫、1995年
S・ランシマン著、護雅夫訳『コンスタンティノープル陥落す』みすず書房、1969年
野中恵子『寛容なる都――コンスタンティノープルとイスタンブール』春秋社、2008年
牟田口義郎編『世界の戦争3 イスラムの戦争――アラブ帝国からコンスタンティノープル陥落まで』講談社、1985年
前嶋信次、杉勇、護雅夫編『オリエント史講座3 渦巻く諸宗教』学生社、1982年
酒井潔著『人と思想 ライプニッツ』清水書院、2008年
下村寅太郎『ライプニッツ』みすず書房、1983年
R・フィンスター、G・ファン・デル・ホイフェル著、沢田允茂監訳、向井久他訳『ライプニッツ――その思想と生涯』シュプリンガー・フェアラーク東京、1996年
バートランド・ラッセル著、細川董訳『ライプニッツの哲学』弘文堂、1959年
町田一訳著『初期ライプニッツにおける信仰と理性――『カトリック論証』注解』知泉書館、2015年
M・スチュアート著、桜井直文、朝倉友海訳『宮廷人と異端者――ライプニッツとスピノザ、そして近代における神』書肆心水、2011年
E・J・エイトン著、渡辺正雄、原純夫、佐柳文男訳『ライプニッツの普遍計画』工作舎、1990年
ジェイムズ・ノウルソン著、浜口稔訳『英仏普遍言語計画――デカルト、ライプニッツにはじまる』工作舎、1993年
酒井潔、佐々木能章監修、酒井潔、長綱啓典、町田一、川添美央子、津崎良典、佐々木能章、清水洋貴、福島清紀、枝村祥平、今野諒子訳『ライプニッツ著作集 第Ⅱ期 2法学・神学・歴史学――共通善を求めて』工作舎、2016年
シャトレ著、竹内良知監訳『シャトレ哲学史Ⅲ 近代世界の哲学――ミュンツァーからライプニッツへ』白水社、1976年
C・ヴェロニカ・ウェッジウッド著、瀬原義生訳『ドイツ三十年戦争』刀水書房、2003年
シルレル著、渡辺格司訳『三十年戦史』第一部、第二部、岩波文庫、1988年
ルター著作集委員会編『ルター著作集 第一集第九巻』聖文舎、1973年
マルチン・ルター、I・B・プラナイティス著、歴史修正研究所訳『ユダヤ人と彼らの嘘 仮面を剥がされたタルムード』雷韻出版、2003年
宮田光雄著『ルターはヒトラーの先駆者だったか――宗教改革論集』新教出版社、2018年
W・カスパー著、高柳俊一訳『マルティン・ルター――エキュメニズムの視点から』教文館、2017年
Yves Congar, Martin Luther; sa foi et sa reformé - Etudes de théologie historique, cerf, 1983
Yves Congar, Mon Journal du Concile, cerf, 2002
クロォチェ著、羽仁五郎訳『歴史の理論と歴史』岩波文庫、1952年
B・クローチェ著、上村忠男訳『思考としての歴史と行動としての歴史』未来社、1988年
ランケ著、鈴木成高、相原信作訳『世界史概説――近世史の諸時代』岩波文庫、1941年
J・ル=ゴフ著、池田健二、菅沼潤訳『中世とは何か』藤原書店、2005年
ジャック・ル=ゴフ『ヨーロッパは中世に誕生したのか?』藤原書店、2014年
ジャック・ル・ゴフ著、桐村泰次『中世西欧文明』論創社、2007年
ヤーコプ・ブルクハルト著、新井靖一訳『イタリア・ルネサンスの文化』筑摩書房、2007年
ヤーコプ・ブルクハルト著、新井靖一訳『世界史的考察』ちくま学芸文庫、2009年
アンリ・ピレンヌ著、佐々木克巳訳『中世都市――社会経済史的試論』講談社学術文庫、2018年
アンリ・ピレンヌ著、佐々木克巳訳『ヨーロッパ社会の誕生――マホメットとシャルルマーニュ』講談社学術文庫、2020年
E・ジルソン著、三嶋唯義訳『神と哲学』行路社、1975年
E・ジルソン著、三嶋唯義訳『理性の思想史――哲学的経験の一体性』行路社、1976年
エティエンヌ・ジルソン著、渡辺秀訳『中世哲学史』エンデルレ書店、1949年
M・グラーブマン著、下宮守之訳『中世哲学史』創造社、1967年
F・コプルストン著、箕輪秀二、柏木英彦訳『中世哲学史』創文社、1970年
アラン・ド・リベラ著、阿部一智、永野潤、永野拓也訳『中世哲学史』新評論、1999年
ウィリストン・ウォーカー著、速水敏彦、柳原光、中澤宜夫訳『キリスト教史2 中世の教会』ヨルダン社、1987年
フスト・ゴンサレス著、石田学訳『キリスト教史 上巻 初代教会から宗教改革の夜明けまで』新教出版社、2002年
J・ペリカン著、鈴木浩訳『キリスト教の伝統 教理発展の歴史 第3巻――中世神学の成長(600-1300年)』教文館、2007年
ヨゼフ・ロルツ著、神山四郎訳『教会史』ドン・ボスコ社、1956年
マーガレット・マクミラン著、稲村美貴子訳『ピースメイカーズ――1919年パリ講和会議の群像 上下』芙蓉書房出版、2007年