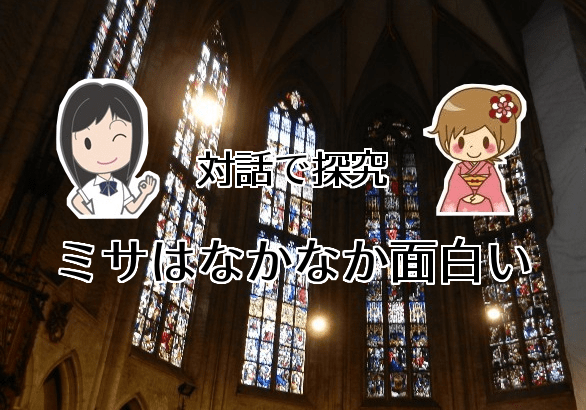多言語時代の典礼言語
答五郎 さて、ミサの式次第に沿って「交わりの儀」のところから、聖体拝領の歴史や、最近は、典礼言語の問題まで入って、16世紀から20世紀までを見てきたところだ。
問次郎 そして、意外にも、カトリック諸国でも、国語使用への望みはわりとはっきり出ていたことがわかりました。ラテン語で凝り固まっていたわけではなかったのでしたね。
答五郎 でもね、現代の典礼刷新(つまり第2バチカン公会議の理念による典礼改革)は、単にこの時代からの国語化への希求がそのまま実現したものではないということが大事なのだよ。
問次郎 ええっ? どういうことなのでしょうか。
答五郎 それはちょっと難しい話になるので、いつか機会があればということで。ともかく1965年からは自国語でミサがささげられる時代に入っている。だからって、これで万々歳というわけでもない。実際にラテン語の祈りを日本語にしたのだけれど、それで典礼は望ましいものになったといえるのだろうか。
美沙 わたしたちが見学を始めたのは、今のミサですから、日本語ではない典礼をイメージしにくいです。
答五郎 私だってそうだよ。言いたいのは、ラテン語を諸国語に置き換えたということの意味をどう考えるかだ。まず一つに、典礼言語の問題は、その地域や国での言語のあり方と関係している。この点で日本には独自の問題があるのを知っているだろうか。
美沙 文語体のことでしょうか。「主よ、あわれみたまえ」とか「栄光のゆえに感謝したてまつる」とか、ミサのたびに歌うこれらの賛歌が文語調なのに、最初は戸惑ったことがあります。「栄光の賛歌」は長いので、余計に。それに『カトリック聖歌集』が歌われるときも文語の詞ですよね。
答五郎 主の祈りだって、ついこの間まで、「天にましますわれらの父よ……」だった。典礼の外で祈られる祈り「アヴェ・マリアの祈り」も、ついこの間まで「めでたし聖寵満ちみてるマリア」だった。カトリックの祈りというと文語の祈りがふつうで、そのほうが、格式があったと感じている人は、今も多いかもしれない。ともかく、実際、第2バチカン公会議後、典礼の刷新に伴って国語にすることが至上命令となったとき、文語にするか口語にするかが論じられたらしい。結局、口語(現代語)で行くという決断になったわけだ。
問次郎 では、どうして、「主よ、あわれみたまえ」などの賛歌は文語のまま残されたのですか。
答五郎 私が学んだ先生方から聞いたことだけれど、これらの歌はカトリック教会だけでなく、ルーテル教会や聖公会などでも賛歌として歌われているので、これを現代日本語にするときには、共通のものができたらよいだろう、というとても高い理念が唱えられていたというのだ。そのときまでしばらくは文語のまま続けようということだったらしい。そのしばらくがずいぶん長くなったのだけれどね。
美沙 つまり、日本語にするときには、賛歌の伝統を同じように守っている諸教会の間で、共通性や一致を大事にしようとしたわけですね。それは、とても素敵で、現代的な精神ですね。
答五郎 だが、実際には、諸教会が、それぞれ自前で、これらの賛歌を現代語にしていっているのだよ。そこに関しては足並みを揃えようというふうにはならかったらしい。けれど、キリスト教の祈りでもっとも大切な「主の祈り」に関しては、聖公会とカトリック教会が共通の現代語訳にしたのだ。2000年のことで、それは画期的なことだった。ルーテル教会も最近これを採用したので、三教会は「主の祈り」においては一致したことになる。
問次郎 なるほど。日本語の歴史の中での文語(古典語)から口語(現代語)へという課題が典礼言語の場合は絡んでいるのですね。ヨーロッパでは、古典語がラテン語で口語が諸国語だったのですね。
答五郎 日本では、この問題は継続中だともいえる。そして、新たな事情も生まれている。多言語時代の到来だよ。公会議後にラテン語を日本語にすることになったとき、考えられていたのは、日本の教会は当然、日本語の教会という考え方だった。
問次郎 それは当然だと思いますが。
答五郎 ところが、どうだろう。やがてカトリック教会は、日本人、というか日本語を母国語とする人たちだけの教会ではなくなってきた。移住した外国籍の人がたくさん集まっている。ブラジル人、フィリピン人、ベトナム人、もっともっと多くの国から来ている。日本におけるカトリック教会は、ポルトガル語やスペイン語やベトナム語や中国語やタガログ語や、もっとさまざまな言語を母国語としている人々の教会になったわけだ。
美沙 それで、書店で「六カ国語ミサ式次第」という本を見たことがあります。教会の情報ハンドブックにも、いろいろな言語のミサを行っている教会と時刻が示されていますね。
答五郎 それぞれの国の信者がコミュニティーを作っていて、その共同体でささげられるミサの場合は、その国の言語でささげられるので、それができる教会はそのような時間を設けているということだよ。もちろん、日本社会で生活し働くということは日本語を学習することだから、そのような人たちが日本人の信徒のいるふつうの教会共同体に溶け込んで、日本語のミサに参加していくことも自然だし、望まれることでもあるだろう。こうしたことは、日本語典礼の始まりのときは、想定されていなかっただろうね。
美沙 一つの典礼の中で、いろいろな言語が使われる場合もありますよね。
答五郎 そう、インターナショナル・ミサという形式で、多国籍の人々が集って、一つのミサをささげるというイベント的ミサだね。ベースがたとえば、日本語であっても、聖書朗読や共同祈願や賛歌などでは、いろいろな言語が使用されることとかね。
問次郎 そういうことは、典礼としてはどうなのでしょうか。望ましいことなのでしょうか。
答五郎 これは、あくまで私の観点なのだけれど、典礼とは、単一言語で完結するものことではないということではないかな。日本語の今のミサでも、「アーメン」「ハレルヤ=アレルヤ」とか「ホザンナ」という片仮名の語があるだろう。それらはヘブライ語から来るもので、古代イスラエルの礼拝、旧約聖書の時代からの信者皆が応唱してきた言葉がキリスト教になっても受け継がれている例だよ。新約聖書が書かれたギリシア語でも、それから西方ラテン語典礼が形成されたときで受け継がれて今に至っている。一種のキリスト教のしるしのようなものともいえる。
問次郎 だから、ときどき、その意味はなにかと思いますし、教わらなくてはならないところでもありますよ。
答五郎 その手間はありつつも、大事に受け継いでいく意味はあるのではないかな。「あわれみの賛歌」もラテン語ではキリエといわれ、キリエ・エレイソン……というけれど、実はこれはラテン語ではなくてギリシア語だ。そういうのも残しているのが典礼なんだな。
美沙 おっしゃりたいことは、こういうことですね。典礼はもともと多言語的なものだと。今の例は、神の民の歴史を反映しているものですが、先ほどの例は、現代の教会がますます多国籍・多民族の教会になっていることと関係しているのですね。
答五郎 よくまとめてくれた。特に後者の、多言語時代の典礼とその言語のあり方ということは、実際の教会生活がどうなっていくかということとも関係していて、教会としては、未経験な、最先端の課題といえることだよ。
美沙 私は、ラテン語も、ほかの言語にも興味があるので、とにかくいろいろな言語でミサを体験できたらいいなと思います。
答五郎 そう。一人の人間自身が多言語的になりうるわけだ。いずれにしても、言語に関しては、教会の豊かさ、諸民族の光であるキリストと出会う道の多様性、言語という素晴らしいものを与えてくれた創造主である神を賛美する心で考えていけたらよいね。さて、「交わりの儀」のところで、寄り道してしまったけれど、次回は、またミサの式次第に沿う勉強に戻ろう。
(企画・構成 石井祥裕/典礼神学者)