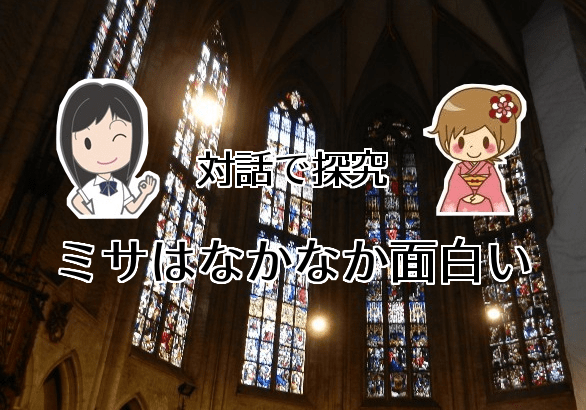畏れ多いものとなっていく聖体
答五郎 こんにちは。「交わりの儀」、とくに聖体拝領という話題になって、歴史を振り返る流れになっているが、きょうは、少しジャンプして、4世紀後半・末という時代を見てみよう。
問次郎 4世紀ですか。キリスト教の大発展の時代ですよね。世界史の授業でも学びます。コンスタンティノス大帝によるキリスト教公認(313年)、ニケア公会議の開催(325年)、アレイオス派(アリウス派)との論争、コンスタンティノポリス公会議の開催(381年)など……。
答五郎 そういう推移のもとで、教会生活、とくに信者の生活も大きく変わっていくのは当然だろうね。典礼に関しては、どのような変化が生まれたと想像するかな。
美沙 迫害の時代から公認の時代へ変わったということは、まず信者が増えていったのでしょうね。
答五郎 そのとおり。信者が増えるということは教会の建物もそれだけ大きなものになるということで、大聖堂時代が始まる。ある意味、教会建築史上の現代が始まるといってもいいものだよ。建築の話はともかく、信者が増えると典礼祭儀にも変化が訪れるかな?
美沙 たくさんの信者が集まるということは、祭儀も盛大になってくるということでしょうか。
答五郎 そうだね。前回見たユスティノスが報告した2世紀半ばでは、信者たちがもう集まっていて、そこで「ことばの典礼」と「感謝の典礼」が簡素なかたちで営まれている感じだった。大聖堂時代になると、大会衆が集まってくること自体に典礼的な意味が与えられてくるようになる。
答五郎 そう! 司式者(司教、司祭)と助祭や他の奉仕者の役割分担も出てきて、また同じ言語で、信者(会衆)との声の掛け合いも活発だったんだ。そうしていた頃の姿に立ち返るかたちでね。
美沙 入祭の歌や「あわれみの賛歌」「栄光の賛歌」もその時代に生まれたのですね。
答五郎 そう、しかも、ミサの賛歌のたぐいは例外なく東方教会で生まれて、西方に伝来し、ローマでも採用に至ったものなのだよ。
問次郎 ところで、この頃の聖体拝領や聖体に対する意識はどうだったのでしょうか。
答五郎 そうだった。聖体拝領について、この時代らしさを伝えてくれる二つの書が注目される。一つはエルサレムのキュリロスの『秘義教話』。4世紀後半から末にかけて、エルサレム教会(聖墳墓教会)で行われた新しく洗礼を受けた人のための講話だ。もう一つは、ミラノのアンブロシウスの『秘跡についての講話』で、これもミラノの教会で行われた同様のものだ。どちらも洗礼式と初めての聖体拝領の信仰的意味を説き明かすというのが主な内容となっている。
問次郎 興味深いですね。洗礼を受けたばかりの人への教えなら、そう難しくなさそうですね。
答五郎 そのとおり。たとえば、アンブロウシスは、洗礼を受けた人に対して、「君たちは、祭壇に置いてあるパンを見て、きっと『毎日食べているパンじゃないか』と思うだろう」と逆に質問しているところがある。そこから、ふつうのパンがいかにしてキリストのからだになるかということを、奉献文を解説しながら教えていくのだよ。もっとも、このテーマは、最初からあって、パウロの1コリント書や『十二使徒の教え』やユスティノスにも必ず含まれていたのだけれどね。アンブロシウスの場合は、大聖堂での典礼の雰囲気を前提にしているので、より身近に感じられる。
美沙 では、この時代、聖体になるパンは日常で食べていたパンだったということでしょうか。
答五郎 そうらしいのだよ。ユスティノスの時代でも、ふつうに食事をする集まりの中で典礼的な段取りが踏まれていたようで、どうやら基本的には、日常生活で食するパンと違わないという前提で話が進んでいるらしい。だから、そういう問いかけが生まれて、それに対して、いわゆる聖体の秘跡についての教えがなされることになったわけだ。
問次郎 そんな率直な質問を投げかける信者さんがその時代にいたのですね。親しみを感じるなぁ。
答五郎 そういう時代だからだと思うのだけれど、キュリロスもアンブロシウスも「キリストの御からだ」と司祭が告げて与える聖体に対して、信仰をもって応えて「アーメン」とはっきり言うように、と教えている。教えの趣旨としては今も全く変わらないだろう。
美沙 はい、つい最近、見学参加した教会でも、神父さんが、聖体を受けるときに「アーメン」とはっきり言うように注意していました。
答五郎 さて、アンブロシウスの講話の中には、注目すべき情報がある。ギリシアの教会の信者たちが、だんだん聖体拝領をしなくてなっているってね。本来、毎週日曜日のミサで受けるものであるのに、だんだん一年に一度ぐらいになっていったというのだ。それに対して、アンブロシウスは、聖体を受ける喜びを強調して、聖体をミサのたびに受けるよう教えているのだけれどね。
問次郎 東方教会でのそういう傾向はどこから来たのでしょうか。
答五郎 4世紀を通じての強い流れとして、やはり、アレイオス派との論争が大きかったらしい。簡単にいえば、御子を御父よりも低い存在とみなす彼らの考え方に対して、神の子キリストの神性をより強調する傾向が強くなって、そのことが教会生活のさまざまな側面に反映されていったのだよ。降誕祭や公現祭が4世紀前半に成立し、4世紀終わりには全キリスト教世界に広まったということもその一つだった。ミサで歌う「栄光の賛歌」の内容もこの背景から生まれている。
問次郎 なるほど! すると、聖体はキリストそのものとして、それ相応に礼拝心が高まっていくのですね。でも、本来、聖体はもちろん聖なるものとして尊敬しつつ、だからこそ、神の子キリストに信者一人ひとりが一致して、神のいのちに養われることを意味するのでしょう?
答五郎 もちろん、そうだ。聖体がキリストの現存で、それを受けることは、まさしくキリストとの交わり(コムニオ)であるということが本質であることは変わらない。キュリロスやアンブロウシスも、まさにそのことを一生懸命説いているわけだ。ただ、そうでありつつ、聖体の秘跡に対する一般の信者の観念が度を越していくのも事実なのだよ。
美沙 過度の尊敬という意味ですか?
答五郎 畏れ多いという気持ちが強くなりすぎて、自分には頂けないという遠慮の意識が強くなっていったのだ。主の晩餐の食卓で一緒にいるという交わりの原体験、原風景が遠ざかっていくのだね。
美沙 今のミサの雰囲気からすると、想像がつきませんね。
答五郎 この時代から各地教会圏でまとめられていく奉献文にも、また教父たちの講話の中でも、聖体に対する畏れ多い気持ちが表現されるようになる。場合によっては、恐れとおののきを強調するようにさえね。たしかにそれは、神秘の一つの側面だけれど、キリストとの交わりにもつ親しみや喜びといった側面が弱まっていくことになる。
問次郎 でも、その現象は、東方教会だけのものだったのでしょう。
答五郎 いやあ、だんだんと西方にも押し寄せてくることになる。それがはっきりしてくるのはフランク王国のカロリング朝時代(8、9世紀)以降なので、それは次回ざっと見ることにする。
(企画・構成 石井祥裕/典礼神学者)
《参考邦訳文献》
*エルサレムのキュリロス「洗礼志願者のための秘義教話」
『盛期ギリシア教父』 中世思想原典集成2、上智大学中世思想研究所監訳(平凡社 1992)所収
*『アンブロジウス 秘跡』P.ネメシェギ編・熊谷賢二訳(創文社 1963)所収