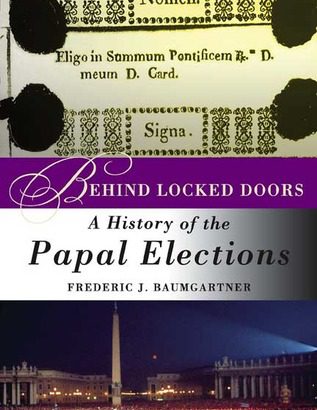日本にも久方ぶりに教皇選挙権をもつ枢機卿が誕生した。教皇選挙の歴史を物語る本を紹介しよう。2000年以降に刊行されたキリスト教の歴史・聖書・霊性に関する洋書をセレクトして紹介してきたこのシリーズも最終回。異例の長編だが、貴重な歴史に関する概観として注目したい:
フレデリック・J・ボームガートナー著『閉ざされた扉の向こうで―教皇選挙の歴史』
Frederic J. Baumgartner, Behind Locked Doors: A History of the Papal Elections (New York: Palgrave Macmillan, 2003), xv+272 pages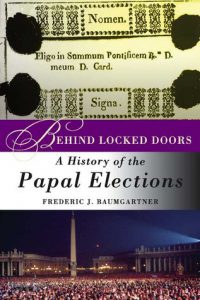
21世紀に入り、2005年にはベネディクト16世、2013年には同教皇の退位に伴い、フランシスコが教皇に選出された。近年の選挙にともない、教皇選挙とはどのようにして行われるのか、あるいはどのように過去に行われてきたのかに新たな関心が集まった。本書は2003年に出版されたものだが、このような関心にちょうどよく対応するものであった。著者は米国カトリック史学会の会長を務めたことがあるカトリック史学界の長老である。
コンクラーヴェと呼ばれる教皇選挙は、西欧中世が形成される黎明期を前史として、11世紀に教皇権が西欧全体に広く認められ、教皇庁に莫大な収入が入るようになり、イタリア半島の中央を占める国家となった時代の到来とともに始まるのである。以下、少し長くなるが、注目すべき教皇選挙の歴史概観が得られるので、著者の叙述に沿って見ていこう。
4世紀までのローマ司教
教皇の権威は全カトリック教会に及ぶ。それは、使徒たちの指導者であり、また最初のローマ司教であるペトロの後継者であることに由来し、初代教皇は使徒ペトロだということになっている。しかし、著者によれば1~2世紀の信者は彼を司教(エピスコポス)とは考えていなかったであろうと述べている。2世紀以後、あちこちのキリスト教共同体は司教をそれぞれの教会の指導者として選ぶようになったが、250年までのローマの教会の事情を示す記録はほとんど残っていない。400年頃の記録はペトロがリヌスを後継者として任命し、さらにアナクレトゥス、クレメンスが彼に続くように支持したとしている。354年に編纂された『リベル・ポンティフィカーリス』(教皇に関する文書)は、最初の2世紀のローマ教会の記録としてはあてにならないと考えられている。3世紀半ばのカルタゴの司教キプリアヌスは、ローマの司教をペトロの後継者と尊敬の念をもってみなしながらも、自分も司教として同じ権威をもっていると考えていた。
さて、コンスタンティヌス大帝は325年にニカイア公会議を招集し、この会議にローマの司教シルヴェステル1世は二人の司祭を派遣した。コンスタンティヌスは最初のキリスト教徒の皇帝で、彼の統治法が帝国内の主要な都市の司教の選出に影響を与え始めるようになった。彼の教会に対する莫大な寄進はローマに集中したため、ローマの司教は財産の管理者としての能力を持たなくてはならなくなった。この皇帝の息子はアレイオス派の異端をローマの教会に押しつけようとし、この時、ローマの教会は二派に分かれてそれぞれの指導者が暴力に訴えて争うようになる。ローマの司教はこの時期に初めて「パパ」と呼ばれるようになった。それまでどこの司教もパパと呼ばれていた。それが4世紀に入ると帝国内の主要都市の司教(大司教)に限って使われるようになり、西方ではローマ司教だけの呼称として使われるようになった。だが、ローマの司教が「パパ」と呼ばれるようになったことはその選挙方法が変わったことを意味せず、依然として司祭たちと民衆が実際の選出権をもっていたのである。
派閥争いに支配された教皇選出
しかしローマ司教(パパ)の選出には、しだいに地方政治の次元と帝国政治の次元の両面から政治的意図が絡むようになる。特に門閥が要素として加わった。インノケンティウス1世(401~417。以下、年号表示は在位年)は西ゴート族によるローマ略奪(410年)の時、皇帝の宮廷に滞在中であった。彼の後、ギリシア人ゾシムス(417~418)が選ばれ、2年後、彼の支持者だった人々はエウラリウスを選出したが、彼の敵はボニファティウス1世(418~422)を選ぶという騒動になった。そこで、ホノリウス帝が介入し、最初エウラリウスを支持したが、彼の支持者が少なかったのでボニファティウス支持に回った。ホノリウスは同時に別々の選挙が行われた場合、もう一度全教会が一致して決めなければならないと命じた。ボニファティウスの後継者、ケレスティヌス1世(422~432)は反対なく全員一致で選ばれた。
これに続く、レオ1世(440~461)までの四代も騒動なしに選ばれた。レオ1世は外交交渉でガリアにいたとき、ローマ不在のまま選ばれた。聖ペトロ大聖堂に葬られた最初の教皇である。ゲラシウス1世(492~496)は、自らを「キリストの代理者」と呼び、有名な「両剣論」、すなわち、現世には二つの権威、教皇に代表された教会と皇帝に代表された国家があり、教会が上位にあると主張した最初の教皇である。ギリシアの司教たちと東方の皇帝に対する強硬な路線は、彼の後継者アタナシウス2世(496~498)が選出されたことで協調路線に変更された。しかし、ローマの聖職者の間では強い反対派がおり、彼の死の後、反アタナシウス派は両親が異教徒であったサルディナ出身のシンマクスを、親アタナシウス派はラウレンティウスを選び、それぞれバチカンとラテラノに拠点を置いて対立した。両派は衝突をくり返したが、東ゴート王国のテオドリック王(493~526。アレイオス派支持者)がシンマクスを選び、教皇として着座した(498~514)。しかし、ラウレンティウス支持者たちはなお10年間も抵抗した。
以後の教皇選挙も必ずと言ってよいくらい同じように派閥争いが続き、東方の皇帝やゲルマン人の王の介入を求めたり、その口実を与えたりした紛糾の連続であった。レオ1世とともに輝かしい功績を残したのは大グレゴリウス(1世)である。590年の彼の選挙については資料があまり残されていないが、ローマ市民を代表する聖職者と元老院によって一致して選ばれたようである。その彼もローマ貴族の家柄の出で、卓抜した行政官としての訓練も受けていた。さらに彼は教皇に選ばれた最初の修道士であり、ローマの教会の役職に修道士を好んで就けた。
カロリング朝フランク王国の台頭のもとで
西方ではフランク王国が台頭し、神聖ローマ帝国への道を歩み始め、ローマの教会ではフランク王国支持派が勢力を増し、聖職者の中のコンスタンティノポリス支持派と対立するようになった。767年、信徒であったコンスタンティヌスが教皇に選ばれ、同時にローマの公爵の称号を取ったとき騒動が持ち上がった。1年後の768年、より正統な手続きによってステファヌス3世(768~772)が選ばれた。対立教皇とされたコンスタンティヌスはラテラノ聖堂から引き出され、両目をくりぬかれ、投獄された。ステファヌス3世は教会会議を開いてコンスタンティヌスの選挙の無効を宣言させた。この時以来、教皇選挙はローマの聖職者全員が選挙権をもつが、被選挙人は枢機卿のみと定められた。しかしローマの貴族はまもなく選挙権を取り戻し、1059年までそれが続いた。
その次に、ローマの聖職者によって一致して選ばれたハドリアヌス1世(772~795)の治世は長くおよそ24年にわたり、教皇庁がカール大帝(シャルルマーニュ、王として768~814)と密接な関係を樹立した時代であった。彼を継いだレオ3世(895~816)はローマ聖職者によって一致して選ばれたが、強力な反対派が生まれたため、カール大帝の宮廷に亡命し、その軍の保護下でローマに戻った翌年の800年、ローマを訪れたカール大帝にローマ皇帝の冠を授けた。続く二人の教皇の選挙は平穏に行われたが、824年の選挙はフランク支持派と反対派に分かれて激しく争われ、4ヶ月の硬直状態の後、カールの子ルートヴィッヒ1世(814~40)の調停でエウゲヌス2世(824~827)が選ばれた。
ニコラウス2世による教皇選挙改革
962年からの神聖ローマ帝国時代には、教皇はいわば皇帝のローマにおける行政官となってしまい、その支持と任命を実質的に受けることとなった。ベネディクトゥス9世(1032~1044、復位1043~46、再復位1047~1048)の選挙の時ほど事態が混迷したことは珍しかった。皇帝冠を受けるためにローマに到着したとき、皇帝ハインリッヒ3世(1039~56)は3人も教皇がいることを発見し、全員を廃位させ、自分好みのクレメンス2世(1046~1047)を教皇座に着けた。彼は続く10年の間に3人の教皇を任命し、選挙の手続きを無視した。彼の子ハインリッヒ4世(1056~1106)は6歳で即位したため、皇帝側は教皇庁の支配権を失った。こうして皇帝の権力から独立して、教皇選挙制度の抜本的な改革を行うチャンスがめぐってきた。
11世紀半ば、イタリア半島の中央部で得た膨大な収入による財力により、教皇の地上的権力は神聖ローマ皇帝に匹敵するまでになっていた。1059年1月ブルガンディア出身のフィレンツェ司教ゲラルドゥスがローレーヌ公爵から送られた軍隊の支持を受けてローマに入り、ラテラノ大聖堂で教皇ニコラウス2世(1058~1061)として聖別式を行った。これはビザンティン皇帝の即位式の要素を取り入れたものであり、以後、教皇聖別式が選挙後の儀式となった。ニコラウス2世は1059年教皇選挙の手続きを決める教会会議を招集し、教令を発布した。その基本はステファヌス9世が、769年に選挙人をローマの聖職者に限り、被選挙人を枢機卿に限った改革の路線を受け継ぐものであったが、最も重要なのは一定の条件の下にローマ以外の人間も被選挙人として認めたことであった。教皇座に着く人物をローマ出身の聖職者以外にも求める可能性を認めることによって、教皇の全教会に対する普遍的権威を真剣に考え始めたことが窺われる。
ニコラウス2世は、シチリア島を含む南イタリアを支配していたノルマン王国と同盟を結び、神聖ローマ帝国の皇帝に対抗して教皇権の独立性を維持しようとした。その結果、以降の中世を通じて、イタリア半島における皇帝派と教皇派の紛争が長く続くことになる。特に教皇グレゴリウス7世(1073~1085)と皇帝ハインリッヒ4世の争いでは、「カノッサの屈辱」(1077年)でいったん教皇が勝利したように見えたが、ハインリッヒ4世は教会会議を招集してグレゴリウス7世を弾劾し、ローマを占領。グレゴリウス7世はノルマン王国に逃れてそこで没した。彼はローマの司教以外はパパの称号を使うことを禁止する勅令を発布し、教皇至上権の確立の第一歩を画したが、死後、彼が指名した3名の枢機卿の中から後継者が選ばれることを命じていたので、事態は紛糾し、改革派がヴィクトル3世(1086~1087)の選挙にこぎつけるまで1年を要した。
ローマ市民の反発と支持の間の教皇たち
1086年以後の歴代の教皇は修道士、修道院長出身であった。修道院長は純粋な信仰と行政能力に長けていると考えられたからである。モンテ・カッシーノの修道院出身で1086年選出されたヴィクトル3世はローマ出身ではなかったことから、ローマ市民の反発を受けてモンテ・カッシーノで没するが、その後継者としてフランス人司教枢機卿がウルバヌス2世(1088~1099)として教皇に選出された。これがニコラウス2世の定めた規定による最初の教皇選挙であったようである。ウルバヌス2世の治世は第1回十字軍の派遣によって知られているが、彼自身は十字軍のエルサレム占領の2週間前に没している。ローマで教皇選挙が行われ、パスカリス2世(1099~1118)が教皇となった。この教皇はローマ市民の反対に遭い、19年間の長い治世の終わりの数日前までローマの外にいた。
パスカリス2世の後継者ゲラシウス2世(1118~1119)の選挙も1059年の勅令通りに行われた。49人の枢機卿、ローマの聖職者、有力市民が一致して助祭枢機卿であった彼を選挙した。しかし、ローマ市では反対派の勢力が強かったので、選挙はラテラノ大聖堂ではなく、ある修道院で行われ、聖別式はナポリ近くのガエタで行われた。その後ゲラシウスはローマに戻ることができず、フランスに亡命し、1119年クリュニーで没した。
4人の司教枢機卿がゲラシウスとともにフランスに亡命しており、彼の意向を受けて現地で選挙を行い、カリストゥス2世(1124~1130)を選び、ローマの枢機卿たちの同意を得るために手紙が直ちに送られた。カリストゥス2世自身は自分の選挙の合法性について確信しており、ヴィエンヌ大聖堂での即位式の準備に直ちに取りかかった。14ヶ月たたないうちに、彼はローマに入り、ローマ出身でなかったにもかかわらず、熱烈に群衆から歓迎された。本来改革派であったが、グレゴリウス7世の遺産である帝国との敵対関係のしこりをもたず、皇帝ハインリッヒ5世(1106~1125)とヴォルムス協約(1122年)を結び、没する2年前までに教皇側に有利に叙任論争にけりをつけることができた。しかし、教皇選挙が規則に従って粛々と行われるという希望は砕かれ、ローマにおけるノルマン王国支持派貴族と、皇帝支持派貴族の党派対立が始まった。
枢機卿団による「閉ざされた部屋での選挙」(コンクラーヴェ)の始まり
しかしこの間、教皇選挙一般に今日に至る重要な仕組みが形成された。一つは、ローマの枢機卿たちはいわゆる枢機卿団意識を持ち始めた。「枢機卿団」という言葉は1148年に初めて使われた。枢機卿団は7人の司教枢機卿、ローマの主要な教会の数の28人の司祭枢機卿、18人の助祭枢機卿から成り立っていた。続く時代に枢機卿の数は減少し、20人以下になった。ローマ以外の司教が枢機卿に任命されるようになったが、司祭枢機卿と助祭枢機卿はローマの聖職者の独占物となった。さらに、教皇制は君主制の様相をますます呈し始め、その権威が増大していった。それとともに、教皇庁の官僚機構が整備され、枢機卿たちは教皇の顧問となり、法的問題に関与し、教皇勅令に名を連ねるようになった。一時期、「ローマ教会の元老院」が使われたが、後世まで続く名称は「クリア」である。1200年までに教皇が枢機卿を招集して行う枢機卿会議(コンシストリウム)が始まり、数人の教皇の下ではそれが毎日行われた。
具体的には教皇グレゴリウス9世(1227~1241)と皇帝フリードリッヒ2世(1215~1250)の争いが発端である。1240年までに二人の間に軍事衝突が頻発し、皇帝軍はローマを封鎖した。グレゴリウス9世は皇帝を弾劾するためにローマに教会会議を招集したが、皇帝軍はローマに来る枢機卿や司教を捕縛。グレゴリウス9世が没したときには12人の枢機卿しかおらず、うち2人は捕縛されていた。おきまりの親皇帝派と反皇帝派の争いが起こり、どちらの側も3分の2を獲得することができず、会議は夏の終わりの暑さの中で続いていた。ローマの政府の長官オルシーニは枢機卿たちを設備の充分でない建物に枢機卿たちと彼らの従者と共に閉じ込め、枢機卿が病気になっても医者が入ることを禁じた。一人の枢機卿が死亡し、ローマ市民が、亡くなった教皇の遺骸を暴くと脅かした結果、枢機卿たちは最初の投票で多数を獲得した人物を教皇にすることに合意し、ケレスティヌス4世(1241)が教皇となった。このときの選挙が「コンクラーヴェ」と呼ばれるものの最初であった。「コンクラーヴェ」(conclave)の語源は「クム cum +クラーヴェ clave=鍵とともに、鍵によって」である。このように「閉ざされた部屋」で選挙をすることが慣習となるのは30年後のことである。以後の教皇選挙はコンクラーヴェで行われ、今日まで教皇選挙の歴史はコンクラーヴェの歴史だということになる。
しかし、中世末の教会分裂の時代をもたらしたものはこのコンクラーヴェが機能しなかったことによる。1270年、クレメンス4世の後継者選びのコンクラーヴェはヴィテルボの宮殿で行われたが、紛糾し、長引き、ヴィテルボ市民は最後には聖霊が自由に働くためにと屋根を取り払ってしまった。もちろん、枢機卿たちはヴィテルボ市に聖務停止を執行すると脅し、仮の屋根がつくられたのだが、教皇選挙で聖霊が働くという考え方はこのとき初めて現れた。ヴィテルボ市民の行動の裏にはアンジュウ公とフィリップ3世がいたと見られていたが、フランシスコ会総長ボナヴェントゥラが、コンクラーヴェが早く結論を出すことを求め、シリアの十字軍で教皇使節であったテオバルド・ヴィスコンティを選ぶように勧告し、彼がグレゴリウス10世(1271~1276)として教皇に即位するまで、前任者が没してから40ヶ月もかかっていた。
グレゴリウス10世の定めた手続き
グレゴリウス10世は即位後、1274年のリヨン公会議で勅書『ウビ・ペリクルム』を発布してコンクラーヴェの手続きを定め、教皇没後10日後に行われなければならず、開催地は教皇が没した都市、その都市が聖務停止の罰を受けているならば近い都市で行われなければならないことを定め、該当の都市の行政官は選挙が適切に行われるように配慮しなければならないこと、コンクラーヴェのために隔離される枢機卿は、一人の召使い、必要な場合二人しか許されないこと、全員がカーテンで仕切られた一つの部屋で睡眠しなければならないこと、コンクラーヴェにはいった瞬間から互いに連絡してはならないこと、さらに食事についての細かい規定を定め、5日目以降パンと水と少量のブドウ酒に限られるように定められた。コンクラーヴェの間中、枢機卿たちは教会を守るため以外の仕事を一切禁じられた。枢機卿たちはコンクラーヴェの間収入を引き出すことが禁じられた。多少の変更があったものの、教皇選挙は1274年の形を維持することとなった。グレゴリウス10世没後のコンクラーヴェでインノケンティウス5世(1276)が選ばれ、このときの選挙は模範的とされたが、これはむしろ例外であった。選挙のたびにフランス王や強力なローマ貴族の利害が衝突して選挙が長引き混迷することが多かった。
そのなかでも、ボニファティウス8世(1294~1303)は、教皇の力と富と威信を享受した人物であった。その即位の直後からボニファティウスの選挙は無効だとする主張が広まった。フランス王フィリップ4世(1285~1314)がイングランドとの領土争いで戦費が必要になり、フランスの聖職者に税金を課したとき、ボニファティウス8世は教会会議を開いて教皇の許可なくして聖職者に課税できないと宣言させた。1301年フィリップは一人の司教を反逆罪で投獄したとき、ボニファティウスは教皇の権威が現世の君主のものを超えると宣言する勅書『ウナム・サンクトゥム』を発布した。
アヴィニョン教皇時代から西方教会大分裂へ
ボニファティウスの後継者、ベネディクトゥス11世(1303~1304)が早く没したのちのコンクラーヴェは一年も続き、枢機卿の中で候補者を絞れず、フィリップ4世が承認したボルドー大司教ベルトラン・デ・ゴットが選ばれ、彼はリヨンでクレメンス5世(1305~1314)として即位した。クレメンスはローマ居住の義務をなかなか果たさず、1309年にようやくローマに向かったが、病を得てアヴィニョンに留まることになった。こうしてアヴィニョン教皇の時代が始まる。
その70年間のあいだ136名の枢機卿のうち112名がフランス人であった。アヴィニョンはプロヴァンスにあったのでフィリップ4世の領土ではなく、教皇の臣下ナポリのシャルル王のものであり、1229年以来教皇に寄進されたヴェネサンに隣接していた。クレメンス5世が同地で没したとき、コンクラーヴェが初めてイタリア以外の場所で行われた。以後、度重なるローマ市の要請にもかかわらず、ローマの群衆による暴動を枢機卿たちは恐れ、コンクラーヴェはアヴィニョンで行われた。
これまで122年間、教皇の61パーセントはローマ以外の都市であったが、アヴィニョン時代の教皇がローマ司教でありながら、帰還の意図をまったく示さないことは教会にとってスキャンダルであった。グレゴリウス11世(1370~1378)はシエナのカタリナの言葉に動かされてローマに帰還したが、健康を害して没した。彼の遺言によって教皇選挙は党派的衝突を避けるためにローマの外で、しかも度々場所を移動してもいいとの指示によって行われた。しかしコンクラーヴェはローマ出身の教皇の選挙を要求する群衆の叫び声の喧噪の中バチカンで行われた。枢機卿たちは妥協策としてバリのイタリア人大司教バルトレメオ・プリニャーノを選び、彼はウルバヌス6世(1378~1389)と称した。ローマ出身者でない人物が選ばれたと聞いた群衆は暴徒化し、枢機卿たちの宮殿、特に新教皇の宮殿を略奪した。しかし枢機卿たちが彼の指示を拒絶したとき、ローマ市民は彼の支持にまわった。ウルバヌス6世は激しい気性で、2ヶ月以内に12人の枢機卿がローマを逃げ出し、残ったのは4名だけになった。その後、3人も逃げ出し、1378年8月2日、枢機卿たちは選挙の無効と教皇座の空位を宣言し、ウルバヌスに対して教皇の称号を用いないように要求した。彼らはフォンディで選挙を行ったが、3人のイタリア人枢機卿はフランス人枢機卿の策略にはまって欠席し、ジュネーヴ大司教枢機卿がフランス人枢機卿によって選ばれ、クレメンス7世(対立教皇 1378~1394)と称した。
ウルバヌスとクレメンスは互いに相手とそれぞれの側の枢機卿を破門し会い、クレメンスは自分の枢機卿を新たにに任命した。ウルバヌスはローマ市民の支持を得て、教皇座を明け渡す意志を示さなかったので、クレメンスはアヴィニョンに教皇座を占めた。両方の側に正統性の根拠があった。二人の没後、両方の側の枢機卿はそれぞれの教皇を選出した。こうして以後、西方教会における教会大分裂の時代が続く。
改革公会議の時代
この大分裂が収拾されるのはコンスタンツ公会議においてである。それまですでにローマの教皇を正統な教皇のリストにあげる伝統が確立していた。コンスタンツの都市の商人たちの倉庫でコンクラーヴェが開かれ、説教、「ヴェニ・クレアトール・スピリトゥス」(創造主である聖霊来てください)が歌われた後、これまでで最大数の50人による選挙が行われ、有力なローマの貴族の家柄で、教皇を出してきたコロンナ家のオドンネが選ばれ、マルティヌス5世(1417~1431)と名乗った。ローマ市は荒廃していたが、以後、教皇はローマに居住することになり、自分からはけっしてローマ市以外に居を構えることがなくなった。マルティヌスに始まり、20世紀後半にヨハネ・パウロ2世が登場するまで、教皇はイタリア人でなければならないとする強力な伝統も生まれた。
コンスタンツ公会議は、公会議によって教皇の権力を拘束しようとした公会議至上主義によって知られている。マルティヌスの跡を継いだのはエウゲヌス4世(1431~1447)であった。彼はコンスタンツ公会議の間、公会議至上主義の枢機卿たちのリーダーだったが、教皇に選ばれるやいなやその立場を変え、公会議の敵となった。彼はバーセルに招集された公会議をフィレンツェに移すように提案したが、バーセルに残った参加者たちが彼を廃位し、サヴォイの前の公爵をフェリクス5世(対立教皇)として選出した。エウゲヌス4世の功績はバーゼル公会議に対抗してカトリック君主たちを味方につけるために、枢機卿団をスペイン人4人、フランス人2人、イングランド、ドイツ、ハンガリー、ポーランド、ポルトガルそれぞれ1名というように初めて国際化したことである。
エウゲヌス4世の死後ニコラウス5世(1447~1455)が教皇になった。対立教皇フェリクス5世は枢機卿に任命されたのち没し、それによって対立教皇は消滅した。ニコラウスの死後、15人の枢機卿がバチカンにコンクラーヴェのために集まり、以後6回を除いて現在までバチカンがコンクラーヴェの場所になった。この時以来、コンクラーヴェの規則や設備は実質的には変わっていない。枢機卿が連れてくることを許される随員がはっきりと定義され、他の枢機卿と話すことが許されていない枢機卿のために他の枢機卿の随員を通して接触する、秘書というよりも助言者的人物とはっきりこの時規定された。
ルネサンス時代から現在へ
しかし、教皇をめぐる駆け引きや混迷が終わったわけではない。ニコラウス5世の死後の選出は長引き、77歳のスペイン人アルフォンソ・ボルハが暫定的に枢機卿たちの合意で教皇となり、カリストゥス3世(1455~1458)と称した。彼の死によってコンクラーヴェが行われ、カリストゥスによって任命された人文主義者アエネアス・シルヴィウス・ピッコリミニが教皇となってピウス2世(1458~1464)となった。
彼が教皇の座に着いたことはコンクラーヴェがルネサンス時代に入ったことを意味する。以後の教皇選挙には、イタリア貴族家間の教皇座の奪い合い、オスマン・トルコの脅威、ドイツ、オーストリア、スペインにまたがるハプスブルク家の神聖ローマ帝国とフランス王国の外交的あるいは軍事的圧力が、宗教改革とバロック時代を通じて加わった。
啓蒙主義から19世紀にかけては、コンクラーヴェに集まった枢機卿にはそれぞれの出身国、特にフランスとオーストリア政府の意向が反映し、調停がつかなかった時にはコンクラーヴェは長期に渡った。コンクラーヴェが今日のように公明正大に新教皇を選挙できるようになるのは19世紀末から20世紀になってである。ちなみに、新教皇が選出されたかどうかを告げるための黒い煙、白い煙の習慣は1294年頃始まったが、明確化したのは1823年のレオ12世(1823~1829)選出の時以来の比較的に新しい習慣である。
現在
ピウス10世以後、教皇選挙の手続きは厳格に規定された。パウロ6世はコンクラーヴェに参加する枢機卿の年齢を80歳以下とし、ヨハネ・パウロ2世は1996年の使徒座憲章によって教皇選挙手続きを詳細に規定した。従来慣習の抜本的な変更として、投票数の3分の2の秘密投票によって新教皇を決定することが明記された。さらにコンクラーヴェの内部の事柄について厳重な秘密厳守を、違反したときは破門の罰に処すると命じた。これによって教皇選挙はスピードアップされることになった。ヨハネ・パウロ2世は、盗聴が行われることを警戒し、念入りに探索するように命じたほどである。21世紀になっての最初のコンクラーヴェはヨハネ・パウロ2世の改革をもとに、かつ同教皇の終焉が予想されていたため、新教皇選挙も準備ができており、ベネディクト16世も早々に選ばれたのである。
(高柳俊一/英文学者)
※教皇選挙の歴史については、『新カトリック大事典』(研究社刊)第2巻の項目「教皇選挙」も参照のこと。