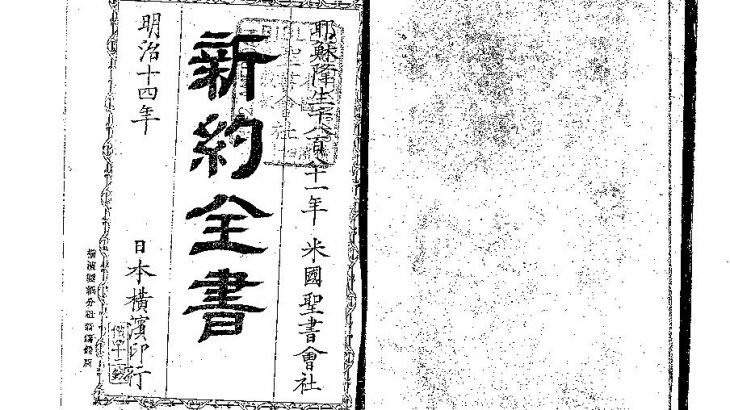キリスト教が「神」というのは当たり前
キリスト教は神を信じ、神の子、救い主であるイエス・キリストを信じる宗教ということはよく知られていると思います。この神を「神(かみ)」とすることはもう定着していて、違和感を抱く人が少ないどころか、この語はキリスト教の専売特許の用語と思われているかもしれません。信者からも、信者でない人からも。しかし、日本には神道が昔からあり、神とはもともと日本宗教のもの。キリスト教の神を「神」と漢字表記し、「かみ」と呼ぶことが通例となり始めたのは、まさに明治からのことです。近代の日本語訳聖書の歴史をひもとくと、そこにたどりつくまで紆余曲折があったことがわかります。海老沢有道氏の『日本の聖書―聖書和訳の歴史』(日本基督教団出版局、1964年)がこのあたりを調べるのに重要な書物ですが、これを踏まえて批判的な検討を加えた鈴木範久氏の「『カミ』の訳語考」は、この問題に関するきわめて的確な論文です(『講座宗教学4 秘められた意味』東京大学出版会、1977年、281~330頁)。
「神(かみ)」という訳語が一般化した経緯
鈴木氏の所説に沿って、「神(かみ)」という訳語が定着するまでの経緯を簡単に見てみます:
(1)キリシタン時代、ザビエルがラテン語のデウス(神)を当初「大日」と訳したことは有名だが、ただちにその問題性に気づき、キリシタン時代のカトリック宣教の中では、ラテン語の「デウス」がそのまま使われた。一部で「天主」を使う例も見られた。
(2)近世中国では、「上帝」「天主」が使われていた。やがて中国人の礼拝との区別を問題とする論議(典礼問題)を経て、教皇庁は「天主」のみを公認し、中国的な信仰対象である「天」「上帝」は禁じた。
(3)ところが清朝中国に列強が進出し、英米人宣教師による布教が進むなか聖書の中国語訳に際して、Godの訳語として「上帝」か「神」かの大論争が起こった。英国系宣教師は「上帝」、米国系宣教師「神」をとり、併存するようになった。他方「天主」という訳語も提案されたが、承認されることはなかった。
(このあたりの文化の翻訳の問題については、柳父章著『「ゴッド」は神か上帝か』岩波書店、2001年が扱っていて重要)

1881年(明治14年)の新約聖書(国立国会図書館デジタルコレクションより)
(4)近代日本キリスト教の聖書誕生の先駆者であるギュツラフによるヨハネ福音書の訳(1837年)では、神が「ゴクラク」と訳されていた。ベッテルハイムによる翻訳(1855年)では、神は「シャウテイ」つまり中国での訳語「上帝」と訳されていたが、その改訂版(1873年)では「神」と訳されている。他方、有名なヘボンとブラウンによる1872年のルカ福音書、ヨハネ福音書の訳でも「神」と訳されている。その後、1880年に完成し諸教派の代表委員からなるいわゆる委員会訳(明治訳)でも「神」となり、以後定着する。
(5)このような経緯において、中国で「上帝」か「神」かの論争で問題になったほどの議論は生じなく、あっさりと決まったという。その背景に、(a) 中国語訳で「神」とする訳が日本にも流布していたこと、(b) 復古神道において「神」は創造者、至上者との観念をおびていたこと、(c) キリシタンが「天主」と訳していたことから「天主」が避けられたことがあるという。
カトリックでは長く続いた「天主」と「神」の二重状態
このようにプロテスタントの宣教師たちの共同翻訳事業を通じて「神(かみ)」という訳語が一般化していきました。カトリックの近代日本語訳にもプロテスタントの和訳事業に関わった高橋五郎が協力していたため「神」は自然に入ってきた一方、他の教会著作や祈りの中では「天主」も使われています。明治の終わり、1910年に出たラゲ訳新約聖書も「神」を採用し、カトリック教会の準標準訳となっていく過程で、「神」がカトリックの側では一般化していくようになったようです。
それでも、教会生活や教理教育書(カテキズム)、祈りにおいては「天主」が使われるという二重状態が長く続きます。そこで、『カトリック大辞典』第1巻(1940年)では、「神」という項目の冒頭に次のような断りを入れています。「カトリックではデウス (Deus) に対して天主の語を用い、教理に於いては神の語をつとめて避けることになっている。従って本辞典に於いても従来の慣習上已むを得ざる場合の外、特に教理に関しては教外者の理解を妨げざる限り成るべく神の代りに天主の語を用いることにした」。その上でこの「神」の項目の中で、哲学的な神論の文脈では「神」、キリスト教の教理に関するところでは「天主」を用いるという苦心をしています。
神が避けられた背景に、国家神道、天皇=現人神論との対峙があったことも知られているところです。ともかくこのような二重状態は、1959年に解消され、カトリックでも神呼称は統一されました。戦前からの変化が背景の一つであることはいうまでもありません。それでもなお、四半世紀祈りの生活では不思議な二重化がありました。ほんの四半世紀前の1993年まで、聖母マリアへの祈り、現在の「アヴェ・マリアの祈り」は「天使祝詞」または「めでたし」と呼ばれていて、そこでは、「天主の御母聖マリア、罪びとなるわれらのために今も臨終のときも祈りたまえ」と祈られていました。「神の母聖マリア」という言い方も教会で広まりつつあったなか、すでに暗唱して親しんでいた祈りのためか、我が口が「てんしゅのおんははせいマリア」と唱えていても、違和感も問題意識も生まれませんでした。
「神」問題再び?
上で紹介した鈴木範久氏は、キリスト教の神を日本語の「神(かみ)」と訳すことからキリスト教用語として一般化したなかで、神の均質化、画一化が起こってきた反面、多義化も進行したと指摘しています。日本の「カミ」との違いや緊張関係が宣教の場面で鋭く意識されたときもありますが、日本の「カミ」にしても多様化、多彩化し、また、キリスト教の「神」に対してさまざまな見方、考え方が湧き出てきているのが現代かもしれません。
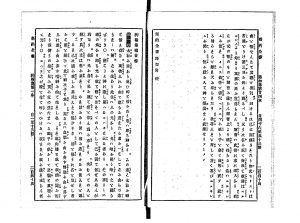
上記新約聖書のヨハネ福音書の冒頭部分(クリックで拡大、国立国会図書館デジタルコレクションより)
最近、カトリック信徒であるジャーナリストの南条俊二氏は『なぜ「神」なのですか -聖書のキーワードのルーツを求めて-』(燦葉出版社、2011年)で、「神(かみ)」という訳語が果たして適当であったのか、上述のような経緯の洗い出しと、再検討を提案しています。あっさりと定着しているかのような「神(かみ)」という用語の無力さを指摘しているという意味では、注目に値する問題提起です。
2016年には、「カミッてる」ということばが流行りました。プロ野球の世界で出てきた言い方です。新聞やネットニュースでも「神対応」「神疑問」といった、おそらく宗教とは無関係と思われる次元で「神」用語が目立つようになりました。耳をとめてみると、日本語世界のなかの「神(カミ)」という語感には案外なじむような、自然な感覚に驚かされます。そうした表現の余韻の中、教会で、ミサで、また典礼書・日本語訳聖書・神学書などで「神」という文字が出てきて、我が口で「かみ」と発音するとき、なんとなく違和感が増してきているのも事実です。気にしすぎでしょうか?
上述のような経緯を知ると、キリスト教の神が「神(かみ)」とされるようになってたかだか150年、今は普遍化しているといっても、ほんの5、60年のことにすぎません。しかも、日本語世界古来の「神」という漢字、「カミ」という音の世界にいわば間借りしているのも同然。にもかかわらず、キリスト教宣教というと、“間借り人がやたら偉そうなことを言う”だけにすぎなかった面があるのではないでしょうか。
「神(かみ)」という語を使うことの問題性やそこに本来含まれている緊張関係を新たに意識化することを、明治を思い起こす意義の一つと考えるのはいかがでしょうか。
(石井祥裕/AMOR編集長)