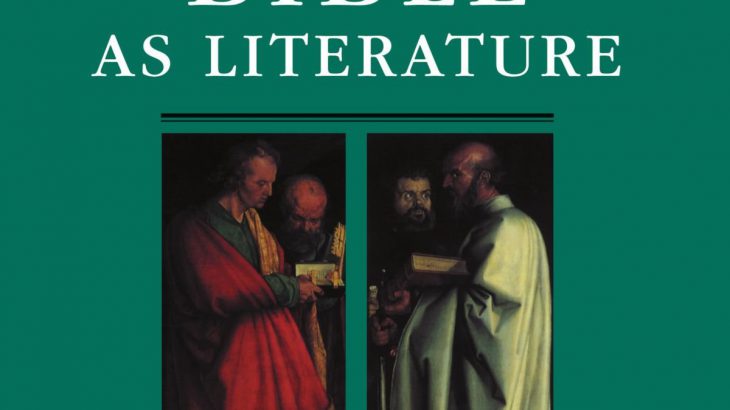聖書の新しい日本語訳が2018年暮れに登場するという。『聖書-日本聖書協会 共同訳』となるらしい。現代日本語訳聖書もずいぶん増えてくることになるが、この機会に、聖書の国語訳というものがその国の歴史の中でどのような意味をもつことになるのか、英訳聖書の事例に目を向けてみよう:
ディヴィッド・ノートン著『文学としての英訳聖書の歴史』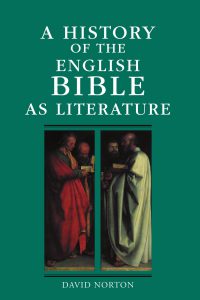
David Norton, A History of the English Bible as Literature(Cambridge: Cambridge University Press, 2000, xii+484pp)
本書は著者が1993年に世に問うた『文学としての聖書の歴史』全2巻を圧縮・改訂して1巻本にしたものである。その中心となっているのは17世紀に出来上がった、いわゆる「欽定英訳聖書」(Kings James Version)の文学史・批評史における運命である。それ以前の英訳聖書と20世紀になってからのこの訳の改訂、新しい聖書の翻訳はあくまでも著者が本題を語るための前備であり後日談といえよう。それは英文学史における「欽定訳聖書」の「正典化」のプロセスとそのプロセスからはじき出された英訳聖書の物語である。
【さらに読む】
イエズス会司祭である詩人ジェラールド・マンリー・ホプキンズ(生没年1844~1889)は、カトリックに転会したとき、英国教会の聖書つまり欽定訳を使うことができなくなり、「ドゥエー・ランス訳聖書」を使わなければならなくなったため詩作に支障をきたしたことを嘆いたといわれている(「ドゥエー・ランス訳聖書」とは、トリエント公会議によってカトリック公認訳と宣言された「ラテン語ウルガタ訳」に基づいて作られたカトリックの英訳聖書。イングランドでの弾圧を避けてフランスのドゥエーに移転していたカトリック神学校の教授マーティンが中心となって翻訳され、1582年に新約聖書、1609~10年に旧約聖書がランスで出版されたためドゥエー・ランス訳と呼ばれる)。今日、厳密な聖書本文校訂を反映した数々の公的、私的英訳によって、「欽定訳聖書」の圧倒的に権威付けられた地位は消滅している。
当初この英訳聖書の評判はたいしたものではなかったようで、数々の批判があったが、それでも、その渦中から19世紀までの間に、「欽定訳聖書」は英文学史上の傑作としての動かざる地歩を確立していった。ちょうどそれはロマン主義の時代にあたり、「欽定訳聖書」はロマン主義の詩人たちに愛読され、彼らの作品に影響を与え、称えられた。さらにそれ以後の聖書の英訳においても、この聖書はすべてのものを対比的に見るための規準とみなされ、影響を与え続けた。この評価の変遷史は、それぞれの時代の文学観、批評における意識づけが関係している。
近代における聖書英訳の歴史はまずナショナリズムを背景にした英国民の統一的言語、国語の創出への動きと密接な関係にある。著者はその歴史物語を中世の詩人・神秘家であるリチャード・ロール(1300頃~1349)の英訳詩編書とウィクリフ(1320/30~1384)の名が付されている英訳聖書から始める。近世ではティンダル(1494頃~1536)による訳からカンタベリー大司教クランマーと護国卿クロムウェルの命によって作られた「大聖書」(Great Bible, 1539~41年)等の欽定訳以前の翻訳の意図が問題にされている。「大聖書」と「ドゥエー・ランス訳聖書」が生まれる時代は、そもそも国語としての英語がどのようなものにならなければならないかをめぐる論争が背景にあった。つまり、アングロサクソン系統の語彙とラテン語起源の語彙をどう混合させるかの問題であり、それはまた聖書翻訳が宗教改革をめぐる政治的神学的論争を反映していたことも示している。
やがて現れた「ジェネーヴ訳聖書」(1557~60年。メアリ・テューダーによって迫害され、ジュネーヴに亡命した国教会聖職者ホイッティンガムによる翻訳)と国教会主教団によって作られた「主教聖書」(1568年)が加わって、それぞれの支持グループの間で論争が巻き起こる。それぞれの宗教的立場の違いによって翻訳が正確かどうか、あるいは相手の支持する翻訳が英語らしいかどうかが、たとえば「ドゥエー・ランス訳聖書」の訳者マーティンと「主教聖書」支持のファルクの間で戦わされた。
このような経過を背景にして「欽定訳聖書」が英国教会の公的聖書として現れたが、それでも1644年の最後の版まで「ジュネーヴ訳聖書」は流布し続けた。しかしやがて「欽定訳聖書」が「ジュネーヴ訳聖書」を駆逐し、反王党的傾向をもつとみなされた「ジュネーヴ訳聖書」に代わって事実上、英国民の公的聖書の地位を獲得した。ただ、このことは欽定訳の文学性が直ちに承認されたことを意味しない。その後、欽定訳は「雄弁な聖書」と絶賛され始め、詩人ジョン・ダン(1572~1631)がすべての古典を凌駕すると評価し、ミルトン(1608~1674)、バニヤン(1628~1688)によっても称えられたが、新古典主義の時代にはそれが文体のモデルになりうるかどうかをめぐって論争が起こった。
18世紀半ばロバート・ラウスが『ヘブライ人の聖なる詩について』によって聖書がローマ古典とは異なる基準で書かれており、その観点から評価するようになってから、その文学性が認められ、欽定訳の訳者たちが神からの霊感を受けていたという神話とそれが原文の文学的改訂であるとする神話が広まった。それと同時に、著者は、第3の神話、すなわち、欽定訳が出版と同時に絶大な人気を得たとする神話が現れたと述べている。しかしとにかく、ブレイク(1757~1827)、ワーズワース(1770~1850)、コールリッジ(1772~1834)、シェリー(1792~1822)、シャーロット・ブロンテ(1816~1855)らは聖書の中に文学的可能性を見つけた。バイロン(1788~1824)でさえも聖書を読み、作品中の人物のヒントを得ていた。それよりも、批評家ハズリット(1778~1830)が随筆の中で報告しているように、19世紀になってますます重要なのは一般読者による欽定訳評価の声であろう。これはヴィクトリア朝時代を通じて深まり、一歩では非国教徒の間での欽定訳使用の定着と他方では文学としてそれが優れた作品であるとの評価の定着につながった。D・H・ローレンス(1885~1930)の小説を読めば、「欽定訳聖書」なしにそれらが書かれなかったことがわかるであろう。
これら一連のことは別の聖書に依存したカトリック信者たちを、カトリック解放法にもかかわらず、そして19世紀後半の「カトリック・ルネサンス」と呼ばれたカトリック文学者の活躍にもかかわらず、英国文化の主流から疎外することになったことは、ホプキンズの話から想像できよう。
欽定訳は聖書をますます文学的傑作にしていった。また19世紀から20世紀にかけて学校制度が整備されていくと、特に米国で聖書が学校や大学で文学として教えられるようになる。今日「文学としての聖書」は、大学では一つの学科目になっているが、すでに19世紀末にはそれについての教科書や選集が現れていたのである。
※『新カトリック大事典』第3巻 「聖書の翻訳:英語」参照
(高柳俊一/英文学者)