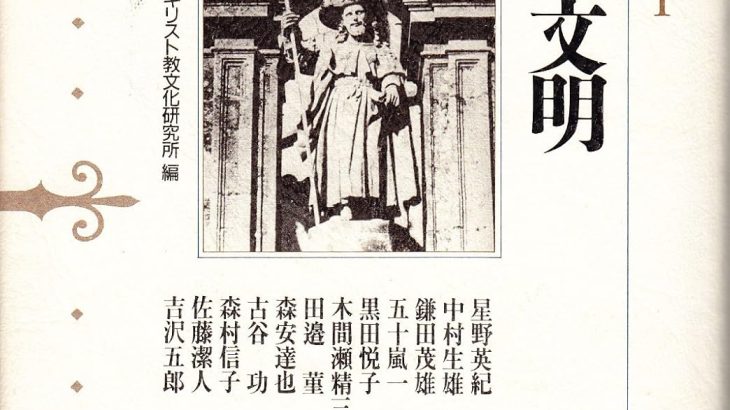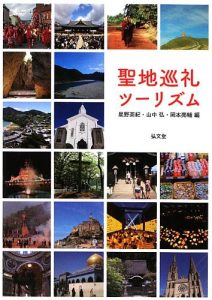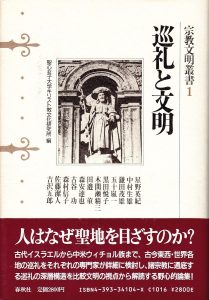AMOR編集部
「巡礼」ということばは日本では、カトリック教会でよく使われるほか、日本の宗教、仏教との関連でもよく使われることばのようです。巡礼について、具体的な地域に関する巡礼記はさまざまにありますが、それとは別に「巡礼っていったい何なのだろう?」と考えたいと思うとき、そして、巡礼が指すことがら全体について知りたい、考えたい、と思うとき、どんな本が参考になってくれるかを調べてみました。一般向きに編集されている幾つかの本がその扉になってくれます。
この主題に関して比較的新しい本がこれです。
近年の「聖地」や「巡礼」ということばの広がり、アニメの“聖地”などへの関心の広がりも視野に入れつつ、伝統的な聖地巡礼を含めて、現代の新しい宗教的感性の発生を考えていこうとしているものです。宗教学、宗教社会学という分野での研究ということでしょうが、新書版らしくとても親しみやすく語ってくれています。
その巻末参考文献リストも情報源として貴重です。著者の岡本亮輔氏(1979~ )は北海道大学教授。より学術的な著書として『聖地と祈りの宗教社会学――巡礼ツーリズムが生み出す共同性』(春風社 2012年)があります。
上記の岡本氏自身も編者として主軸を担っている書。3名の編者のほか38名の研究者が執筆参加する総覧型現代「聖地」ガイド。キリスト教関係としてはサンティアゴ・デ・コンポステラ、ルルド、エルサレム、パリなどのほか長崎の教会群が取り上げられています。とりわけ御巣鷹山が取り上げられる「悲劇と聖地」の章、靖国神社が取り上げられる「国家と聖地」の章、沖縄、広島・長崎、パールハーバーなどが取り上げられる「戦争と聖地」の章などは、巡礼への関心とこれについて考えることの重要さを認識させてくれます。
上記の書の編者の一人 星野英紀(えいき)氏(1943~ )は、大正大学名誉教授、宗教社会学・宗教人類学が専攻で、日本における巡礼の宗教学のパイオニア的存在のようです。新書版のこの書は、「巡礼とは何か」について、その普遍的な本質を考えたいと思うときの序説、私たちにとって貴重な入門書といえるものです。著者は四国遍路が主な研究領域で、『四国遍路の宗教学的研究――その構造と近現代の展開』(法蔵館 2001年)、浅川泰宏氏との共著『四国遍路――さまざまな祈りの世界』(吉川弘文館 2011年)などを著しています。
カトリック大学の研究所から出された、総勢12名の研究者が執筆参加している本書は、巡礼とは何かという問いかけを根底にしつつ、カトリックだけではない幅広い巡礼現象に視野を開かせてくれます。日本、中国、イスラム、そしてキリスト教に関係する歴史や諸地域として古代イスラエル、ビザンツ、中世西欧、イグナチオの巡礼、ロシアなどのさまざまな現象を取り上げていきます。巡礼とはどのようなことがらを指すのかを知るために欠かせない寄稿があります。
これらの文献で、巡礼の本質や構造を論じる際に、しばしば紹介されるのが、イギリスの文化人類学者ヴィクター・ターナー(Victor Turner, 1920~83)の学説です。ターナーについては、『儀礼の過程』(The ritual process: structure and anti-structure)という1969年刊行の主著が訳されており(思索社 1976年/ 新思索社 1996年/ちくま学芸文庫 2020年)、この分野ではよく知られています。
彼には、妻(Edith Turner)との共著で『キリスト教文化における表象と巡礼――人類学的展望』(Image and pilgrimage in Christian culture: anthropological perspectives, 1978)という著作があります。ここでの彼の学説が、上掲の文献を見ると、日本における巡礼論のいわば引き金になっている感があります。その意味では、巡礼をめぐる今日的議論はここ半世紀ほどのものと言えます。
調べてみると、各地域、個別の聖地巡礼の研究についてさまざまな書が見られますが、面白いのは「古寺巡礼」というタイトルの本が比較的多いことです。そうした流れの源流といえるのが和辻哲郎(1889~1960)の『古寺巡礼』(1919年、改訂版1947年)ではないかと思われます。飛鳥時代の寺、仏教美術の見物・鑑賞の旅の記録です。同じく和辻には『イタリア古寺巡礼』(1950年)という書があります。教会や聖堂を寺、寺院と呼ぶ形での聖堂巡りが古寺巡礼と呼ばれる流れの始まりといえるのでしょうか。
日本の寺・仏像を扱う古寺巡礼の書としては、ほかに写真家・土門拳の『古寺巡礼』全5巻(1963~75年)、佐藤昭夫他著『日本古寺巡礼』(1965年)、高橋富雄著『みちのく古寺巡礼』(1985年)などがあります。
海外について、アジアに関しては、建築史家・千原大五郎(1916~97)の『南の国の古寺巡礼――アジア建築の歴史』(1986年)、仏教学者・鎌田茂雄(1927~2001)のNHK取材班との共著『韓国古寺巡礼』シリーズ(1991年)、写真家・小松健一の『ヒマラヤ古寺巡礼』(2004年)、伊東照司の『インド東南アジア古寺巡礼』(1995年)と『バンコク古寺巡礼』(2020年)などの書があります。仏教のお寺巡りが主なものですので、古寺は自然です。
他方、ヨーロッパの関しても古寺巡礼というタイトルを付ける例が次のようなものです。美術史学者・小川光陽(1926~95)の『世界古寺巡礼――アテネとアンコールの間』(1969年)、カトリック信者の作家として知られる小川国夫(1927~2008)の『ヨーロッパ古寺巡礼――パリからサンチャゴまで』(1976年)。また、フランス中世史の専門家で、中公新書に『巡礼の道――西南ヨーロッパの歴史景観』(1980年)があり、『新カトリック大事典』の「巡礼」項目執筆者でもある渡邊昌美(1930~2016)には『フランスの聖者たち――古寺巡礼の手帖』(2008年)というタイトルの著書もあります。
これらの書籍を巡って気づくのは、日本語の「巡礼」という語が、古代から現代まで、古今東西の諸宗教、諸文化を包括的にとらえるための概念・用語になっているような事情です。
キリスト教の事柄だけだと思っている人には、日本をはじめアジアの諸宗教と対話するきっかけが巡礼にはあること、そして、日本の巡礼や遍路や参詣の伝統の中にある人には、巡礼という観点が、キリスト教やイスラム教の世界に対する扉になっていくかもしれないことを、考えさせてくれるのではないか、と思わされます。