Minori M C(Japan Christians Vox)
 小学生の頃、父と殉教について話した記憶がある。またキリシタン弾圧のような迫害の時代が来たらどうしようかとの私の問いに、父はこんなふうに答えた。
小学生の頃、父と殉教について話した記憶がある。またキリシタン弾圧のような迫害の時代が来たらどうしようかとの私の問いに、父はこんなふうに答えた。
――今は守るべき家族がいるから、お父さんは隠れて生きて信仰を伝える立場にまわると思う。
どうやら我が家は殉教せずに済むようだと、幼かった私は安心したのを覚えている。
数年後同じ話をした。
――お父さんは今だったら、キリスト教徒だと告白してしまうかもしれない。
私は高校生になっていた。殉教の意義はまだ見えていなかった。ただ普段合理的に物事を考える父が、生き延びる以外の選択をする可能性があるということが頭に残った。
「『ともに歩む教会』について黙想し、分かち合ってください」。パソコン越しに聞こえてくる声。
今年10月に開催されるシノドス(世界代表司教会議)に向けて、カトリック教会の中でも、自分たちのアイデンティティと役割を問い直す機運が高まってきている。世界中にいるカトリック信徒一人ひとりが、シノドスに向けて思いを巡らし、議論を深めることが求められている。
日本のカトリック青年も例外ではなく、1年以上のあいだシノドスをテーマとした集まりが多くなった。正直私はシノドスがどのような変化をもたらすものなのか見通しが立たず、理由も聞かされずに宿題を押しつけられたように感じていた。
黙想開始の合図とともに画面と音声を切り、伸びをしてコーヒーを淹れる。窓の外はもう暗くなっていた。「ともに」っていうのはわかるけど、「歩む」ってなんだろう。歩いてどこに行くんだろう。それはゴールが設定された旅なのだろうか? 私の頭の中の「教会」という白いもやのような物体が、ひょろひょろとした人の姿に形を変え、踊るように歩き始めた。
 気がついたら一つの光景が浮かんでいた。薄暗い雪の中を、身を寄せ合って歩く傷だらけの一団。長く続いたキリシタン迫害の、最初の犠牲者であり、日本で最初のカトリックの聖人となった26人。京都から長崎まで連行され、西坂の丘で十字架にかかって死んだ殉教者。「歩む」という言葉が引き金となり彼らのことが思い出されたのだろうが、そのとき突然霧が晴れるように、殉教の意味を理解した思いがした。
気がついたら一つの光景が浮かんでいた。薄暗い雪の中を、身を寄せ合って歩く傷だらけの一団。長く続いたキリシタン迫害の、最初の犠牲者であり、日本で最初のカトリックの聖人となった26人。京都から長崎まで連行され、西坂の丘で十字架にかかって死んだ殉教者。「歩む」という言葉が引き金となり彼らのことが思い出されたのだろうが、そのとき突然霧が晴れるように、殉教の意味を理解した思いがした。
彼ら26人はともに歩んだ教会だったのだ。命を懸ける価値があるものがもたらされたことを、身をもって告げ知らせてまわる使徒だった。子どもの頃から抱いていた私の殉教者たちに対するイメージが間違っていたことを思い知らされた。裏切りと密告、目を覆いたくなるような拷問の記録、時代が違えば自分も同じ目に遭っていたのではないかという恐れ……。完全に悲劇だと思っていた。あと300年遅くキリスト教が伝えられていれば、誰もこんな思いをしなくて済んだのに、と。
私が見ていたのは彼らの殉教の事実の、片面に過ぎなかった。
殉教の事実のもう片面は、心をつかんで離さない喜びであった。26人で唱えた祈り、絶えず彼らに働いた聖霊、牢にこだまする聖歌、彼らの姿を目にして堪えきれずに流れた民衆の涙、本当の意味で生きたという、静かな確信・・・。迫害され、聖堂が破壊し尽くされようが、ここに主の住まう教会があったのだ。彼らは天の国を目指して歩んだのではなく、天の国はすでに彼らのあいだにあり、それを奪うことは誰にもできなかった。
26人と彼らに続いた何千人もの日本における殉教者は失敗ではなく、この日本の地に美しく咲いた大輪の花であった。シノドスのための黙想を通して図らずも、このような気づきが私にもたらされたのだった。
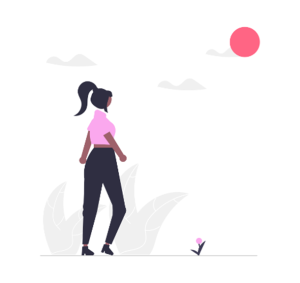 二十六聖人が捕らえられて歩んだ道のりは、現在「長崎への道」として知られている。京都から始まる全長900キロメートルのこの道を、今日でも「巡礼路」として歩んでいる人々がいる。二十六聖人の殉教を新たな目で見つめ始めたとき、この巡礼路に対する知見を深め、周知することが私の大きな使命の一つとなった。時代を超えて、彼らと「ともに歩む」この巡礼を少しでも多くの人と分かち合うため、巡礼路をさらに整備していくことが、私の人生の一つの目標である。
二十六聖人が捕らえられて歩んだ道のりは、現在「長崎への道」として知られている。京都から始まる全長900キロメートルのこの道を、今日でも「巡礼路」として歩んでいる人々がいる。二十六聖人の殉教を新たな目で見つめ始めたとき、この巡礼路に対する知見を深め、周知することが私の大きな使命の一つとなった。時代を超えて、彼らと「ともに歩む」この巡礼を少しでも多くの人と分かち合うため、巡礼路をさらに整備していくことが、私の人生の一つの目標である。










