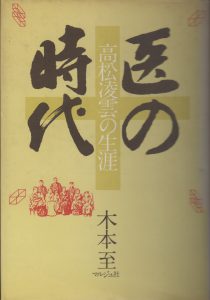寒さが続く冬の一日、それでも少しずつ春らしい日差しを感じる頃、谷中霊園に足を向けました。高松凌雲という人のお墓へ行こうと思ったからです。ずいぶんと久しぶりの谷中墓地でした。最初に高松凌雲のお墓に行ったのはいまから42年前、私が29歳のときでした。そのときのことに触れた「民学のたより」(「民学の会」1998年10月5日発行)に書いた記事を紹介します。高松凌雲のことを知っていただけたらと思います。
「ANAのボーイングが函館空港に着陸態勢にはいってから、にわかに耳の調子がおかしくなった。耳の奥へ差し込むような激痛が走ったのである。それも延々と続いた。地面に立って、バスに乗るまで、迎えに来てくれた瀬戸圭子ちゃん(「仮面の会」の仲間)の言葉さえはっきり聞こえなかった。二度目の函館行はとんだ出発になってしまった。
圭子ちゃんは湯の川に住んでいる。私たち夫婦は温泉に浸かりながらクリスマスを過ごそうと思った。普段の疲れをとるためには温泉が一番である。圭子ちゃんが東京暮らしを止めて、故郷の函館に戻ったと聞いていたので、早速追いかけることに決めたという次第である。実は数年前にも身体の不調から故郷に戻っていた圭子ちゃんを追いかけて、函館を訪れたことがあった。それで今回が二回目ということになる。
一度目の観光旅行と違って、今回は一応の目的もあった。それは土方歳三の最期の地である「一本木関門」に行ってみたかったからである。『新選組研究最前線 上』(新人物往来社)に「伝説の男(ひと)――土方歳三」を寄稿していたので、最期の地で手を合わせたかったのである。圭子ちゃんのお父さんに案内されて、まず「碧血碑」に行き、そして「一本木関門」の跡へ向かった。ここには当時の様子をうかがい知る術はもうないが、京都からこの地までの土方の心境を、いま一度想った。五稜郭は堀が凍って寒々としていた。しばら歩いていると市立函館博物館があった。明日は江差に復元された「開陽丸」を見物しよう思っていたので、ここには模型ぐらいはあるだろうと中に入ることにした。
展示室の2階のガラスケースを覗き込んでいると、どこかで見たことのある医療器具に出くわした。そう、この人だ。なんと懐かしい人に再会した。あれはいつ頃のことだったろうか。
1979年、私は桜井俊紀、大塚典正氏と出版社のマルジュ社を創った。最初に出した『逃げる兵』(渡辺憲央著)という沖縄戦での戦記物が好評で、なんとかスタートできたものの、それに続く話題性のあるものをと考えていた。私は、木本至さんに〈赤ひげ〉のような医者がいたらその人の伝記を書いていただけないかとお願いした。木本さんは、加藤時次郎か高松凌雲はどうだろうかと言ってくださった。もちろん私は両名ともまったく知らない人だったので、それは木本さんにおまかせした。
偶然にもNHKの大河ドラマが『獅子の時代』になり、幕末の会津を中心としたものであることが分かった。そこに奥詰医師として高松凌雲が登場するというのである。尾上菊五郎が凌雲に扮することも分かった。しかし、木本さんも私もNHKに便乗することは本義ではなかった。もともとこちら側の企画発想の趣旨があって高松凌雲を描こうとしたのだから、それは当然ではあった。
凌雲は、九州久留米藩の庄屋の三男坊として生まれ、幼少の頃は馬糞拾いから一日が始まったという。苦学の末医者となって将軍の脈をとるところまで
出世した。慶應3年に幕府の遣外使節の一員として、パリ大博覧会に出席することになる。ここで凌雲はフランス仕込みの医療技術を習得した。ガラスケースにあったフランス製とイギリス製の医療器具は、凌雲の生涯の宝物である。私はその写真を口絵に載せたかっ
たので、本郷の事務所から函館に電話をして了解を得たのである。そのとき、えらく遠くへ電話をしているような気がした。まさかその実物をこの目で見ようとは、そのときはそんなことがあったらと思ってはいたが、こんなふうに突然目に飛び込んでこようとは思いもかけなかった。
パリで凌雲が学んだことが、その後の凌雲の生涯を決定することになる。パリで凌雲が何を考え会得したのか。それはピサの斜塔で有名な町で見た、捕虜たちの扱い方であったろう。300名以上の一群の捕虜兵たちが繋がれて歩いているのを見た凌雲は、不審に思って調べた。それはフランスから秘密に送り込まれ、ローマで何事か起こさんとしていた者たちだった。それをガリバルディに知られて逮捕された。ガリバルディはフランス軍兵士として送ると不穏な事態になりかねないので、フランスの浪人として処理しようとしているのだということが分かった。当時の日本は武士道の国であって、「捕虜」の思想がなかった。安全を保証されて捕虜が本国へ送還されようとしている光景は、凌雲にとって衝撃だったにちがいない。
そして凌雲が、病院の無給助手のような形で働いたと思われる「オテル・デュー」での体験だろう。ノートルダム寺院に近いHotel-Dieuは「神の館」を意味するパリ市立病院である。ここはただの病院ではなく、医療費に事欠く貧しい市民に対しては、無料で医療をする施薬救療病院だったのである。人民共立の施設として制度化されたこのような医療のあり方は、まだ日本にはあり得なかった。そういったなかで凌雲がパリで幕府瓦解の報を聞いたとき、その胸に去来したものはなんであったろうか。
凌雲が横浜に戻ったとき、上野の戦争で彰義隊が敗れて、会津に向かっていた。凌雲も榎本武揚と開陽丸に乗って箱館を目指した。台場の上に病院をつくり、敵も味方もなく治療にあたり、さらには戦況が敗戦の色濃くなったとき、降伏を仲介する役目もしている。こうしたことを行動に移せたのは、あのパリでの体験だったろう。
しかし凌雲の生涯で特に感銘させられるのは、敗者となってからの活躍ではなかろうか。上野の桜木町に窮民医療のための同愛社を設立するのである。新政府からの誘いを断り、貧しい者のために医療技術を提供しようという精神は、明らかにフランスから吸収した思想からだったと思われる。自ら翻訳したものには、フランスの隣国ベルギーのドクトル「設児沕私」(セルウェス)が1863年に著した著述を『保嬰新書上下』として刊行している。そのほか日本の医学界に貢献した業績は限りない。
同愛社の社長に榎本武揚を据えているのも凌雲らしく、凌雲の喜寿(77歳)を祝う会が精養軒で催されたときには、凌雲のために徳川慶喜が揮毫した『至誠一貫』の文字が披露されたという。大正5年10月12日午前7時30分、高松凌雲は自宅で亡くなった。80年の生涯だった。
『医の時代―高松凌雲の生涯』(木本至著 1980年1月1日初版発行)が出来たとき、私は凌雲の墓のある谷中の墓地に行った。凌
雲に頭を下げた後、暮石の近くを掘って本を埋めた。あのとき函館は遠く遠くに感じられ、せめて私の思いが箱館までとどけと願って……。
五稜郭タワーの1階の展示室には、大きな肖像写真が3つ並んで掲げられている。榎本武揚、高松凌雲、土方歳三である。土方は箱館で死に、凌雲は負けても幕府に忠義を保ち、榎本は新政府のなかで近代化を進めた。それぞれに活きた3人を観ながら、私は榎本への視線を意識しはじめていた。
2日目は、圭子ちゃんの知り合いの気骨あるお坊さんに、自動車で江差まで連れて行ってもらった。開陽丸の甲板に立って明るい冬の日差しを浴びながら、幕末という時代を改めて考えていた。凌雲に再会できた喜びとともに、いま新たなる感慨をもった。
函館空港まで送ってくれた二人に、私たち夫婦はあまり愛想もなく飛行機に乗ってしまった。まだ耳の調子がよくなかったのと、どうも今度の函館は刺激が強すぎた。いつまでも続く耳鳴りは飛行機のせいばかりではなく、こころの準備不足、いや私の修行不足から来ているものかもしれなかったのだ。
東京に戻ってから、圭子ちゃんとお坊さんに、なぜかまた、たまらなく会いたくなってしまっているのである。」
木本さんは『医の時代』の最後で次のように書かれています。
「同愛社は太平洋戦争後まで、凌雲の遺志を守って続いた。ということは、大日本帝国が軍備に熱中し、人民の医療を放置していたという証明にもなる。戦後日本が福祉政策をとるようになると共に、同愛社は自然消滅した」
凌雲のお墓の前に立ち、愛ある医療活動に尽力した偉大なる先達に対し、手を合わせしばらく祈りのときを過ごしたのでした。
鵜飼清(評論家)