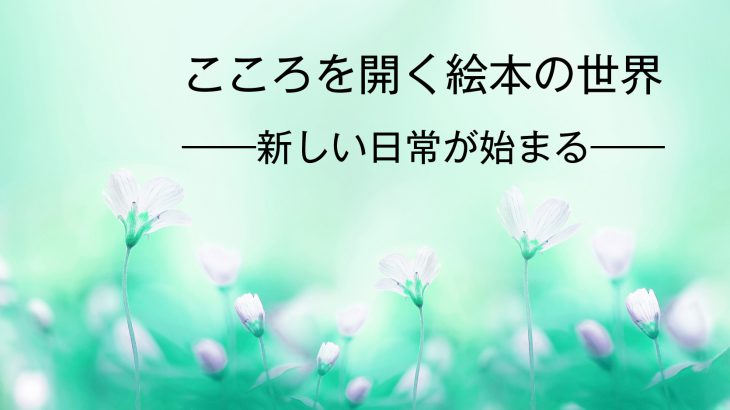山本潤子(絵本セラピスト)
自分史
「今年一年を振り返ってみましょう」という声が聞こえる季節を迎えました。年々、年齢という分母が増えていくので分子の一年はとても短く感じます。それでも一月からのスケジュール帳を遡ってみると様々な出来事がありました。そんな一年一年を分母の数だけ繋いでいくと、私だけの物語『自分史』が完成するのです。
自分史を書くことは出来事の良し悪しに関わらず、自分のたどってきた人生を肯定的に捉え、生き方を豊かに元気にするものなのだと感じています。人生の集大成としてある程度年配の方が書くものだと思っていましたが、私も50代前半に学んでいた心理系の講座で課題の一つとして取り組むことになりました。
まず、人生の主な出来事を年表にまとめます。誕生から保育園時代、それぞれの学生時代、社会人になってからは転勤・結婚・出産など時代ごとに起きたエピソードを箇条書きにするのです。項目に上がるような誰にでもある節目の出来事はすぐに書けますが、その間に起こった出来事を埋めていくのは簡単ではありません。晴れやかなエピソードはスラスラと進みますが、心が大きく動いた出来事を掘り起こし書き下ろす作業は、過去の感情と再び向き合うも時間でもあります。時間軸に沿って流れていくだけでなく、それぞれのエピソードに登場する家族や友人・知人のことなど、横にふくらむ出来事にも立ち止まって向き合わなければなりません。一つ一つが今の私を育てたこと、素通りすることは出来ないのです。
そして、何とか完成させた自分史ですが、数年後一冊の絵本を読んだ時、拍子抜けするほど簡単に書けるのではないかと気がつきました。
『つみきのいえ』
絵:加藤久仁生、文:平田研也、白泉社
海の中に家々が点在している町があります。その中の一軒の家におじいさんが一人で住んでいます。その家は浮かんでいるわけではなく、徐々に海水が上がってくる環境に合わせて上へ上へと積み木のように積み上げて建てられています。床下からは魚釣りができ、屋根の上では卵を産むニワトリやパンを焼く小麦も育てています。家の周りには行商人の船が行き交い必要なものを手に入れることができるのです。
ある年の冬、また水位が上がりおじいさんは新しい家を作りはじめました。ところが大工道具を落としてしまい、潜水服を着てザブンと道具を探しに潜った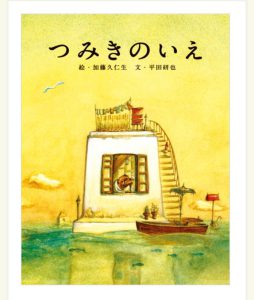 のです。大工道具が落ちていた家はおばあさんが家族に見守られながら息を引き取った家でした。その時おじいさんはずーっとおばあさんの手を握っていたことを思い出しました。おじいさんはもっと下の家にも潜ってみたくなりました。賑やかなカーニバルがあったこと、娘が嫁いだ家、子猫が行商人の船に乗っていなくなったことなど、何層にも積み重ねられたそれぞれの家には家族と過ごしたたくさんの思い出が詰まっていました。楽しかったこと、悲しかったこと、一軒一軒思い出をたどりながら一番下の家にまでやってきました。そこは、新婚時代におばあさんと暮らした小さな家でした。
のです。大工道具が落ちていた家はおばあさんが家族に見守られながら息を引き取った家でした。その時おじいさんはずーっとおばあさんの手を握っていたことを思い出しました。おじいさんはもっと下の家にも潜ってみたくなりました。賑やかなカーニバルがあったこと、娘が嫁いだ家、子猫が行商人の船に乗っていなくなったことなど、何層にも積み重ねられたそれぞれの家には家族と過ごしたたくさんの思い出が詰まっていました。楽しかったこと、悲しかったこと、一軒一軒思い出をたどりながら一番下の家にまでやってきました。そこは、新婚時代におばあさんと暮らした小さな家でした。
幼い頃からその土地で暮らしていたおじいさんとおばあさんは結婚して、そこに小さな家を建てました。水が上がるようになるとその土地を離れる人も増えましたが、おじいさんとおばあさんは家を積み重ねながら暮らしてきたのです。
絵本セラピーでこの絵本を読みました。絵本セラピーでは絵本に書いてある事実を取り上げ、一般化して問いかけることがあります。私はこの絵本から、おじいさんが積み上げた家の数だけ引っ越しをしたことを取り上げました。そして、私もこれまでにたくさんの引っ越しをしたことを話し、「皆さんは何回くらい引っ越しをしましたか?」と問いかけました。
引っ越したことがない人もいましたが、10回以上、15回以上の人もいました。
次に、「では、その中で印象に残っている家は?」と問いかけました。私自身、引っ越した家を指で数えながらとても気になった家があったからです。
一人一人語られる話はかけがえのない私物語です。
・新婚時代の家、不便な場所を日曜大工で直した。狭いけれど希望に満ちていました。
・親戚のクリーニング店、父母とは暮らしていなかったけれど、狭い部屋でちゃぶ台を囲んでいる時が私のほっとする時間でした。
・居場所がなかったように感じた嫁ぎ先の家、でも、子どもたちにとっては生まれ育った家です。義両親が高齢になり、今ようやく私の家になったような気がします。
家という引き出しから次々と過去の出来事が湧き上がり、そして、その時一緒にいた人や心が動いた出来事が語られたのです。絵本のおじいさんが一軒一軒の家で過去を回想するシーンと同じような状況ではないだろうかと考えました。絵本から自分史の年表を埋めていく本当に興味深い時間でした。
私は18歳でひとり暮らしを始めた時、父が決めた下宿が印象深いです。その家には大家さん夫婦の他に3人の男子学生と2人の女子学生、浪人生がひとりいました。
「銭湯に行くよ」と誰かの声がすると何人かが部屋から出てきて一緒に行きます。また、バイオリンを弾く男子学生が外国に行く日には、皆で羽田まで見送りに行きました。休日は年長の学生の部屋に集まり、故郷から届く食品を分け合い、賑やかに飲食しながらも東大を目指す一浪君を気遣ったものです。
狭い部屋でしたが下宿中が居場所のようで楽しかった事を覚えています。まるで兄弟姉妹のような、今では考えられない他人との面白い関わり方でした。
『つみきのいえ』とは積み重ねた人生そのもの、つまり自分史の比喩なのかもしれません。おじいさんが新しい家の屋根から「さあ、あなたも人生を振り返ってみましょう」と、笑っているかのようです。
季節の絵本
『アンナの赤いオーバー』
ハリエット・ジィーフェルト:ぶん、アニタ・ローベル:え、松川真弓:やく、評論社
アンナのオーバーは擦り切れて小さくなりました。お母さんは戦争が終わったら新しいオーバーを買ってあげようと言いましたが、戦後の街には売る物がなく、お金を持っている人もいません。
春になるとお母さんは持っていた金時計で羊飼いから羊毛を買い、夏にはランプと引き換えに糸つむぎのおばあさんから羊毛を紡いでもらいました。お母さん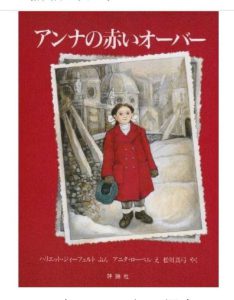 とアンナはその毛糸をコケモモで真っ赤に染め、乾かし、毛糸玉にしました。毛糸玉は機屋さんできれいな布地になり、お母さんはキラキラ光るガーネットの首飾りを渡しました。最後は仕立て屋さんです。きれいなティーポットをお礼にアンナは素敵なオーバーを着ることができたのです。
とアンナはその毛糸をコケモモで真っ赤に染め、乾かし、毛糸玉にしました。毛糸玉は機屋さんできれいな布地になり、お母さんはキラキラ光るガーネットの首飾りを渡しました。最後は仕立て屋さんです。きれいなティーポットをお礼にアンナは素敵なオーバーを着ることができたのです。
オーバーを手に入れるまで一年もの時間がかかりました。お母さんが大切にしていた品物はオーバーを作ってくれた4人の手に渡りました。お母さんが品物を選ぶ時、誰が何を喜ぶのかと相手を思う気持ちがあったことでしょう。お金がなかったからこそ、代金をもらう以上の喜びが伝わり渦を巻き、作った人にとってもかけがえのない素敵なオーバーになったのだと思いました。
この物語はノンフィクションです。お金も物もなくお店はあっても売るものがない、そんな誰もが貧しく苦しい時代です。ただオーバーを手に入れるだけではなく、暗く沈みがちな人々の心に光を灯すようなお母さんの行動、絵をじっくりみて文も繰り返し読みました。
「お金があれば欲しい物を手に入れることができる」そんな物流社会に暮らし、家にいながら指一本で買い物ができる時代です。近江商人の経営哲学にある「三方よし」という言葉を思い出しました。「売り手良し、買い手良し、世間良し」の三つです。商売において売り手と買い手が満足するのは当たり前、さらに社会にも良い影響があるという意味です。知識としては頭に入っていましたが、この絵本を読みながら「三方よし」を具体的に擬似体験することができたのだと思います。
クリスマスに招待された4人の人たちは、誰もがアンナの最高級のオーバーを自分の宝物のように感じていたことでしょう。仕上がったオーバーを着たアンナの嬉しそうな笑顔に、喜びと誇らしさを感じたことでしょう。明日への生きる力に繋がったに違いありません。社会貢献とはその先に、人間の尊厳を敬い生きる力が湧き上がるきっかけになるのだと思いました。
ところで、私はなぜ絵本を読み、語りたいのだろうと考えました。絵本には「三方よし」そのものが込められているのだと思います。作者と絵描きと出版社、デザイナーと編集者と……大勢の人が関わります。そして、書店に並び読者に届きます。
読み手が社会に向けて絵本を読みたくなるのは、創作から販売までに関わった人たちの社会貢献の流れが確かにあるから、これからも、迷わず前を向いて絵本を読み語ろうと改めて胸に刻むのでした。
(ここでご紹介した絵本を購入したい方は、ぜひ絵本の画像をクリックしてください。購入サイトに移行します)
東京理科大学理学部数学科卒業。国家公務員として勤務するも相次ぐ家族の喪失体験から「心と体」の関係を学び、1997年から相談業務を開始。2010年から絵本メンタルセラピーの概念を構築。