今年は、宗教改革500年にあたり、ルターに始まるあの運動が盛んに回顧され論じられている。この歴史的反省は、やがては、近代カトリック教会の揺籃といえるトリエント公会議にまで広げられていくであろう。更新された史料状況に基づく検証を示す書を紹介しよう:
ジョン・オマリー『トリエント――公会議で何が起こったか』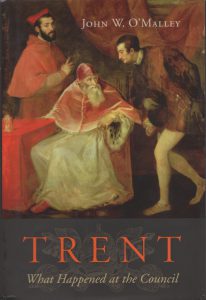
John O'Malley, Trent: What Happened at the Council,
(Cambridge Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press) 2013, 335 pages.
本書の著者オマリーは米国の著名な教会史家であり、イエズス会創立時代と第2バチカン公会議についての著書もある。今回は、トリエント公会議についての著書である。
15世紀末の低迷ぶりに教会の聖職階級内外から改革を求める声が上がっていた。コンスタンツ公会議(1414〜18年)は、俗人諸侯が3人の教皇座主張者の出現による教会分裂(西方教会大分裂)を解消し、教会規律の再確立をめざした公会議であった。しかし、教会分裂が解消され、教皇と教皇庁がローマに戻り、教皇の権威が再び確立されたのちも、神聖ローマ帝国領ドイツと中央ヨーロッパでは、ルターの追従者による改革の叫びが大きくなったので、皇帝カール5世(在位年1519〜56)は、教皇に新たに公会議を開くように強く要求した。当初、消極的であった教皇側もこれに応じざるを得なくなったが、公会議開催の場所をめぐって両者の交渉は長引いた。教皇側は、当初イタリア中部の都市、どちらかといえばローマに近いマントヴァで公会議を開こうとしていたが、ルターを支持するシュマルカルデン同盟の諸侯が反対し、帝国都市とはいえ皇帝の影響を受けないであろう、北イタリアのトリエントでの開催ということで合意し、公会議が開かれることになった。
著者は、この公会議の経緯を検証し、本来のトリエント公会議それ自体と、それ以後に派生し蓄積されたトリエント公会議以後の現象としての「トリエント(公会議的伝統)」を区別し、この公会議にまとわりつく誤解を歴史学的に払拭しようとしている。
【さらに読む】
著者はこの町が現在では中規模の都市になっていると書いているが、評者は、昔クリスマスに近いある日、ミュンヘンを朝6時に発ちローマに夜9時に着く列車で旅行したとき、トリエントの駅が小さく、ここがあのトリエントかと思ったことを今でも記憶している。半世紀前のことである。今では、ローマやイタリアの主要都市に行く旅行者の大部分は航空機を使うから、トリエント公会議に関心があっても実際にその町を通る者は少ないであろう。
16世紀当時、この町は帝国都市とはいえ、今よりもっと小さな山岳地帯の町であった。まず、このような小さな町に、ヨーロッパ各地から教会の高位聖職者と皇帝使節、随員、召使、それに聖職者顧問らのための宿泊施設や食料補給が可能なのか、ローマが本気で公会議を開くつもりなのかを疑う者も多かった。しかし、教皇パウルス3世(在位年1534〜49)の決意は堅く、フランス国王フランソア1世(在位年1515〜47)の軍隊を打ち破り、パリ近くまで侵攻していたカール5世は、スペインを含むヨーロッパ全土から配下の司教を送り込み、ベネディクト会修道院の院長や托鉢修道会の長上、諸国の大使が加わって、教皇使節モローネ枢機卿(生没年1509-80)の司式によって聖霊のミサが荘厳に祝われ、その5日後、最初の総会が開かれ、議事日程と議題が決められ、審議が始まった。
こうしてトリエント公会議は、1545〜47年、1551〜52年、1562〜63年の3つの会期を通じて18年にわたって続けられた。回を重ねるごとに参加者の数は増え、そのことは宿泊と食料補給の問題をいっそう差し迫ったものとした。加えて、この町の冬の寒さと夏の暑さに参加者は悩まされ、身体的疲労は長期にわたって、いつ終わるか先行きのわからない議論の連続に対する倦怠感を助長した。
この18年の間に、教皇はパウルス3世からユリウス3世(在位年1550〜55)、そしてピウス5世(在位年1566〜72)へと受け継がれ、神聖ローマ皇帝は、カール5世からフェルディナント1世(在位年1558〜64)の時代へと移り、フランスではフランソア1世とアンリ2世(在位年1547〜59)、スペインではフェリペ2世(在位年1556〜98)が頭角を現し、顧問神学者の中でアウグスチノ会のセリパンド(生没年1492〜1563)が最初の2期、イエズス会のライネス(生没年1512〜65)は最初の2期は教皇顧問神学者として、第3会期では総会長として、同じくイエズス会士サルメロン(生没年1515〜85)は全会期を通して教皇顧問神学者として抜きんでた活躍をした。数人の教皇代理の中で最後までその任にとどまったのはモローネ枢機卿であり、彼こそがさまざまな障害と行き詰まりを、卓越した能力によって克服し、トリエント公会議を成功裏に終了に導いた功労者であった。彼の成功は、第3期の途中にやっと姿を現したフランス勢の中心的人物シャルル・ド・ギーズ枢機卿(生没年1524〜74)の協力のおかげであった。そして、第3期まで常時200名だった参加者は、最後には280人になっていた。
なぜ、そのような緩慢な始まりだったのだろうか。アルプス以北のヨーロッパは政情、社会状況とも不安定であった。派遣する司教を選ぶ領主は、当然のことながら費用を抑えるために派遣司教の数を最小限にしていた。最後の会期では、イタリア勢がフィレンツェ、ハプスブルク家領のミラノ公とナポリを含めて多数を占め、アイルランド、中央ヨーロッパのハンガリー、チェコ、クロアチアからもごく少数の参加者があったが、ドイツ国内の宗教問題による騒動を終結させるのが、この公会議の当初の目的であったにもかかわらず、第2期をのぞいてドイツ勢はほとんど無に近かった。
コンスタンツ公会議では、諸侯つまり聖職者を含む諸国の大使が「オラトーレス」と呼ばれ、すべての会議に出席する権利を与えられており、会議の決定に大きな影響力をもっていた。しかし、ともかくも、コンスタンツ公会議に比べて、トリエント公会議は、聖職者が主導権をもった公会議であった。教皇はローマに在住し、枢機卿たちを集めた枢密院会議を定期的に開いていたので、教皇代理としてトリエントに派遣されていた数人をのぞいて大部分の枢機卿はローマにとどまっていた。教皇代理たちは、トリエントからローマへ議事録を送ったり、教皇から指令を仰いだりするために、多くの日時を要した。
18年もかかった公会議は、教皇にとって財政的に重い負担を背負わされる、結末の見えない事業であった。だから、彼らは教皇代理にしばしば強い調子で議事促進の指令を出した。それで「昔の公会議は聖霊が天から司教たちに降って進行したが、この公会議では聖霊がローマ教皇の指令の郵便袋によって到着する」と皮肉をささやかれたものである。
トリエント公会議についての書物といえば、ドイツの教会史家イェディン(生没年1900〜80)の『トリエント公会議史』全4巻(刊行年間1949〜75)が学問的な権威ある書物である。著者はイェディンに多くを依存しつつも、第2バチカン公会議以後の教会の現状に対する歴史的展望を読者に提供しようとしたと述べている。確かに、トリエント公会議は、ヨーロッパ内の不安定な状況に加えて、中央ヨーロッパと地中海へのイスラム(オスマン帝国)の進出による脅威の中で続けられた、教会刷新をめざした公会議であった。J.H.ニューマン(生没年1801〜90)が長い間、ローマ・カトリックへの改宗をためらった理由は、彼自身の言葉によれば、トリエント公会議がそれまでのキリスト教の伝統を捨てて、教会が昔の姿とは似ても似つかない代物に変わったと考えたからであった。
しかし、カトリック教会はまさにトリエント公会議によって近代への対応ができる教会になったのである。トリエント公会議は「祭具室の中での話し合い」では決してなく、近代に向かいつつある社会に対応する教義と制度に基づいて教会生活を確立しようとしたものであった。著者には、ぜひ19世紀末の第1バチカン公会議の評価も書いてもらいたいと思う。
(高柳俊一/英文学者)











なんか~
だんだんむずかしくなってきている気が~。