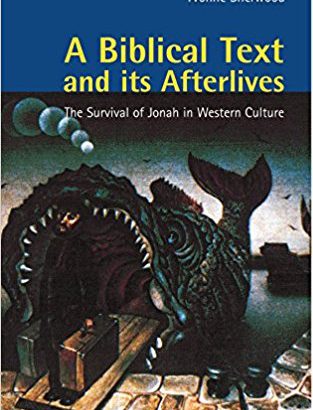たった4章だけの旧約聖書の小預言書、ヨナ書。そこに登場するヨナは、巨大な魚(鯨とは書かれていないが自然に想像してしまう)に呑み込まれたエピソードで有名である。この話のゆえにキリスト教美術でも人気がある。このヨナ書を、ヨーロッパ文化はどのように「読んで」きたのか。その精神史の陰影を探る一書である:
イヴォン・シャーウッド著『聖書テクストとその後の生命・西欧文化におけるヨナの生存』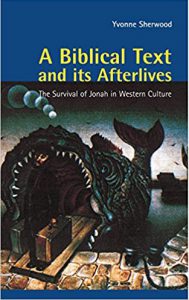
Yvonne Sherwood, Biblical Text and Its Afterlives: The Survival of Jonah in Western Culture
(Cambridge: Cambridge University Press, 2000), xii+321 pages.
旧約聖書のヨナ書は預言書の中に位置づけられているが、その位置は不安定である。他の預言書のように預言者ヨナが述べた預言から成り立つのではなく、ヨナにふりかかった出来事の物語であり、神から逃れた彼が鯨に呑み込まれ、3日3晩その内部にいてから吐き出され、ニネベで罪を悔い改めるように説いて回る物語である。ヨナは物語上の人物である。イエスも自分の復活を預言するのに使ったこの物語の主人公は、ヨセフやヨブと同じく、今日に至るまでさまざまな性格をもつ人物として描かれ、語られ続けてきた。ヨナとその物語は、聖書の中から外に出て、その後の長い生命をもっている。著者はその長い生存の歴史をたどる。ヨナ像の変遷は、聖書テクストとそれが読まれた文化との出会いの結実である。
【さらに読む】
ヨナの物語の読みは解釈から解釈を呼び起こし、主人公ヨナのイメージを変形し、それを取り巻く場である物語を変えていく。その始まりを、著者は、マタイとルカが伝えるイエスの説教にみられる分裂に置いている。両者の差違がヨナの変形の原動力となり、教父たちから宗教改革者たちに至る釈義に対する刺激となった。
教父たちは予型論的にヨナとイエスとの関係を説明した。たとえばヒエロニムスはヨナが神から逃れたということを、キリストが御父のいる天から逃れてタルシシュ、つまり「この世界の海」に向かったと説明した。逃亡するヨナは御父の家と国を棄てて人間となった受肉したキリストである。ヒエロニムスにとって、嵐の時、船底で眠っていたヨナは、共観福音書の中で嵐の湖で船の上で眠っていたイエスを指し示す。偽クリュソストモス文書では、船底で眠っていたヨナは聖母の胎内にいたキリストである。ヨナの物語をイエスに予型論的に結びつける過程はやがてイエスの受難物語に結びつけられるまでに成長する。
ヨナが神から逃れるために乗った船は、教会や世界あるいは会堂に変化し、それがヨナの犠牲によって破局から救われたと説明されるようになる。船乗りたちは教会という船を操っていたのだが、彼らはゲツセマネの園でイエスが彼らの慰めを必要としていたときに眠っていた使徒、あるいはキリストに死刑を宣告したローマ官憲、あるいはキリストに反対したユダヤ人になっていく。嵐は、人類の苦しみ、あるいは罪によって起こされた混乱、あるいはペトロやパウロが経験した嵐の予型、あるいはユダの心に忍び込んだ悪魔の悪巧みと説明され、このとき船乗りの一人が「イエスを船から海に投げ捨てた」とされた。
ヨナとキリストの関連は、宇宙論的、黙示録的に拡大され、キリストと悪魔の戦いとなる。大魚は、人類に害を及ぼす巨大なあらゆる敵の軍勢、その頭目、サタン、最初のアダムを誘惑によって敗北させた死と地獄の受肉したものとされる。その内部の暗黒世界ではあらゆる汚物が呑み込まれ、失われた霊魂が永遠にあえぎ苦しんでいる。ヨナ=キリストは、古代の石棺に刻まれているように、その中から復活して死に勝利したと説明された。
ヨナの物語のテーマである彼と主なる神との争いは都合良く忘れ去られ、ヨナの名前が「ハト」を意味するとされ、聖霊のしるしとされた。アイルランドの宣教師コルンバヌス(543頃〜615)は、自分の名前とハトの結びつきをもじって自分が受けた苦難をヨナのものになぞらえている。12万の人口のニネベは、イスラエルの12部族のものよりもはるかに多く、それゆえにユダヤ教に対する教会の勝利を予告していると、ベダ・ヴェネラビリス(672/73 〜735頃。イングランドの司祭、神学者、歴史家)は釈義したが、ここに、ヨナ書の解説で初めて反ユダヤ主義が現れたと著者は考えている
教父の時代から中世の終わりまでのヨナに好意的な解釈は、宗教改革の時代に転機を迎える。ルター(1483〜1546)の説教によって、ヨナのユダヤ人としての性格が強調される。ルターは、一方ではヨナ=キリストの予型説、ヨナ=聖霊説を受け入れたが、ユダヤ人ヨナを神の意志に対応する頑迷な姿勢を示した人物、新約が取って代わる瞬間の、死に絶えようとする旧約を代表する人物を見ている。復活の予型というテーマは、大魚の体内の暗黒世界から新しい人に変化して現れた人物として、ルターがヨナを見るきっかけになっている。
ルターが、ヨナをユダヤ人とし、キリスト教徒にとっての「敵対者」として対照的に位置づけたのに対して、カルヴァン(1509〜1564)は、ヨナの物語を「教会=キリスト教徒共同体」内の敵対者の象徴と見て、教会内の規律を保つために用いた。ヨナの物語における嵐は、カルヴァンによれば、揺れ動く個人の良心の世界である。大魚の体内は地獄あるいは墓場、ヨナが引き込まれることを強いられた法廷であると同時に、驚くべきことに、それが病院であるとも説く。著者はミシェル・フーコー(1926〜1984)の『監獄の誕生:監視と刑罰』(1975)に言及しながら、カルヴァンは魚の体内に地獄の炎を見て、それがヨナの良心の呵責だと説明しているが、それはヨナの問題を外的世界から内面の世界へ向けることになる。キリスト教徒は自分の心の中の「敵対者」の誘惑に対決しなければならない。こうしてヨナは、心理的葛藤のドラマの中に位置づけられることになった。
以後、啓蒙期から19世紀にかけての聖書学の確立に至る過程で、ヨナは啓蒙主義哲学の代弁者に仕立て上げられていく。シュライエルマハー(1768〜1834)とアドルフ・フォン・ハルナック(1851〜1930)は、新約の純粋に倫理的宗教が旧約の抑圧的一神教に取って代わり、アブラハムの子孫は迷信にしがみつく古い時代の残り物であるとみなした。ハルナックは、旧約聖書が新約聖書の後に付録としてつけなければならないと主張した。ユダヤ系詩人ハイネ(1797〜1856)にとって,ヨナ書は迷信と排他性を乗り越えて西欧文化への入場券を手にするための格好な文献であった。ユダヤ教は古めかしく、時代遅れ、偏狭な神の声に対して抵抗した合理主義者として、旧約の内部からユダヤ教を非難した人物とみなされるようになる。ヨナ書は「原福音書」として、ユダヤ教を棄てて近代化の道を取るための道しるべとなった。
19世紀半ばになると、エドワード・ピュージ(1800〜1882。イングランド国教会の司祭。教父叢書の創刊者)の注釈に見られるように、古生物学や海洋生物学の発達のおかげで、注釈者たちはヨナ書の大魚に注目するようになった。彼は動物学的知見によってこの大魚の大きさを特定し、そのような生物が実在することを証明しようとした。そうすることによって、彼はダーウィン(1809〜1882)の進化論における生命の自然的連続の中に聖書を位置づけ、聖書のテクストを自然史の一部に組み入れようとしたのである。
著者は、ここまでをヨナについての思想・文化・文学史の表層における主流部分と位置づけ、以後を底流の部分として、ユダヤ教の旧約聖書ミドラシュ(ユダヤ教的聖書解釈)における解釈とそれが生み出した続編物語、さらに民間伝承の産物を分析している。その際、著者は19世紀のミドラシュと14世紀の二つのミドラシュを取り上げている。キリスト教のヨナの取り扱いにおいて、予型論を主流としたところの聖書の世界が自然科学の世界に組み込まれることができるかどうか、その意味で近代的な思考の世界に属しうるかの問題に焦点を置くものとなっていったが、ミドラシュの伝統は、ヨナの物語を旧約聖書の他のテクストに結びつける。そして、イディシュ語(ヘブライ語的要素の混合したドイツ語で、中東欧ユダヤ人の言語)の非論理的な語呂合わせ、語源解説および旧約聖書の他のテクストの引用や言及による、荒唐無稽で、ますます拡大して終わりのない喜劇的世界の中で不安定に動き回る「生き物」にしている。ミドラシュによるヨナ物語は、大魚の体内の暗黒の世界とヨナの苦しみとそこから解放されても癒されない絶望に、ブラックユーモアの感覚をもって集中しているようである。
このようなヨナ像は過去の主流のヨナ像とは正反対のものである。ミドラシュにおける、正統的なものとは違うヨナ像は、中世伝承・文学から近代文学にかけてのヨナ物語と一脈通じるものがある。著者はその要素がポストモダン文学につながっていくと考えているようである。中世物語文学では、『ヨナの物語』(Carmen de Jona)や14世紀の『忍耐』(Patience)のヨナが、呑み込まれた鯨の体内の世界につながる。この世界の「不気味さ」は、たとえばフランソア・ラブレー(1494頃~1553頃)の『ガルガンチュア物語』では滑稽なブラックユーモアの世界において表現される。あるいは絵ではヒエロニムス・ボス(1450頃~1516。ネーデルラントの画家)の混沌世界に発展していく。イディシュ的ユーモアは、ジョージ・オーウェル(1903 〜1950。イギリスの作家。『1984年』で知られる)の有名な随筆「鯨の体内」につながり、それが作品引用による滑稽な混沌世界に拡大されれば、ジョイス(1882〜1941。アイルランドの小説家)の『ユリシーズ』の世界になっていく。
著者は、解釈の主流と底流の伝統枠からヨナを救い出そうとし、それを新しい、ポストモダンの不確定な神義論の現場に位置づけようとしている。そして、そこに聖書学の将来があることを暗示する。
(高柳俊一/英文学者)