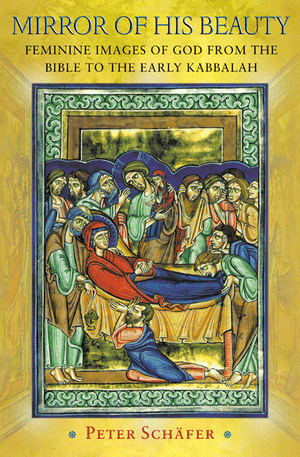神の女性性や母性を重視する傾向は、現代の神学思想のひとつの特徴といえる。このテーマを旧約聖書からユダヤ教の神秘思想までを含む大きな歴史的展望で探り出そうとした研究を紹介し、論評を加えながら正しいアプローチの道を考える:
ピーター・シェーファー著『神の美しさの鏡:聖書から初期カバラに至る神の女性イメージ』
Peter Schäfer, Mirror of His Beauty: Feminine Images of God from the Bible to the Early Kabbalah (Princeton: Princeton University Press, 2002), xiv+305 pages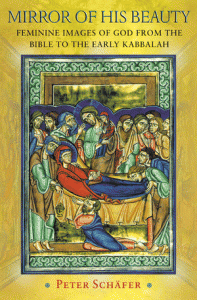
聖書における知恵の重要さは聖書学、教父学のほかキリスト教思想研究において知れ渡っている。旧約聖書の知恵文学は新約聖書のキリスト像形成に深い影響を与えた。この点に関しての文献は豊富であるが、本書はむしろ、一神教でヤーウェ信仰であるユダヤ教が神についての女性イメージを形成し、後にキリスト教と接触していく様子、そして12世紀のユダヤ教内の神秘主義的傾向(初期カバラ主義)がキリスト教の聖母信心の影響を受けて、神を女性イメージで捉えるようになるまでの経過を跡づけている。最後の段階は、突如12世紀に現れたように見えるが、それはグノーシス主義的異端派の流れが地下に連続しており、クレルヴォーのベルナルドゥス(1090頃-1153)の聖母についての熱狂的な説教がユダヤ教徒にも影響を及ぼしたことから表面に現れたと著者は考えている。このようにして、キリスト教とユダヤ教の思想的相互関係を展望したところに本書の貢献がある。
【さらに読む】
知恵を意味するヘブライ語ホクマーあるいはギリシア語ソフィアは女性名詞である。ユダヤ教の厳格な一神教的姿勢はヤーウェ信仰にメシアニズムが結びついて成立したのであろうと思われる。著者は、ユダヤ教の形成初期の事情に結びつけて、多神教からの決定的進歩とみなされているこのメシア的一神教が、ある時代に突然起こった革命によるものではなく、周辺文化の多神教の要素を組み入れつつ行われた総合の結果であることを指摘する。聖書は周辺の宗教的習慣を採用し、自分たちに合うものとしながら一神教的色彩を強めていたのである。
そのため、民衆的なユダヤ教においては多神教の要素が生存し続け、預言者たちはそれに対抗する運動を続けざるを得なかった。その有名な例として、カナン人たちの神殿における最高神エルの配偶者女性神アシェラーが、実際のユダヤ人の宗教生活においてバアルとして根強く信仰されていた事実が聖書によって確認できる。最近の多くの発見に拠りながら、著者は、イスラエルの一神教がより広範な展望における一方の極をなすのに対して、他方には多神教があって、両者の間には多くの可能な形態があったとする。たしかに、紀元前7世紀のヨシヤ王(在位 前640/39-609)の改革によって、ユダヤ教は決定的にエルサレムの神殿を中心とするようになり、イスラエルの信仰の祈り「我らの神、主は唯一の主である」(申命記6・4)はユダヤ教の宗教生活の一部となったが、その宗教史はもっと複雑であった。そして、ユダヤ教の厳格な一神教のイメージにもっとも合わないものがカバリズムであると、著者は考える。
カバリズムは、神の超越的次元と神が人間に示した次元に区別し、唯一の神が自らを10の属性「セフィロート」(=「数」の意味)で示すと考える。その中の一つは女性的なものであり、シェキナと呼んでいる(シェキナは女性名詞)。古典的ラビ思想では、シェキナは世界における神の内住を意味し、元来女性的な特徴をもっていなかったが、カバリズムにとって、シェキナは神の内的生命の原理であるばかりでなく、女性原理であるとされるようになった。セフィロートとシェキナの考え方を含むカバリズムの最初の文献は12世紀の『バヒール』(『セフェル・ハ・バヒール』ともいう。「清明の書」の意)である。
著者は、この12世紀の『バヒール』を軸として旧約の知恵文学からアレクサンドリアのフィロン(前25-後45)、キリスト教の異端であるグノーシス主義を振り返り、その思想とキリスト教との接触の過程を跡づけていく。旧約聖書の知恵文学を取り扱う際、ヨブ記から始める。そこでは、知恵はまだ抽象的原理で人格化されておらず、また女性でもなく中性的なものであった。それが、箴言では、知恵は地上における神の存在として神の幼い娘となる。さらにシラ書と知恵の書では知恵は律法となり、神の活力の手段、神の配偶者として女性的人格存在になっていく。その後、ユダヤ人哲学者フィロンにおいて、知恵はモーセ五書ばかりでなくその後の文書でも働くものとしてロゴスと霊に一体化され、人間に知恵をもたらす神の娘となり、彼女に勇気づけられて人間は自分の配偶者として知恵を求めるようになると考えられる。その結果、人間は市民本来の生活を構成するものを超える「完全な徳」をもつようになるのである。著者は、フィロンにおいてユダヤ教の知恵論は最高の頂に達し、それがキリスト教によって取り上げられたとしている。そしてキリスト教がそれを知恵の人格化としての聖母マリアの信心に発展させたと考える。フィロンはパウロとほとんど同時代の人であった。
ところが、著者はこのあと、意外なことに、共観福音書における知恵のみならず、コロサイ書やエフェソ書のようなパウロ的手紙やヤコブ書における知恵、ヨハネ福音書序文における内包された知恵とことば(ロゴス)の結びつきを完全に無視して、新約聖書外典の『ヨハネ行伝』やエイレナイオス(130/40-202頃)の『異端反駁論』に見られるようなグノーシス主義の考え方に目を向け、知恵の思想がその役割を回復するのは西暦70年以後、ユダヤ戦争によるエルサレム破壊の痛手から立ち直ったユダヤ教のラビ思想においてであったと主張する。著者によれば、それまでのユダヤ教の知恵の展開は、ユダヤ戦争以後の空白によって絶たれ、以後のラビたちは自らを伝統的なホクマー(知恵)すなわち律法の解説者ホクマミム(賢者)と称した。彼らによると、神ヤーウェは唯一の創造者であり、旧約聖書の「シオンの娘」のたとえに基づいて民イスラエルは神の配偶者、娘、妹であった(詩編45・11他参照)。雅歌における「愛する人」は神ヤーウェであり、「愛される人」は民イスラエルであった。ラビのミドラシュ(聖書解釈)は驚くべきことにイザヤ54章1節の“母”を民イスラエルに帰した。このようにして、イスラエルが神がいます場として母のイメージで捉えられた。それがシェキナである。創造の知恵を唯一の神に帰することで、その内住の場シェキナはしだいに人格化され、女性として取り扱われるようになったのである。
著者は、ラビ思想の律法解釈におけるシェキナの理念の展開から、マイモニデス(1135-1204)ら中世ユダヤ教哲学者たちがプラトンやアリストテレスの哲学を導入して、カボード(神の栄光)とシェキナの領域を最初に創造された光の領域と捉え、カボード・シェキナを神の本質(知恵)の顕現としたことを跡づける。彼らは神の本質は女性的なものとして捉えたが、まだ性的なものとしては考えていなかった。12世紀のカバリズムの書『バヒール』は、ここから一歩進んでシェキナを性的な意味における女性に仕立て上げたと著者は考えており、その価値を高く評価する。
この書は、南フランスのカタリ派やアルビ派のような、グノーシス主義の復活ともいえるキリスト教異端勢力が強かった地域を背景にしており、当然その精神的雰囲気の中で生まれたユダヤ教思想の形態を反映していた。著者は、キリスト教の教会の側で、その異端に対抗するために聖母マリアの信心を強硬に推進する説教運動が十字軍運動との関連で展開されたことを指摘している。ベルナルドゥスの説教もこの文脈において、正統信仰復興のために強烈な聖母マリア信心を推進するためのものであった。その同じ地域のユダヤ教に、内住する神の本質である知恵を女性とする神秘主義的傾向が生まれていたと、著者は考えるのである。
本書は、知恵の思想史と諸宗教における理念の交流をテーマにした興味ある研究である。しかしすでに指摘したように簡単に賛成しかねる点をもっている。シェキナとマリアの共通点が救済的機能であるとし、マリアがその息子キリストのメシア的性格の大部分を吸収しているとする論点も、おそらく民衆宗教に関してはいわれうることだろうが、不正確な指摘と言わざるをえない。また、著者が、新約聖書におけるキリスト論が旧約および両約時代の知恵論なしには考えられないことについて、特にパウロ的手紙における宇宙論的知恵としてのキリスト論について、まったく関知していないのは不思議である。正統キリスト教伝統において、知恵は宇宙の原理であるとともに、救済史の原動力であるということが見過ごされているのである。
(高柳俊一/英文学者)